−荒天日記 3−
Copyright (C) s-maru 1996
1992年11月1日 午前8時半頃に再び風が凪いだ。さて出漁だ。 風もなく波{のた}も減ったとはいえ、やっぱり海面{うみづら}は荒い。 船は波一枚一枚叩き伏せながら進む。 第八誠福丸は操舵室が面{おもて:船の前方}にあるので、ラットを握る私 は、一緒に舞い上げられたりドッパーンと叩きつけられたりで腰に堪える。凪 いでるとはいえ冬の日本海。体の位置の高低差は3〜4メートルになる。 まず、波で船が振り回されるので舵がきかない。でもちゃんとコツというも のはあって、波を先読みしながらラットを回していけば船は進路を保つことが できる。 ときたまこれを暗闇でやらないといけないことがあるのだが、最近夜目がき くようになって、先輩達がどうやってそうしていたのかが初めて理解できた。 網場にたどり着き、浮子{あば:ラグビーボール大の浮き}がズラリと並ん でいる中へ船を入れるのだが、これはちゃんと場所が決っている。エンジンの 回転をスローにしてペラの推進力が落ちると、舵は全くきかなくなるので、前 もって行き足{いきあし:惰力}をつけておかなければならない。 行き足をつけるためには、船を入れる手前で風と潮流と波と慣性力とを先読 みして、舳先をどの辺に向けるか、スロットルをどれくらい開けるかを決めて 突っ込んでいかなければならない。 張られたロープに船係りの綱がついているので、これを竿鈎で拾って素早く ウィンチで巻き付けるため、キチンとその場所へ船を着けなければいけない。 つかまってしまえばこっちのもんで、あとは網をおこしていくだけなのだが、 揚網機の使い方を波もち{のたもち:波のリズム}に合わせてやらないと、網 がジョワーっと裂けてしまうのだ。 どうにかこうにか網をおこし、めでたく魚をとって港に帰る。今日はカマス がけっこうあった。金額にして20万円くらいの漁だ。 一日平均10万円の水揚げが必要なので、昨日出漁できなかったため、 今日は2日分。だいたいカツカツの漁だ。今日も若狭湾でたった1件の操業だ った。一日一日がおまんまの種である漁師は、とにかく少しでも多く操業した 者の勝ちである。 そして、このような無理をして漁に出るのにはもう一つの理由がある。民宿 でお客に新鮮な魚を食べさせるためなのだ。普通どこの旅館でも、時化が続く と、3日ぐらい前の魚や、養殖物や、若狭湾でとれるはずのない伊勢海老だと か、冷凍魚を使わざるを得なくなるのだが、うちの場合はそのようなことは全 くない。 観光業不振の中、うちの民宿が賑わっている所以である。 |

|
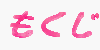
|
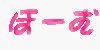
|