−荒天日記夏の編 3−
Copyright (C) s-maru 1996
|
夏も終りに近づくと、波止場では、巣立ったツバメのヒナ達が編隊を組んで飛行訓練を始める。かわいいんだよね、5、6羽が揃い踏み(揃い羽?)で赤とんぼみたいにスーっと飛んで、そんなファミリーが何十組もいて、ちっちゃいヒナ達は、波止場の回りから離れることなく飛び続けている。 生き残ったヒナ達、秋には南に向かってまた飛んで行く。 荷揚げ場の上屋根は、天井の隅という隅いたるところにツバメの巣がある。合計で30個ぐらいあるんだけど、雀に乗っ取られてヒナだけが入れ替わってるのに気づかずに餌を与え続けていた親鳥は、巣立った雀を今も自分達のヒナだと信じているのだろうか。 落されて干からびた燕の雛を6月頃にはたくさん見た。毎年憂鬱になる光景である。 荷揚げ場には、砕氷機がある。モーターの動力を減速機にかけてトルクを上げ、二本の太い鉄の棒を回すようになっているのだが、その鉄棒には鷹のくちばしのような鋭い刃がいくつもついている。 その間に重さ64kgの四角い氷塊が乗ると、吸い込むように刃は回る。 午前3時半、四角い鉄の箱の中にある砕氷機を回して、出漁前、砕氷を船に積んでおくのが、私達の一日の始まりである。 砕氷機はほとんど天井近くに設置されている。氷を持ち上げるためのリフトの設備もある。もちろんそれらは貯氷庫のすぐそばにある。砕氷は上から降って来るわけだ。それをケースに受け止めて船に積む。 ある朝、巣から離れたばかりでまだ飛ぶことが出来ないヒナが、砕氷機を回した途端に吐き出されて私の目の前に落ちてきた。刃の間隔はヒナの身体よりもわずかに広く、無傷であった。 そのうち、氷塊が砕かれ始め、ケースを構えてそれを受け止めた。ふと氷を見ると、なんだか血がついている。砕氷機の中にはもう一羽別のヒナがいたのだ。空回りならば無傷ですむのだが、氷塊と一緒に入り込んだらひとたまりもない。 最初の一羽はとにかく助かった。それだけでも救いだ。生き残ったヒナを、近くの台の上に置いて出漁したのだが、帰ってから見たら、もういなかった。回復して飛べるようになったのか、猫にもって行かれたのかは不明である。 その日はなぜか、10年前の真冬の出来事を思い出していた。沖で風にあい、命からがら波止場へ逃げてきた日のことである。静かだった海が突然荒れ狂った。 当時の船は全長14メートル。波止場へ戻るためには波に逆らって走らなければならなかった。日本海の波は波長が短いため、三角に切り立ったような波になる。波に向かう度にまっ縦になり、のぼりつめてまた落ちる。そんなことをいったい何回ぐらい繰り返しただろうか。全然進んでる感じがしない。上ったり降りたりしているだけだ。 一枚一枚、波をかけあがる時、船の舳先よりもはるか上の方で、海水のトンネルが形成される。 鉛色の空をジェット機よりも速い雲が走り、乗り越えた波の向こう側の谷間へ船が向かうときにはただ海底が待っているようにしか思えなかった。目の前も頭の上も全て藍色の海面なのである。 港が見えた時には、まだ緊張状態が続いていて、黙々と事務的に必要な作業をしていたが、魚を揚げて船を定位置におさめて合羽を脱いだ時になって初めて、背中を脂汗が伝った。 そんな日のことが、なぜか思い出された。 |

|
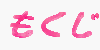
|
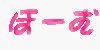
|