自作ノベルス
Copyright (C) by s-maru 2004
|
涙絵 ある夕方、バイトが終わってアパートに帰ると、お袋が来ていて勝手に掃除していた。 「なにやってんだよ!」 「どうせ散らかしてると思って片付けに来てやったのさ、ふん」 お袋は、押入の中のものを手当たり次第に畳の上へ放り出している。 とっさに、3枚の絵のことが気になった。幼稚園の時に自分が描いた絵を3枚、家から持ってきて押入にしまってあったのだ。掃除をやめさせて絵があるかどうか確かめようとしたが、目の前に土鍋を差し出されて受け取ってしまった。1ヶ月くらい前に友達を呼んで寄せ鍋したときのやつで、洗わずに中身が残ったまま押入に突っ込んであったのだ。ふたを開けてみるとカビの塊で一杯だ。ばつが悪くて言葉に詰まった。 「絵は、絵はどうした?」 少し弱気になりながら訊くと、 「ここにあるだろ」 押入の隅を指さす。大きめの画用紙が2枚、隅に立てかけられていた。動かされた様子はない。少しホッとした。でも、あと1枚の落書き帳から抜き出したやつを入れた封筒が見あたらない。 「一緒にあった封筒は?」 「捨てたよ」 「す……!?」 怒りで声が出なかった。お袋の肩をつかんで後ろへ投げた。お袋は驚いて何か言ったが、そのまま玄関口の方へ歩いていった。捨てぜりふに、 「ガラクタばっかり集めてんじゃねーよ、あほー」 と言った。 「きさまの顔なんか見たくもねーよ、はやく出ていきやがれ!」 俺に言える精一杯の罵り言葉をあびせかけてやると、お袋はさっさと出ていった。 ばかやろー。 つまんない幼児画かもしれない、でも俺にはとても大切なものだった。五才の時に初めて描いた親父の顔だったんだ。 俺はゴミ箱をひっくり返して封筒をさがした。でもゴミはすでに全部出された後で、何にも残っていないのだ。アパートの裏のゴミ置き場まで行ってみたが、すでに運び去られていた。 体中の筋肉が、時間を拒絶してしまった。 かろうじて部屋まで戻ったが、何もする気になれず寝ころんだ。 親父は、チャンバラごっこしてくれたり寝床で絵本を読んでくれたり、すごく可愛がってくれた。風邪ひいて鼻がつまって苦しんでるときなんか、汚い話だけど鼻水を口で吸い上げてくれたりした。熱が下がらないと、一晩中濡れタオルを取り替えてくれた。 ぐうたらなお袋は、俺が病気になっても何にもしてくれなくて、親父がずっと面倒診てくれたんだよ。本当のところは、どうして良いのかわからなくてオロオロしてただけなのかもしれないけど。 俺が小学校に上がる年の冬、親父は逝っちまった。幼かった俺は、まるで肋骨をベキベキとひきむしられるみたいに、とんでもなく悲しかった。悲しいのと同時に、恐怖だった。俺を生かしてくれる存在は、親父以外にあり得なかったからだ。 それから数年間、毎日鏡を見て過ごした。そうしないと、自分が消えちまってるような気がして、すごく不安になるからだ。学校にまで小さな手鏡を持っていった。 そのうち友達もできて、大きくなるにつれて心の痛みはやわらいだけど、親父の思い出だけは絶対に消えない。 お袋が捨ててしまった絵は、親父が一番喜んでくれたやつだった。 あの絵は親父の思い出を呼び起こすための鍵なんだ。かけがえのない、大切な思い出が、あの絵をきっかけにしてたくさんたくさん呼び覚まされてくるんだ。 しばらくして起きあがったものの、部屋の中を片付け直す気にもなれず、俺はパソコンの電源を入れた。マシンが「うーん」とうなり声を上げる。通信ソフトが起ち上がり、ネットメニューの一番目に登録されたBBS局が反転表示されている。そのままエンターキーを押す。 見慣れたトップメニューが現れて、それから会議室の未読を読みに……、いくはずなんだが、オートパイロットが止まってしまっている。スクリプトエラーか。いや、そうじゃない、何か致命的なハードエラーのように見える。ディスプレイの表示そのものがぼやけてしまっている。 俺は目を凝らしてディスプレイを見つめた。文字などどこにも現れてこない。ぼやけた画面は波打ち始め、そのうちマンデルブロのフラクタル画みたいな変化を始めた。 そして、段々と何かの形らしいものが浮かび上がってきたのだ。それは初め輪郭だけ、徐々に模様らしきものの線、という風に変化した。完全に画像として浮かび上がったときに俺は仰天した。封筒に入れてあった親父の似顔絵が浮かび上がっていたのだ。 画像データにして残した記憶なんかない。通信ソフトのやつ、いったいどこへアクセスしやがったんだ。 俺は、意味もなくおろおろと部屋の中を歩き回った。この絵を、いったいどうやって保存すりゃいいんだよ。 闇雲にキーボードをたたいてみても、何の反応もない。 あきらめて絵を眺めた。このパソコン、もう電源を切るわけにはいかない。観賞専用にする。 赤いクレヨンで横長に描かれた楕円の顔。ざくざくと刺さった髪は紫のクレヨン。緑で描かれた目は、右目だけ10円玉くらいの大きさで丁寧に塗られているのに、左目は毛糸の切れ端がぽたりと落ちたみたいにちっちゃく描かれている。口の黄色は、三日月が寝っころがった形で笑ってる。 ぼんやり絵を眺めていたら、涙が出てきた。すごく喜んでくれた親父の顔を思い出してしまったのだ。溢れる涙と一緒に絵もゆらゆらと動いた。まるで、しゃべっているみたいだ。少し笑えた。 ポケットからハンカチを出して涙を拭いた。絵が、まだ動いている。もう一回拭いた。でも、動いていた。絵は、本当にしゃべっていたのだ。何をしゃべっているのかとても気になり、30分くらいディスプレイを見つめた。 よおやく解読し終わり、理解した。あの絵は捨てられてなんかいない。お袋が去る時、セーターの下に隠し持っていたのだ。 涙と鼻水でグシャグシャになりながら、俺は笑わずにいられなかった。 お袋も、親父のことを死ぬほど愛してたんだ。そして不器用なりにもなんとか俺を育て上げてくれた。 お袋が、親父の思い出の品をわざわざ取り返しに来たのだと、わかった。 |
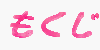
|
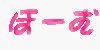
|