自作ノベルス
Copyright (C) by s-maru 2004
|
Kとレム 「都市は常に壊れている。壊れ続ける意志によって都市は都市として固定化される」 ブツブツと独り言を言いながら、コートの襟を立て、Kは高架道路脇のタイルの歩道を歩いていた。クスリが、彼をいざなう。 ――――夜明けなんか永遠に来なけりゃいい。夜と昼、男と女、どちらか一つにしてくれ、二つもあるなんて、むずかしすぎて俺にはわからない。―――― 時折、猛スピードでタクシーが走りすぎる。ヘッドライトの光に、Kは何度か目をくらまされて平衡感覚を失う。そのたびにふらつきながら、Kは歩いた。真っ暗な空を背景に、幽霊のような高層ビル群がゆらりと並んでいるのが見えた。 Kは、自分がなぜ絶望しているのか知らなかった。絶望していても悲しくないのはなぜなのか、知らなかった。悲しみの細胞が、きっと不足しているんだと思った。男は、女に比べると悲しみの細胞が8分の1しかないのだと、Kは教えられた。 Kはやっと、死ぬ決心がついた。 走り来るタクシーに跳ねてもらおうと考えた。運転手には申し訳ないが、今死ぬにはその方法しか思い浮かばないのだ。Kはふらふらと車道の方へ歩き出した。ちょうどまぶしいヘッドライトをきらめかせて、タクシーがやってきた。 まさか飛び出してくるとは思っていないだろう。それにこんな時間に走っているのは回送の車ばっかりだ。乗せる気なんてさらさらないさ、特に酔っぱらいみたいにふらついてる若い男など。きっとスピードをゆるめずに走り去ろうとするに違いない。 そんな風に考えながら、Kはタイミングをはかっていた。 数十メートルくらいの距離のところまでタクシーが迫ってきた。Kはアスファルトの車道へと踏み出した。次の瞬間には、Kはまるで水の中にでも飛び込んだかのように、アスファルトの海へすっぽりと落ち込んでしまった。 気がついた時、Kは畑の中にいた。クスリのせいで記憶が陥没してしまっていた。 見上げれば、ガラス越しに半分きりの月が見える。巨大な温室のようだ。Kの傍らには折れた木の枝が二本落ちていた。どこかから落ちたのは確かなようだ、そして枝に絡まったおかげで助かったのだ。 Kは枝を拾い上げてみた。妙に暖かく柔らかな感覚だ。そして、折れた断面からは何か樹液のようなものが…… 血だ。月明かりの中で目を凝らしてみると、Kが手に持っているのは人間の腕だった。 「ぐ……」 息が止まった。その腕は肘の間接あたりでぽっきりと折れてちぎれたものだった。何かを追い求めるように硬直した五本の指がついた手、そして血糊に染まった手首。Kはそれを握りしめたまま動けなくなった。しばらくして息苦しさのために正気に返り、そしてゆっくりとその腕を地面に置いた。 それからまわりの風景の異様さに気づいたのだ。Kのまわりに立ち並んでいる灌木の群は、どうも雰囲気が異様だ。Kは血まみれのコートを脱いで立ち上がった。どの樹も一様にKの身長と同じくらいの高さだった。ちょうど立ち上がった目の前には、枝の折れた樹があった。 よくよく見つめてみると、それは樹ではなく人間だった。人間が植えられているのだ。他の樹も、全部そうだった、どの樹もこの樹も全て人間だった。まるでマネキン人形の倉庫の中へ迷い込んだみたいだ。たくさんの、たくさんの人が、黙って動かずに立ち並んでいるのだ。 腕の折れた人の樹は老人だった。折れ口から血を流し、閉じた目からは涙を流していた。口元に耳を近づけてみると、低く押さえ込んだような泣き声が漏れ聞こえる。 「ああ、す、すまない、じいさん……」 Kは異様な雰囲気の中での恐怖よりも、腕を折ってしまったことへの申し訳なさのためにいたたまれなくなり、とりあえず折れた腕をつなげてみようと試みた。だがそれはつながりようもなく、血はどくどくと流れ続けている。 このままではこの人の樹が死んでしまう、なんとかしなければ。 Kは上着を脱ぎシャツの端をちぎって、肘の少し上のあたりを縛った。とりあえずこれで出血は防げるはずだ。 状況に慣れて落ち着いてきたKは、上着とコートを再び着込んで畑の中を歩いた。自分がどういうところへ迷い込んでしまったのかを把握しようとした。歩きながら見てみると、男もいる、女もいる。美しい者もそうでない者も。皆若い。さっきの老人以外には、年寄りは見あたらなかった。 Kはとにかく歩き回った。 どこかにこの畑のあるじの家があるはずだ。もしかすると国際的な犯罪グループによる実験施設なのかもしれない。人間をあんな風に改造して、それでいったい何をしようというのだろう。あんなにたくさんの人をどうやって集め、そして改造したのか。何者が、何の目的で。 Kは自分も見つかれば捕らえられて改造されるに違いないと思い、用心深く足音を忍ばせて歩いた。 畑の端までたどり着いたとき、建物が見えてきた。赤煉瓦の四角い家だった。家のまわりの生け垣はのばし放題になっているみたいで、家全体を包み込むように生えていた。家の向こう側は広い牧草地になっている。 Kは生け垣の陰に隠れた。そこから家の様子をうかがおうとして、生け垣をかき分けた。その時、その生け垣も異様な手触りであることに気づいた。細かいツタか茎のように見えるそれは、何かの動物の剛毛のようであった。Kはゴクリとつばを飲み込み、そして生け垣の付け根を見てみた。そこには、無数のネズミがうずくまって並んでいた。茎のように見えていたのは、ネズミの毛だった。まるでハリネズミのように、ネズミの毛は逆立って真上に伸び上がっていた。ネズミ達はまんじりともしない。まさかとは思ったが、やはり足は大地に根付いていた。 いったい誰が、こんなむごいことを…… Kはしばらくその場にうずくまって、言い様のない怒りと恐怖を制御できるようになるまで動かないでいた。 だがKの気配は家で飼われている犬に悟られてしまったようだ。激しく吠えたてながら、小さな犬がKの方へ走り込んできた。Kはとっさに走った。牧草地の方へ走り込み、脇のサイロへと逃げ込んだ。犬はサイロの中まで追いかけてきた。 Kはその辺のシャベルを手に持って犬を威嚇した。暗闇の中で、目だけが二つ光って見える。犬は激しく吠える。そのうち家人が気づいてやって来るかもしれない。そんなことになったら捕らえられてしまう。Kは思い切ってシャベルで犬を叩き殺した。一撃で、犬は「ギャン!」と叫んで果てた。だが手応えが異様だった。まるで何かぱさぱさしたものを叩きつぶしたような感触だった。わずかな光をたよりに犬の死骸を探し出して外に持って出た。月明かりに照らして見てみると、なんとそれは犬ではなくキャベツだった。 ――――間違えたのか? いやそんなはずは……、確かにさっき叩き伏せたのはこいつだったはずだ。それにどうしてサイロにキャベツなんか置いておかなくちゃいけないんだ?―――― Kは考えるのが面倒になって、キャベツをその辺にほっぽりだして人の樹畑へ戻ることにした。眠い、とにかく眠ろう。あそこなら誰にも不審に思われたりしない。木を隠すには森の中、人を隠すには人の中とは、よくいったものだ。Kはサイロの横の井戸で手を洗い、とぼとぼと畑へ向かった。 畑にたどり着き、隠れ場所を探した。どの人の樹も皆、独特なポーズを取っている。女の木はたいていクラシックバレェのつま先立ちのような格好をしているし、男の木はまるでブロンズ像のように立ちつくしている。Kは品定めでもするかのように一本一本、人の樹を見て回った。自分が混じっても違和感がないような隙間を探していたのである。 ところが、Kはある一本の人の樹に出会った時、視線がはずせなくなって立ち止まってしまった。そこには、美しい女の樹があった。Kはその樹の前に立って、彼女を見つめた。もしもこの世に“美”という粒子があるならば、きっと彼女のまわりに光のように発散している目に見えない何かがそれに違いない。 Kが気づかないうちに流れ星が十六回、月の横を走った。月も、Kを見守るのに飽きて西に傾いてしまった。それでもKは、罠にかかった虜のように立ちつくして、彼女を見つめていた。 荷物でも下げているみたいに足の付け根のあたりで両手を組み、太股を軽く浮かせている。きれいな足だ。その足指だけが長くのびて地面に没している以外は、何もかも普通の人間の女だ。お椀のような胸の膨らみとツンととがった乳首。小首を傾げてほほえむような口元、形の良い鼻、そして長いまつげの伏せられた目。さらさらの黒髪が肩にかかって背中へ流れている。 「もし、あなたは……」 おそるおそる声をかけてみた。 「わたし……? 私はレムと申します。そういうあなたは」 口を動かさないままで、彼女はしゃべった。それにしてもなんていい声だ。少しトーンの高い、そして甘い甘いささやき。 「お、俺、いや僕は、K、Kと呼んでください」 「けい? けいですか?」 「そう、Kです」 Kは、彼女の瞳を見たいと思った。もし彼女の瞳で見つめられたら、魔法にかかって木になってしまうかもしれないとも思った。でもどうしても彼女の瞳を見たかった。 「あなたは、目を閉ざしたまま、いつもそうしておいでですか?」 「め? めというと……」 「目をご存じない。もし…… 触れてもよろしいですか?」 「私の、めにですか?」 「そうです、あなたの目に」 「かまいません、触れてください」 Kはおそるおそる手をさしのべ、そして右手の中指の腹で彼女の左目に触れてみた。 「あ、そこは……」 驚いてKは手を離した。 「痛いのでしょうか?」 「いえ、そうではなくて……」 「そうではなくて?」 「はい、なにか今不思議な感触でした」 「どのように?」 「あなたは、柔らかい。そして暖かい」 「人は皆柔らかくて暖かいのですよ」 「本当ですか?」 「本当です」 「あなたは人なのですか?」 「そうです、人です」 「人は動いたり、ましてや他の人に触れたりできるものではありません。あなたはうそをついていらっしゃいますか?」 「いえ、うそをついてはおりません」 「もうすぐ夜が明けます。そうしたら、あなたが目と呼んだ私のこれが、開きます。するとあなたの姿形が私にもわかります」 「おお、夜が明ければ目が開くのですね」 「目が開く、そう、目が開きます。朝になれば」 朝が来るというのは、なんて素敵なことなのだろうとKは思った。もう眠ろうとは考えていなかった。夜明けまで、彼女を見つめて過ごしたい。夜が明けてからも、彼女と一緒に。そして彼女に触れたり話をしたりしながら。 Kは、自分の居場所を彼女の隣に決めた。 ちょうど彼女の隣には盛り土のされた場所が一つ空いていた。 「ここにいてもいいでしょうか」 「はい、ぜひ」 Kは、その場所で人の樹の振りをすることにして、まず服を脱ぎにかかった。服を脱ごうと考えた時に、Kは自分の体の一部の変化に気づいた。勃起していたのだ。 ――――なぜだ、決して彼女をそんな風に見ていたわけじゃないのに、どうして体は反応しているんだ。―――― Kは、勃起するのがなにも性欲をもよおした時ばかりとは限らないことを知らなかった。女性を好きになり、その気持ちが高まっている時には、体は自然に反応するものなのだ。 このまま服を脱いで彼女の前に立っていると、夜明には彼女に全てを見られることになってしまう。Kは迷った。 「おーい、お隣さんよ」 突然後ろから声がした。Kは驚いて振り向いた。 「だ、誰だ!」 「誰だはないだろう、オイラはずっと前からここにこうしているんだ。さっきから聞いてればあんた、人のくせに動き回ったりできるそうじゃないか、え?」 見ると、そこには屈強な体つきをした男が立っていた。太い眉毛に大きな鼻、頭髪は縮れ毛だ。 「人が、動き回るのは当たり前だ、動物なんだから」 Kは弱々しい口調で答えた。 「人が動物だと? 笑わせんな。人が動物なもんか。人は何万年も昔っから植物なんだぜ」 男の言葉に、Kはひどく混乱し始めた。 「人が植物だって? それじゃ、犬や猫もか?」 「いぬ? ねこ? なんだそりゃ」 「犬ってのは、あの家の庭で飼われているちっちゃくてよく吠えるやつだよ」 「ああ、あれはキャベツだ。吠えるだけじゃねぇ、噛みやがるぜ。人の足下でションベンたれたりするしな」 キャベツ……、やはりあれは犬ではなくてキャベツだったのだ。 「教えてくれ、いったいここはどこなんだ」 「ここはどこったって、ここはここじゃねぇか。おかしなことを訊くもんだ」 「それじゃ、あんたの名前は」 「オイラかい、オイラの名前はガラってんだ。おぼえときな」 「ガラ、ガラか、おぼえた。ガラ、俺はこれからしばらくここに住まわせてもらう。いろいろ教えて欲しいこともあるからよろしく頼む」 「がってんだい、なんでも訊きな」 話しているうちに勃起はおさまっていた。Kは急いで服を脱ぐと足下の土の中に丸めて埋めた。夜明けが近い。はやいとこカムフラージュしなければ。裸になると、Kは盛り土に足を埋めて立った。レムの姿を見ればまた勃起してしまうかもしれないと思い、横向きになった。 横を向いたものの、レムの姿がまぶたに焼き付いて離れない。そしてレムの姿を見つめていたくて見つめていたくてどうしても我慢ができない。Kは苦しんだ。レムを見たい。見たいけれども、勃起したら恥ずかしい。それに畑のあるじがもしもやってきて、一本だけ様子のおかしい樹を見つければ怪しむに違いない。そしたらおだぶつだ。 Kは必死で我慢した。そしてかたく目を閉ざした。だが夜明けになれば目を開けていなければならない。昼に目を閉じている人の樹などありはしないのだから。 空がだんだん薄紫色に染まり始めた。Kは少しだけ落ち着いてきた。慣れというのはこういう時には便利なものである。 Kは、ガラに勃起するのかどうか訊いてみようと思い、話しかけた。 「ガラ、おいガラ」 「おー、どうした」 「人の樹の男というのは、勃起するものなのか?」 「ぼっき? なんだそりゃ」 「つまり、ここだよほらここ、これが膨らんで立つんだ」 ガラはすでに半分ほど目を開いていた。Kが自分のペニスを手に持って示すと、ガラは納得したようにフムと一言うなづき、答えた。 「ああ、そこは立つよ」 「立つのか、やっぱり」 「そうさ、人参の奴が精液を回収しに来る時にな。なんだか機械をすっぽりかぶせられるんだ。下腹にちくりと何かが刺さると、そこはむくむくと立って、それから変に気持ち良くなって、そいで射精するんだ」 「射精するんだな」 「そうだ」 良かった、体の機能そのものは同じようにできているらしい。 「女の樹を見て勃起することはあるか?」 「ない」 「ない? なぜ」 「なぜ? なぜ女の樹を見て勃起するんだ?」 「それは……」 Kには答えられなかった。 男と女が愛し合うとは、いったいどういうことなんだろう…… ――――男と女、どちらか一つにしてくれ。二つもあるなんてむずかしすぎて俺にはわからない。―――― 無意識のうちにつぶやいていた。いつだったか、そんな言葉を聞いたような気がする。 何かが頭に引っかかる。何かを思い出しそうになった。しかし、そのことよりもさっきのガラの言葉が気にかかり、Kは再び訊ねてみた。 「ところで、さっき人参の奴って言ってなかったか?」 「言ったさ、人参の奴がここのあるじだ」 「人参が、あるじなのかい?」 「当たり前だろう、畑を作ったり木を植えたりなんて、人参でなけりゃできるもんか。ジャガイモやキュウリなんて下等動物にそんな芸当はできないさ」 「下等動物……、ジャガイモやキュウリが?」 「あんた、いちいちオイラの言うことに突っかかるな」 「いや、そういうわけじゃないんだ。ただ、俺は本当に何も知らないんだ」 「そうか、わかった。おっと、さっそく人参様のお出ましだぜ。いつも朝一番に畑の見回りに来るからな」 Kは心臓が高鳴った。人参が、いったいどういう人参が畑の管理などしているというのだろう。ひたすらドキドキしながらKは待った。 ――――ざし、ざし、ざし……―――― 足音が聞こえた。あれが人参の足音なのか。 ――――かさこそかさこそ、かさかさ、こそこそ……―――― 「おい、ガラ、あのかさかさ言ってるのは何だ?」 「人参の独り言さ」 「人参がしゃべるのか」 「当たり前だろう」 「俺達の声は奴には聞こえないのか?」 「さぁな、きっと『かさかさこそこそ』って聞こえてるんじゃないのか」 「なるほど」 そのうち、足音が近づいてきた。人参が、ついにKの前にやってきた。Kは目をきょろきょろさせないように気をつけながらさりげなく人参を観察した。別に何の変哲もない人参だった。長さは40センチくらいで、太さは直径10センチくらい。頭の上に葉っぱをたくわえ、赤い色をして、体の所々に細かい根が派生してついている、ありきたりな人参だった。 違うところといえば、しゃがんだり跳ねたり、運動しているというところぐらいのものか。冗談じゃない、どこがありきたりなんだ、飛んだり跳ねたりするけったいな人参なんて初めて見た。 人参は、Kの前で立ち止まり、そして不思議そうにKを眺め上げた。小さい割れ目の中に小さな目があるようだ。それから人参は、Kの足下にまでやってきて、何かごそごそし始めた。見ると、人参の葉っぱがにょきにょきとのびてきて、Kの体をまさぐり始めた。植えた覚えのない木を不審に思って調べ始めたのだ。人参の葉はKの体中をなめるようになで回した。くすぐったくて、Kは思わず体をよじりそうになったが、かろうじてこらえることができた。 ほんの数分で調査は済んだらしい。人参はそれだけで納得してKの足下から離れた。人参は、次にレムの足下に移動した。他の木は全て眺めて行くだけなのに、人参はレムだけは特別に思っているらしく、その葉っぱでレムをさすり始めた。まるで彫刻家が自分の気に入った作品を愛でるようにして、人参はレムを慈しみ、そして体のあちこちをさするのだ。肩、腕、首、そして乳房、おなかにお尻に、太股から足首まで。 レムはすでに開眼していた。緑色の瞳だった。Kはしばしうっとりとなってレムの瞳を見つめた。でもすぐにハッとなって自分の下半身を見た。今度は勃起していなかった。これも慣れというものなのだろうか。胸が締め付けられるようなときめきにも、少し慣れてきた。 人参は、今度はレムの姿勢を変え始めた。人の樹は、自分で動くことはできないが、外部から力を受ければそのように姿勢を変えることができるものらしい。ただ、大きな加重が急に加わると、急激には変化できずに折れてしまうのだ。 人参はゆっくりとていねいに、レムのポーズをいろいろ変えた。まるで壺に花を活けるようにして。 人参の葉がレムの足を開いて恥ずかしい部分をあらわにさせた。Kは一瞬だけ鼓動が激しく揺れるのを感じた。人参はレムの手足や首を同時にいろいろ変えながら考えている。レムは、まるで狂喜の中で踊り狂う一匹のメスのように、くねくねと踊らされていた。だが顔の表情だけは変化しない。目がうつろで悲しそうに見えた。 レムにとってはどうということもない単なる日常的な出来事であるのは理解できる。単にKの知覚認識においてそのように映るだけなのだ。だがKは狂おしかった。それと同時に言い様のない淫らな気持ちがわき起こり、勃起してしまった。Kはあせった。人参に見つかったら大変なことになってしまう。なぜこんな時に変な妄想を抱いてしまったのだろう。Kは雑念を払おうと目を閉じて気持ちを落ち着かせた。だが、ペニスは立ったまま萎えなかった。 こうなったら人参がこちらを見ないことを祈るしかない。そう思ってKは人参の様子をうかがった。人参は、レムをためつすがめつしながら眺めている。そして、レムの首がKの方へ向けられたとき、レムとKの目が合った。目が合った瞬間に、Kは気が遠くなるような衝撃を感じ、そして射精してしまった。レムの瞳のほんの隅っこに、わずかだが驚きの表情が走った。 Kは、穴があったら入りたいとつくづく思った。でも、射精したせいでペニスは萎え、人参がKの方を振り向いて見た時には元通りになっていた。 人参が去った後、レムはKに話しかけてきた。 「あなたは、私を見て射精なさいましたか?」 やさしく、心に直接ささやくようなレムの声が聞こえてきた。 「……」 Kは返答できなかった。 「お話になってはくださらないのですか?」 「いえ、そんなことは……、ただ、とても恥ずかしくて」 「はずかしい……、『はずかしい』というのはどんな感じなのでしょうか」 「恥ずかしいというのは、自分の格好悪いところを見られたくないということです」 「かっこう?」 「私は動くことができますので、いろいろな格好をします」 「姿形ということですか?」 「はい、それに動き方もそうです」 「動き方ですか」 「はい。動き方、何かをする時の見た目のことです」 「何かをする……、つまり動物達がいろいろなことをするのと同じことですね」 「そう、そして自分のしていること、したことが、他の人に見られたくないようなぶざまなものである時、格好悪いと言います」 「そうなのですか、あなたのぶざまなところを見てしまって、申し訳ありませんでした」 「いえ、あなたのせいでは……」 そう言いかけて、レムのせいに他ならないことをKは思い知った。目と目が合っただけで射精してしまうなんて、レム以外の何者のせいでもない。 「私のせいなのですね」 「そうかもしれない。でもあなたは悪くない、悪いのは僕だ」 「どうしてあなたが」 「あなたの姿を見て、淫らなことを考えてしまった」 「みだら?」 「もうよしましょう」 いつのまにか日は高く昇り、畑には太陽の光がふりそそいでいた。 昼の間、キャベツの死体を見つけた人参達は、大事なペットであるキャベツを、いったい何者が殺したのかと大騒ぎして探し回っていた。その様子が畑にまで伝わってきて、Kはなぜか小気味よかった。考えてみれば、図らずも完全犯罪を成就してしまったのだ。誰もKを疑ったりはしない。植物が歩き回ってペットを殺したなど、誰も考えつかないことだ。 Kは、少しずつ状況を把握し始めた。ここは自分が住んでいたのとは全く別の世界としか考えようがなく、要はそれを気持ちの上で受け入れることができるかどうかというだけのことである。Kは比較的環境に順応しやすいタイプで、何にでもすぐに慣れることができる。それは便利といえば便利だが、退屈しやすい性格でもあるということだ。 ここへ来る前、自分はいったい何をしていたのか、Kは考え続けた。そして、昨夜ガラと話していたときに引っかかった言葉を思い出した。 ――――夜と昼、男と女、どちらか一つにしてくれ。二つもあるなんてむずかしすぎて俺にはわからない。―――― どこかでそんな独白を聞いたような気がする。どこだったろう…… 考えているうちに夕方になった。もう人参達は皆家に帰って夕飯のしたくにかかっている。Kは土の中から足を抜いて、再び歩き出した。いずれはこの農場の外にも足を運んで、元の世界に戻るためのヒントを探さなければならない。 Kは、キャベツがその後どうなったか気になってサイロの方へ向かった。夕暮れの薄明かりの中、牧草地へ入る。裸足で草を踏むと、感触が異様だった。 牧草というのは虫だった。蠅のような小さな昆虫が地面から生えだしている。歩けばそれらがつぶれて中身が飛び出してくる。埋めておいた靴を掘り出して持ってくれば良かったと思った。たくさんの虫を踏みつぶしながらKは歩く。 昨夜のサイロの近くに、土の盛り上がった部分がある。おそらくキャベツが埋められてあるに違いない。そのうちキャベツは腐り、そしてそれを栄養にして虫が生えるというわけだ。Kはおぞましさに耐えながら井戸で手足を洗った。 それから、牧草の生えていないところを選び、遠回りして家の方へと走った。 明かりが灯っている窓から人参の家の中を覗いた。花瓶には、人の手足やリスのしっぽ、それから鳥の羽のような物が活けられていた。 「うぐ、ぐえぇ……」 苦い胃液が喉にまで上がってきて焼けつくような痛みをおぼえた。 部屋はダイニング・キッチンで、食事が始まるところだった。テーブルは一見黒檀のようでもあるが、よく見ると黒牛をそのままテーブルにしてあるみたいだ。きっと黒牛の木を加工した物なのだろう。 テーブルの正面で席について新聞を読んでいるのはここのあるじだ。奥の方のキッチンでまだ作業をしているのは女房なのだろう。少し細めで、フライパンをあやつる葉っぱもどこかやさしい感じがする。あるじの反対側の席には小さな人参が二人いた。四人家族なのだった。きっと幸せな家庭なんだろうなと思った。 テーブルには、いろいろな料理が白い磁器の皿に盛られて並んでいる。木材の角切りを焼いてたれをかけたらしいステーキ、ゆで玉子のような白くて丸い物、そして、あれはおそらくサラダなのだろう、何か得体の知れない生き物の体が、細切れにされて盛られていた。半透明なそれは、幼魚のようにも見える。 人参の女房が自分の分のステーキを焼き終わって皿に盛り、食卓に着いた。あるじが新聞をたたんでかたずけ、そして四人は葉っぱを複雑な形に組んで祈りを始めた。祈りが終わり、人参の家族はてんでに食べ物を物色し始めた。子供達はフォークとナイフで不器用に角材のステーキを切って口に運んでいる。 口というのは、葉っぱが生えている頭のてっぺんの中心だった。葉っぱの一つだけが頭の後ろに垂れ下がっていて、その付け根に口があるのだ。食べた物は後ろに垂れ下がった葉の茎の中へ、蛇が卵を呑む時のように順繰り送られていく。そしてだんだん膨らんでいくのだ。 あるじはステーキには手を着けず、サラダにフォークをのばした。サラダの材料というのが何なのかとても気にかかったので、Kはくまなく観察した。あるじがフォークですくって食べ始めた。そのかけらの一つを見て、Kは血の気が引くのをおぼえた。小さな小さな五本指の手が見えたのだ。 「あ、あれは……、胎児だ!」 思わず口をついて言葉が出た。 人参のあるじは、胎児の細切れをショキショキと咀嚼しては呑み込む。まるでフカヒレスープの具を噛むみたいに。Kは目の前がまっ茶色になった。そして理解した。 ここの畑は、胎児を生産するための施設なのだ。胎児を作って売っているのだ。そしてそれを市場へ出荷して、それから卸売業者が店頭へ卸し、人参の人妻が「あらおいしそう」とかなんとか言いながら買い物かごに入れて買って帰る。想像すると、背筋がゾクゾク寒くなった。 いくらKでも、こんなショックに簡単に慣れることはできそうにない。とにかく畑へ戻ることにした。知らないうちに涙が溢れていた。畑に戻ると、Kは何も考えずにレムの木の下でうずくまって寝た。レムのそばにいると、とても心が安らぐのだ。この安らぎにもきっと慣れることはなくて、レムとなら永遠に一緒にいられそうな気がした。かなうなら、レムを連れて元の世界に戻りたい。 「おかえりなさい」 「ただいま」 一言だけ言葉を交わして、Kは深い眠りに就いた。 ――――ざし、ざし……―――― 人参の足音で目覚めたKは、あわてて自分の場所に戻って足を土に埋め、ポーズを作った。人参は、もうKに不審を抱きはしなかった。その日はレムの姿勢を変更することもなく、人参はただ人の樹々を眺めながら通り過ぎていった。 それにしても腹が減った。何か食べる物はないのだろうか。食べ物はないか食べ物はないかとそればかり考えて辺りを見回せば、案外見つかるものだ。探さなければ見つからないのは当たり前だが。 Kは、そこかしこをちょこまかと走り回るジャガイモを見つけた。きっと、こっちの世界ではネズミみたいなものなのだろう。Kがそっと歩いて近寄ると、ジャガイモはきょとんとしていたが、そのうち突然慌てふためいて逃げた。だがKの手の方が速かった。ジャガイモをわしづかみにすると、力まかせにひねった。ジャガイモはまっぷたつに割れた。もし中に内蔵とかが入っていたらどうしようと少しだけ不安だったが、ジャガイモはやっぱりジャガイモだった。 皮には土が付いていて汚いので中身だけをむさぼり食べた。水分が多くてジューシーなジャガイモだった。 ちょうどガラの目の前でジャガイモを食べて見せたもんだから、ガラは微妙に顔の表情を曇らせた。動きはしないが表情は微妙に変化するのだ。Kはハッとなってレムの方を見た。ちょうどレムからは見えない位置に、Kはいた。考えてみれば人がジャガイモを捕まえて食べるなんて、この世界では非常におぞましいことだ。レムに見られなくて良かったと思った。そして、これからは気をつけようと。 何匹かジャガイモを食べて腹が膨れたKは、再び自分の場所に戻った。今の時期、人参は朝の見回り以外は畑にやってこないから気が楽ではあるが、いつ来るかわからない。一応備えはしておかなければならないのだ。 ポーズを取るほどのこともないと思い、体の力を抜いて楽な姿勢で立った。そして自分がここへ来る前に何をしていたのかを思い出そうと、考え始めた。 Kが考え込んでいると、Kのそばへ黄色い小さな花が飛んできた。茎の途中でぶち切れたみたいな花が、竹トンボのようにくるくる回転しながら飛んできたのだ。 「そいつは蜂だよ」 ガラが話しかけてきた。 「蜂? この花がか?」 「蜂だって言ってるだろう。いちいち突っかかるなぁ、あんたは」 「悪かった。で、この蜂は花も咲いてないのにどうして俺のところへやってきたんだろう」 「あんたの精液を採りに来たのさ」 「精液?」 「まぁ、見てな」 その花、いや蜂は、Kのペニスにとまった。それから、茎の先端を持ち上げてKの下腹をチクリとさした。 「いてて……」 だが、不思議なことに次の瞬間にはKのペニスは勃起し始めたのだ。そして瞬く間に射精してしまった。蜂は、茎の先からKの精液を吸い込んだ。茎の表面にも精液をたくさんつけたまま、レムの方へ飛んでいった。 「あ、なにを……」 蜂は、レムの性器にとまった。そしてさっきとは別の針を露出させて陰核を刺した。 「ああすると蜜が溢れてくるのさ。男の樹の精液と女の樹の蜜とを吸い込んでおいて、巣に運んで帰る。両方とも蜂の餌なんだ」 「えさだって!? でも、精液のついたしっぽをあそこへ入れたりしたら……」 「そうさ、そうやって人の樹は実をつけることができるんだ。何万年も昔から、人と蜂とは大事な大事なパートナーなんだよ。最近は人参の奴が蜂の体からホルモンだけを抽出して精液を回収するようになっちまったけどな。確実に実がなるように交配の日を調整してやがるのさ」 Kは、レムの性器から蜜が分泌され、透明な液体が内股を通ってすうっと流れるのを見て、何かとてもとても懐かしいものを見たような気がした。それは本当に蜜なのだろうか。レムの蜜はどんなに甘いだろう。いつかレムに頼んでなめさせてもらおうかと思ったが、そんな恥ずかしいこと絶対言えないと思った。 実というのは、もしかすると昨夜人参の食卓で目撃した胎児のことだろうか。 ガラに訊ねてみた。 「それで、実というのは?」 「実は実だよ。半透明な小さい実だけど、人の形はしている。交配してから三ヶ月くらいで女の樹から出てくる。 「三ヶ月? 十ヶ月の間違いじゃないのか?」 「だから、あんたはどうしてそういちいちオイラの話に突っかかるんだ。そんなに信用できないってんなら、もう何も教えてやらねぇ、自分で勝手に考えりゃいいんだ」 「ごめん、すまない、勘弁してくれ。いや、俺が住んでた世界じゃ人は動物で、人の男と女が結ばれて実ができると十ヶ月後に生まれるようになってるんだ。 それでそう思っただけなんだ」 「あんたが住んでた世界? なんだそりゃ」 「だから、こことは全く違う世界が、すごく近いのにとても遠い世界があるんだよ」 「まるでなぞなぞだな」 「そうだよ、謎だ」 その日の午後、人参が畑にやってきた。K達がいるところからかなり離れた場所で何か作業をしている。何をしているのかはわからないが、時たまチェーンソーのけたたましい音が聞こえてくる。間引きしているのだろうか。そうだとすれば、それもむごいことだ。そんな風に考えていると、あの音がひどく痛々しく聞こえる。胸がどんより重たくなった。ガラに訊いてみることにした。 「ガラ、あの音は何の音なんだろうね」 Kが訊くと、ガラは少しだけ考えてからおもむろに答えた。 「あれは、そうだな、きっと枯れた樹を取っぱらってんだろう」 「枯れた樹って、人の樹も枯れるのかい?」 「ああ、ときたまね」 ガラはどこかよその方角に注意を払いながら、Kの質問に答える。 「人の樹の寿命はどれくらいなんだ?」 「そうだな、二千年くらいだって聞いたけどな」 「この畑の人達はだいたい何歳ぐらい?」 「オイラは五十年ほど前にここに根付いた。他の奴らはだいたい二十年から二百年ってとこだけど、二千年以上生きてる老人も何人かいるらしい」 「レムは?」 「レムは八十年だな」 「じゃ、八十才なんだ」 「そういうこと」 「年取ると、やっぱり年寄りになるの?」 「千五百年くらいからしわが寄ってくるらしいぜ」 「ふうん」 「そういうあんたは?」 「俺は、まだ二十三才だよ」 「見た目よりだいぶ若いな」 「俺の世界では人の寿命は八十才くらいなんだ」 「そうなのか……」 相変わらず、別のことに注意を向けているような表情で、ガラはうなづいた。 チェーンソーの音がやんで、人参の足音が聞こえ始めた。 ――――ざし、ざし……―――― 「来たぜ」 「うん」 人参は二人がかりで何かをかついで歩いているようだ。少し向こう側にある通路を横切る時にそれが見えるはずだ。Kは通路の方をじっと見つめた。 ――――ざし、ざし……―――― 足音が近くなってきた。先を歩く人参が見えた。切り倒した人の樹の足の方をかついでいる。人参は二人で調子を合わせて、まるでボートのオールみたいな動き方をしながら進む。枯れ木の足は老人のものだった。人参がさらに進み、枯れ木の上半身が見えた。 その時、Kはのどの奥に真空を呑み込んだようなショックを受けた。枯れ木は両腕がもげていて、肘の上あたりが布でしばられている。 「あ、あれは……」 脂汗が額に浮いてきた。 「ありゃ長老だな。とうとう逝ったか。あんた知ってるのか?」 Kはガラになんて言って答えれば良いのかわからなかった。 「い、いや……」 きっと、出血多量で死んだのだ。 Kは歯を食いしばり、胸の痛みに耐えた。 「おい、どうしたんだ、何があったんだ、言えよ」 「ガラ……、俺はあの老人を殺したようなものなんだ」 「え?」 「俺がこの世界に降ってきた時、あの老人の腕の上に落ちて、それで腕がもげてしまった。そこから血が吹き出して、血が足りなくなって死んだに違いないんだ」 「っぷ……! あんたはつくづく何にも知らないんだな。腕なんてものはまた生えてくるんだよ。血もすぐに止まる。あの老人は寿命だったんだよ」 「本当に?」 「ああ、本当だとも」 涙がぽろぽろ流れ落ちた。 「ガラ、ありがとう」 「おい、動いちゃだめだ。人参は通り過ぎちゃいないぜ」 「あ……」 Kはそのまま硬直した。しばらくして、ガラが 「もう行った。大丈夫だ」 と言った。 「見られたかな」 「いや、人参の奴足下ばっかり見てたよ」 「そうか、良かった」 三度目の夜が来た。Kはレムの樹の下にうずくまっていた。その夜はなかなか寝つけなかった。Kは立ち上がり、レムに話しかけた。 「もし……、眠っているのですか?」 「いいえ、樹は冬の間しか眠らないのです。でもこの畑は温室だから、私達は一年中眠ることはありません」 「そうですか。ところで……」 「ところで?」 「はい、その……」 Kは、自分が何を言いたいのかが自分でもよくわからなかった。 「なんでしょう?」 レムが問う。 Kは、何も言わず衝動にまかせてレムの手を握った。暖かい、そして柔らかい。 「どうなさいました?」 少しだけ驚いたように、レムが言った。 「こうしていたいんだ」 Kが答えると、レムの表情がやわらいだ。微笑したようにも見えた。 「かまいませんよ」 そのままで、夜はどんどん深まっていった。手を握っていることに、Kはすぐに慣れてしまい、もっとたくさん触れたいと思った。でもなかなか言い出せずに時は過ぎた。 ほんの少し膨らみかけている月の目の前を、雲が急いで通り過ぎた。 Kはレムを抱きしめた。Kの胸にレムの乳房が押しつけられる。Kは背中に回した指に力を込めた。それから、少しだけ体を離してレムの顔を見た。レムの顔には、人参にポーズをあれこれいじられる時のような悲しげな影が降りていた。 「レム……」 「ケイ、ケイはなぜ私に触れたいのですか?」 「わからない。わからないけど、こうしていないとすごく苦しいんだ。こうしているととても気持ちいいんだ」 「気持ちいいのですね」 レムの表情が少しだけ明るくなった。 「レムは、いやかい?」 「ケイなら、いやではありません」 「さっき、悲しそうに見えた」 「ケイが、人参と同じなのかと思って、それで悲しいと思いました。でも同じではないとわかりました」 「同じじゃないって?」 「はい、触れれば伝わります」 「触れれば、伝わるんだね」 「はい」 その夜は、Kはレムを抱きしめて立ったまま眠った。 それから、Kは農場の外へ出歩くこともあきらめ、昼はじっと突っ立ってガラと話し、夜はレムと抱き合ったりささやきあったりしながら幾月か過ごした。Kはこの世界になじむに連れ、この世界の住人になりたいと考えるようになっていた。そう思って何日も足を土に埋めたまま動かないで過ごしたりもしたが、根が付くはずもなかった。 春が来て、畜舎につながれていた杉や松が牧草地に放され、のんびりと戯れ遊ぶ。杉も松もそれぞれの枝ぶりを誇示しあっては、角のような枝を絡ませて喧嘩する。キャベツが吠えたててそれをいさめる。それらの声が、温室にまで聞こえてくるのだ。Kは、その様子を想像して一人で楽しんだ。真夜中になると眠っている杉や松を見物しに牧草地まで行った。何もかもが新鮮な風景だ。もうおぞましさには慣れきってしまい、物珍しさの方が先に立ってしまう。 Kは、この世界での生活もまんざらじゃないと思い始めていた。 そのうち、レムが身ごもった。いつかの蜂がKの精液を運んだせいだった。そのことはもちろん人参も確認していた。そして出産の日がやってきた。 Kは、まだ形も整っていない胎児がどうやって根付き人の樹になるのか、とても興味を持った。自分とレムとの間にできた子供が、どんな風に根付いて大人になっていくのか、ずっと見守りたいと思った。だから人参が回収しに来る前に子供を畑の隅へ運んで隠しておこうと考えていた。うまく真夜中に生まれてくれと、Kは願った。 ちょうど満月の夜、レムが目を開いた。 「レム、レム?」 Kは不思議に思って話しかけた。 「はい?」 「レムの目が……」 「はい、もうじき実が熟して出てくるのだと思います」 レムが、少し苦しそうに答えた。 「初めてなのかい?」 「そう」 レムは、不安げにうなづいた。しばらく沈黙が続いた。Kは、レムが苦しんでいるのなら代わってやりたいと心から願ったが、それは無理なことだった。 「レム、実が生まれ落ちたら、どうやって根付くんだろうね」 「実は、体を丸めたままで一度土の中に潜ります。数日で根が伸びて、それから半年ほど土の中で育ちます。少し大きくなったら体を起こして苗木になり、15年くらいで大人の樹になります」 Kは目を輝かせてレムの話を聞いた。 「生命って、素晴らしいね」 Kの言葉に、レムが心なしか微笑んだように見えた。 そのうち、レムの様子が変化してきた。レムは汗をかき始めた。Kは、埋めてあった服を掘り出し、コートや上着にくるんでおいた綿の肌着を取り出してサイロの横の井戸できれいに洗って持って帰り、それでレムの額を拭いた。レムが少しでも楽になるように、姿勢を直した。それから、何かしてあげられることはないかと、レムのそばに寄り添っていた。 レムが呼吸を乱した。レムの息づかいを、Kは初めて感じた。普段のレムの呼吸はとてもゆっくりなので、Kはレムが呼吸していることさえ知らなかったのだ。Kの心の中に何かが生じた。レムが生身の女であることを、Kは強く意識した。 Kのそれまでのレムへの接し方は確かに人参とは違っていた。造形への慈しみではなく、生きた人間同士としての慈しみであった。それでも、今のKはそれ以上にレムの生身を感じていたのだ。レムの息づかい、レムの鼓動、血流、それらが全て自分の感覚であるかのように、Kには感じられた。 レムが、か細い声で何か言った。 「レム? なに? 何が欲しい?」 「水を、水を一口いただきたいのです」 「水だね」 そう言って井戸の方へ走ろうとした時、足音がやってきたのだ。 ――――ざし、ざし……―――― 人参の足音だ。どうしてこんな真夜中に。 Kはあわてて服を片づけ、自分の場所に立った。まもなく人参がやってきた。人参は水の入った桶と杓を持っていた。そして、レムに水を与え始めたのだ。レムはほんの少量ずつ、それをふくんで飲んだ。しばらく間をおいて、また人参がレムに水を与える。レムが飲み干す。そんなことを繰り返して桶の水が空になった頃、レムの内股を水が流れ落ち始めた。するする、としたたり落ちる水。人参はそれを見つめていたが、頃合をはかってレムの足の間に桶をおいた。 その数秒後に、すとんと胎児が落ちてきたのだ。胎盤らしきものは見あたらないが、へその緒の先に動物の毛のようなだいだい色の物がついていた。その毛のような部分だけがもぞもぞとうごめき、ちょうど土を探すように桶の底をまさぐった。それは、むなしく桶の底を這い回る。だがどこにも土はないのだ。 人参は、そのまま去ろうとした。だがKはそれを黙って見ていられなかった。 「うがー!」 雄叫びを上げながらKは人参に襲いかかった。人参は振り返ってKを見た。 人参は桶を手放して2メートルくらい飛び上がり、落下して地べたに這いつくばり腰を抜かした。Kは桶を拾って走った。畑の隅まで走り、盛り土のされた場所、Kが初めてこの世界に降り立った場所、老人の枯れ木が切り取られて空いたその場所に胎児を置いた。 へそにつながる毛のような器官が土を見つけてさっそく潜り込み始めた。数分で胎児は土の中へ入り込んだ。Kはそれを見守り、そして安堵のため息をついた。 人参が倒れていた場所へ戻ってみると、そこには杓が一本残されているばかりで人参の姿はなかった。Kは、まもなく追っ手がやってくるだろうと思った。 「レム……、さようなら、レム」 「ケイ、どうして」 「僕とレムとの、初めての子供なんだ。人参なんかに食べられてたまるか」 レムがその言葉の持つ意味を理解したのかどうかはわからないが、とにかく納得して 「ケイ、わかりました。気をつけて」 と言った。 温室から抜け出して表に出た時、そこにはすでに何十もの人参が身構えて立っていた。てんでに鍬や鉈などの武器を持っている。Kは、足の速さなら奴らに負けないと思った。そして隊列の隙をついて囲みから脱出することに成功した。このまま逃げて逃げて逃げおおせてやる。そしていつか、レムと子供を連れて元の世界に戻るんだ。必ずその方法を見つけだしてやる。それが無理でも、どこか遠くの山奥へレム達を移してそこで静かに暮らしたい。そう考えながら全力で走った。 しかし、それもつかの間のことだった。どこかから「フッ」という音が聞こえたと思うと、次の瞬間には足に何かがプツリと刺さった。 「いてて……」 Kは足をむだからせて転んだ。すぐに起きあがろうとしたが、すでに平衡感覚がなかった。麻酔銃を撃たれたのだ。意識が朦朧とする中、それでもKは起きあがって走ろうとした。だが体はいうことをきかなかった。意識が遠のいた。 何かの光が迫ってくるのが見えた。そしてそれは通り過ぎ、また別の光が迫ってくる。 ――――夜明けなんか永遠に来なけりゃいい。昼と夜、男と女、どちらか一つにしてくれ、二つもあるなんて、むずかしすぎて俺にはわからない。―――― 誰かがつぶやいているのが聞こえる。何を言っているのかよくわからない。 Kは、目覚めた。薄暗い部屋の中にいた。コンクリートの天井が見える。顔を横に向けると、鉄の檻が見えた。 だが、檻の外をよおく観察してみると、監獄という感じではなかった。まず、部屋の真ん中には大きな台がある。手術台のようにも見える。あれはどう考えても解剖用の台だ。脇のテーブルの上にはビーカーやフラスコなどの実験器具がたくさん並んでいるし、壁の戸棚には分厚い本がたくさん並んでいる。別の棚には瓶詰めにされた得体の知れない生き物が透明な液体に漬けられて保存されている。研究室のように見える。 Kは、一瞬自分が液体に漬けられて瓶詰めにされている様子を想像した。あまり考えたくはないことだが、それはKのごく近い将来の姿として、きわめて可能性の高いものだった。 Kは、明日には解剖されるのだと思った。そして、覚悟を決めて檻の中で仰向けに寝そべった。 ――――解剖って、まず麻酔か何かで体の自由を奪われ、それからメスで腹を裂かれるのかな。それから鉗子で腹をあけられて、はさみで腸を切られて、じょきじょきじょき……―――― じょきじょき、そこまで考えた時に突然頭の一部が痛み出した。ちょうど首の後ろから目の裏側にかけての部分で、小さな小さな時限爆弾が炸裂したように、一気に痛み出したのだ。Kは「う!」と、うなって頭を抱え込んだ。 痛い痛い痛い、とにかく痛い、激しく痛い。後頭部から釘でも打ち込まれたみたいだ。Kは両手で頭を抱えたままコンクリートの床の上を転げ回った。 もがき苦しむKの脳裏に、いやな情景が映し出された。産科医の診察台の上で足を固定された女が医師に犯されている情景だった。すごくいやなイメージだ。そんなものを見た記憶など全くない。なのにイメージはますます鮮明になっていく。女性器の入り口でペニスが行きつ戻りつする様がよく見えた。音まで聞こえる。そして女の泣き声と、涙と鼻水でべたべたになった顔。 ひとしきり、激しい頭痛とそのイメージに悩まされ、次にはその女性が中絶手術を受ける情景が見えてきた。はさみで、医師がじょきじょきじょきと、女の腹の中の何かを切っている。 ――――あのニセ医者め!―――― Kは心の中で毒づいた。そして、なぜそれがニセ医者であることを自分が知っているのか疑問に思った。 痛みに耐えながら考えた。考えていると、痛みが増幅されてますます苦しくなる。 「ぐ、ぎゃー!」 大声を張り上げると、頭がしびれて一時的に痛みを感じなくなるが、ほんの数秒だ。大声を出し続けるような体力も残っていない。なにより、痛みに耐えるだけでもものすごく体力を消耗するのだ。全身の筋肉に力が入る。どこの力を抜くこともできない。床の中央でさそりのように反り返って、Kはうめき声を上げていた。 次に現れたイメージは、その女をボロアパートで看病する自分自身の姿だった。いくら医者へ行こうと言っても女は聞かない。そのうち熱が下がるからと言ってかたくなに拒むのだ。無理矢理連れて行こうとしても泣き叫んで抵抗する。ボロアパートの一室で、Kは途方に暮れていた。 ――――倫子……、そうだ、あの女は倫子だ。俺の恋人だった……―――― 突然、記憶が戻り始めた。 ――――倫子は、倫子は、あのまま逝ったんだ。ニセ医者に犯されたことを俺に知られるのを恐れて、息を引き取る間際にごめんなさいと言って、倫子は……―――― あの晩、Kは倫子が息を引き取ってから抜け殻のようになって町へさまよい出た。いつのまにかその産科医の自宅の前に来ていた。Kの無意識が復讐を決意していたのかもしれなかった。 だが、その産科医の自宅前にはパトカーが何台もとまっていて、見物人が大勢詰めかけ、テレビ局や新聞屋などでごったがえしていた。Kが訪れた時、ちょうどニセ医者が連行されるところだった。見物人の話から、その男がニセ医者であることや、こっそり中絶にくる若い独身女性を診察台の上で犯していたことなどを知った。 ちょうどクリスマスイブだった。町中がにぎわう中、Kは薬局で買った鎮痛剤を十粒ほど飲み、それから安酒場で安酒をあおり、朦朧となったまま町を徘徊していたのだ。そして人っ気のない高架道路に出た。 抑圧されていた記憶がすっかりよみがえると頭痛からは解放されたが、今度はそれ以上に苦しい心の痛みがKを襲った。 「う、う、う、うがー! ぎゃーー!」 Kはもがき苦しみながら叫んだ。 部屋の扉の外で複数の足音が響きわたり、扉の前で止まった。ガチャガチャと錠が解かれ、白衣の若い医師が一人と看護婦が二人入ってきた。体格の良い中年の看護婦がKを後ろからはがいじめにして、それよりも少し年長の看護婦が、Kの顎をつかむようにして頬に指を食い込ませながら、慣れた手つきでKの口の中にハルシオンを放り込み、そして水を含ませて鼻をつまんだ。Kはゴックンと錠剤を呑み込んだ。思考が停止して苦しみが消える。 半ば放心状態となって、口を開けたままボーっとしてベッドの上に座り込んでいるKの横に、華奢な腰をもたれかけて医師が話しかけた。 「私がわかりますか?」 整った顔にさらさらの前髪がかかり、医師は右手でそれをかき上げた。しばらく医師の顔を眺めてから、Kは 「はい」 と答えた。 「誰?」 「お医者さんでしょう。それも、神経科だ」 「うむ」 看護婦が小躍りして喜んだ。初めて会話が成立したのだ。それまでの三ヶ月間、Kはかさかさこそこそと独り言を言い続けていたのだ。 医師が続けざまに質問した。 「あなたは、どうしてそんなに苦しんでいるのですか?」 Kの眉間がぴくりと動いた。年長の看護婦がポケットに手を突っ込む。そこにはハルシオンが入っている。いつでも対応できる体勢で、看護婦が医師とKとのやりとりを見守る。 Kは、無表情のまま話し出した。 「恋人が……、恋人がニセ医者に犯されて殺されたんです」 言い終わると同時にKはポロポロと涙を落とし、それから低く声を押さえて泣き始めた。 看護婦達がもらい泣きして、嗚咽を漏らした。記憶と言葉とを失って入院したKを看病しているうちに、深く同情していたのだ。その事情を初めて聞き、いたたまれなくなったのだろう。 医師は大きなため息を一つつき、それから看護婦に目配せして病室を出た。看護婦達はもらい泣きしながらも、Kの背中をさすったり手を握ったりしてなだめる。 「なんて言って慰めて上げればいいんでしょうねぇ……」 体格の良い方がそう言うと、 「ここでゆっくり静養してくださいね」 年長の方が後をつなぐ。 一時間ぐらいそうしていた。Kはうんうんとうなづきながら泣いた。そのうち看護婦達も病室から出ていった。Kは一晩中泣き明かした。 次の日、連絡を受けたタクシー運転手が見舞いに来た。Kが飛び出した時、ほんの少し接触して軽傷を負っていたのだ。タクシー運転手はKが言葉を取り戻したことを心から喜んだ。自分の保身のためではなく、心底Kの身の上を心配していた。人の好いおじさんだった。 午後からは刑事が二人やってきた。倫子の亡骸は、死亡した明くる日に倫子の両親が発見したそうだ。死因は出血多量だった。子宮の中に胎盤の一部が残されたままだったらしい。刑事は、倫子が件のニセ医者の手によって中絶手術を受けたことを証明する人間がKしかいないことを告げ、一日も早く証言台に立てるようになって欲しいと言い残して去った。 夕方、昨夜の体格の良い看護婦が点滴の瓶を持ってやってきた。白い天井を見つめて身動きしないKに、 「柏木さん、点滴ですよ」 と言う。 「K、俺は、Kだよ」 Kはそう言った。 「違いますよ、あなたの名前は柏木真一。Kというのは部屋の番号ですよ。扉の真ん中にKって書いてあるんです。ここに連れてこられた時にきっと印象に残ったんでしょうねぇ」 「そうなのか……」 「思い出しましたか?」 「うん、そうだ、俺の名前は柏木真一だ。間違いない」 「良かった」 看護婦はKの布団の足下を少しだけまくり上げた。 「すみません、一瞬だけ痛いけど我慢してね」 看護婦はKの足の甲の静脈に点滴の針を入れた。腕の静脈の方はもうかたくなってしまって、うまく針が入らないのだ。絆創膏で針をとめ、チューブの途中の器具を片手できゅきゅきゅっとさばいて点滴の落ちる速さを調節し、看護婦は一人で納得した。 Kは看護婦に訊ねてみた。 「俺、ここに来てどのくらいになるの?」 「かれこれ三ヶ月になりますよ」 「そんなに……」 Kは自分の知らないうちに流れていった時に思いを馳せて、少しだけ驚いていた。 もう、桜が咲く頃じゃないか。 看護婦が出ていくと、Kはまた一人になった。一人になると心の痛みが爆発しそうな気がした。だが、すでにそれをこらえるすべをKは身につけていた。 蛇が脱皮するようにして、苦しんでいる自分自身を脱ぎ捨ててしまえばいいのだ。それで苦しみが少し減る。また苦しくなったら同じように脱皮する。そうやって何度も生まれ変わっているうちに壊れた心は復元されていくのだ。 二時間後、看護婦が点滴の針を抜きに来た。瓶を回収して去った。それから、Kは少しだけまどろんだ。まどろみから覚醒したとき、病室内に誰かがいることに気づいた。気づいても、Kはそちらを見なかった。見なければいるのかどうか確かめられないのだが、でも見えなくても確かにいることがわかる。 「誰?」 Kは小さく言葉を発した。 「ケイ」 聞き覚えのある声だった。Kはその声に結びつくイメージを記憶の中で検索した。数秒でヒットした。 「レム!」 振り向いて見ると、そこにはレムが立っていた。足指に根はついていない、こちらの世界の普通の女になっていた。 「レム、レムなんだね」 「ケイ、会いたかった」 レムは歩いてKのベッドに近づいてきた。 「レム、歩いている」 レムは黙って微笑した。人の樹の精となってKの前に姿を現したのだった。 レムはKのベッドの中に潜り込んだ。暖かい、そしてやわらかい。懐かしい感覚だ。 「また会えるとは思ってもみなかった」 緑色の瞳を輝かせながら、レムはうなづいた。二人は体をぴったりとくっつけて抱き合った。Kの腕の中に頭を埋めて、レムは 「あなたと、ずっと一緒にいたい」 と言った。少しして、 「レム、僕はね」 Kがささやきかける。レムはKの瞳を見つめ、続きを待った。 「僕は、ずっとずっと、何億年も前に」 「ずっとずっと、何億年も前に?」 「そう、何億年も前に、あなただったような気がするんだ」 「ケイが、私だったこと?」 「そう、僕は、あなただったことがある」 そのうち二人の姿は光のかたまりのようになり、徐々に融合した。やがて、一つの大きな光になった。 「ケイ、帰りましょう」 「うん」 光は消えた。 次の朝、看護婦が少量の流動食を持ってKの病室にやってきた。入院してから初めての食事だった。三ヶ月も胃腸が機能をとめていたため、うまく食べることはできないのだが、すこしずつ馴らしていかなければならない。看護婦は、どんな風にKに食事をすすめようかとあれこれ思案していた。 「柏木さん、朝ですよ、起きてください」 一番良い笑顔を作って、明るく言う。返事がない。看護婦は、余裕の笑みを浮かべながら、もう一度大きな声で言った。 「柏木さん」 食事を乗せた盆を床頭台に乗せて、Kの耳元でもう一度名前を呼ぼうとして、様子がおかしいことに気づいた。 「柏木さん、柏木さん?」 肉体的にはどこも悪いところがないのだから、異常事態など全く想定していなかった。看護婦は、あわてて布団をまくり上げ、Kの頸動脈に右手の人差し指と中指を当てた。脈がない。体温はまだ残っている。あるいは蘇生可能かもしれない。看護婦はインターフォンのボタンを押した。 「はいぃ、どうしました?」 「ちょ、せん、先生を呼んでください。あ、外科の先生も。K室の柏木さん、ステルベンです。原因は全くわかりません。早く呼んでください」 「わかりました」 スピーカーからドタバタという音が漏れて出る。そしてインターフォンはブチっと切れる。 看護婦はまずKの首の下に手を入れて背中に枕をかまし、口から息を吹き込んだ。胸が膨らむのを確認してから、そのまま腹の上に馬乗りになって、心臓の位置を確かめ、まず右の手のひらの付け根を、それからその上に左手を重ね、心臓マッサージを始めた。 「1・2・3・4・5・6……」 そして息を吹き込む。 数分後、医師が二人駆けつけた。少し遅れて数人の看護婦が大きな器具を引っ張ってやってきた。看護婦達が心電計を装着し、医師はKの喉のあたりを切開して管を差し込む。 外科医師が、Kの上で心臓マッサージしている看護婦に向かって言う。 「代わろう」 「はい」 だが、誰がやっても同じだった。Kの心臓はぴくりとも反応しなかった。 約五時間にわたって蘇生術が試みられた。だがKは生き返らなかった。外科医師が、看護婦達と神経科医師とに向かって、 「残念ですが……」 と言って小さく頭を下げ、病室を去った。看護婦達はすすり泣き始めた。神経科医師が指示を出して、器具が片づけられた。そして、全員が一旦病室から出た。 数時間後、若い看護婦が二人、Kの体を清拭しに来た。 「この患者さん、なんだか幸せそうな顔してるね」 細い腕でKの寝巻の帯を解きながら、背の高い看護婦が言った。 「うん、まるで寿命をまっとうして満足っていう顔だね」 横で洗面器の消毒液の中にタオルを浸しながら、もう一人が答える。背は高くないが豊かな胸をしている。 「そうだね」 袖を抜いてKの体をあちらこちらと転がしながら、長身の方が相づちを打つ。下着が外され、Kは裸になった。まだ体は硬直していなかった。 「この人、家族はいないのかしら」 「ここに入院してからは誰も来てないみたいよ。最初に運ばれた救急病院の方は知らないけど、誰も見に来てないんじゃないの?」 「天涯孤独だったのかもね」 「そうだね」 「可哀想に……」 「うん」 一人が手足を押さえ、もう一人が体を拭き、作業は速やかに行われる。清拭が終わると、ストレッチャーが運び込まれ、裸のままでKの亡骸は霊安室に運ばれた。台に乗せられ、両手を腹の上で組み、白い布をかぶせられる。霊安室では線香が焚かれ、背広姿の僧侶がやってきて簡単な経を上げて行った。 |
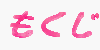
|
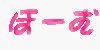
|