自作ノベルス
Copyright (C) by s-maru 2004
|
蛹{さなぎ} 隣町のT市へ買い物に出た帰りだった。国道から県道に降りて、海岸に出る少し手前の廃工場で、夕暮れだというのに、村の子供達がたむろしているのが見えた。早く帰るように注意しようと車を乗り入れる。 買ってきたランニングシューズを車の中に置きっぱなしにするのがなんだか不安で、それを持って出た。いや、新しいシューズがうれしくてそばを離れるのがいやだったのだ。 子供達は、大きな古い火鉢を囲んで、灰の中の何かをいじっていた。 「おい、もう帰らんと、母ちゃんが心配すっぞ」 子供達は、そわそわし始めてお互いに何か言い合っていたが、糞にたかる蠅が逃げるようにして、突然火鉢のそばを離れ、かたわらで輪を作った。輪の中をのぞき込んでみると、そこには大きな幼虫がいて、蛹になろうとしていた。その幼虫の頭が、どう見ても猫だった。耳はなく、大きなイモムシみたいだ。でも、顔はまさしく猫なのだった。 猫って、蛹から生まれるんだったっけ。 よく考えたら猫が生まれるところなんて見たことがないのだ。猫って、本当はこうやって生まれるのかもしれないと思った。 まるで悪い物を食べて嘔吐するように顔をしかめながら、猫の幼虫達は口から粘液を吐き出している。この粘液を体中にまとい、そのまま固まって蛹になるのだろう。横手の石垣にシューズを置いて、僕は猫の幼虫達を観察していた。子供達もじっと観察していた。 そのうち、あたりは段々暗くなってきた。半袖を着ていたので肌寒さをおぼえ、急いで家に帰った。子供達もそのうち帰るだろう。 次の日、村のマラソン大会に出場するための用意をしていて、廃工場にシューズを忘れてきたことを思い出した。 日曜の朝だというのに村中があわただしい。もうすぐ10時だ。受付が始まる。 村の真ん中を通る県道は人でわき返っている。自動車の出入りは普段から少ないのだが、車両通行制限のために渋滞ができている。 そんな中を車でかいくぐって、廃工場へ向かった。シューズをさがす前に、幼虫達がどうしているのか気になって、様子を見てみた。ところが、蛹はどこにもない。抜け殻も見あたらない。 昨日、子供達が取り巻いていた火鉢の中をのぞいてみたら、ビニールテープでグルグル巻きにされた蛹が灰の中に押し込まれていた。火鉢には火が残っている。蛹は蒸し焼きにされていたのだ。 思わず顔をしかめた。なんというひどいことを。子供というのは、こんなむごいことを平気でやってしまうものなのだろうか。胸が痛くならないのだろうか。 かすかに、鳴き声が聞こえた。まだ生きているかもしれない。灰をほじくって蛹を全部取り出し、一つ一つ丁寧にテープをむいてやった。蛹は全部で7つ。鰹節みたいになってしまっている。そのうちの3つだけが、かすかに鳴き声を発していた。 心の中で「頑張れ、まだ間に合う」と強く念じながら、瞳に力を込めて見つめた。 果たして、3匹の猫が同時に殻を割って生まれてきた。体中の毛は粘液でヌルヌルしていて、まるで鯨の胃袋から出てきた魚みたいに、半分溶けかかっていた。手のひらに乗せて見てみたら、結構元気そうだ。3匹の子猫は、自力で川の縁までたどり着き、水を飲み、産湯を使っていた。誰が教えたわけでもないのに、生まれたときからちゃんと知っているのだ。 ホッと安堵の息をつく。途端にマラソン大会のことを思い出した。早くシューズを持って帰って受付しなければ。 石垣のあたりをさがしてみる。確かこの辺に置いたはずなんだがと独り言をもらしながら見て歩いてたら、一角が土砂崩れで破壊されていた。ちょうど、昨日ランニングシューズを置いた場所だった。 しばし愕然としていたが、もう一度買ってくるしかない。ジョギングスタイルのまま、車でT市へ向かった。 T市に着いて、ショッピングモールに入った頃にはスタートの時間を過ぎていた。少しぐらい遅れても、頑張れば追いつけるだろう。とにかく新しいシューズだ。新しいランニングシューズでなければ飛ぶように走ることはできない。新素材が使われた特別なシューズなのだ。 モールのスポーツ品売場のレジで女房が働いている。値札さえ置いてくればそのまま払っておいてくれるだろう。とにかく今は1分1秒が惜しいのだ。 エスカレータを駆け上がろうとしたら、乗り場に浮浪者が座っていて、コンビニの弁当を食べていた。エスカレータの裏側の、陰になったスペースが彼の家なのだった。浮浪権があるために排除できないのだ。まったく、困った法律ができたものだ。だがこれだけ失業者が多いと、そうでもしなければどうしようもないのかもしれない。 走って勢いをつけながら頭の上を飛び越えてエスカレータを駆け上がった。 3階の洋品売場を抜ければスポーツ用品売場なのだが、狭い通路に中学生らしき男の子達がたむろしている。そこは防犯カメラの盲点になっているところだ。女房から聞いた話では、中年の男性がここで暴行を受けて財布を奪われる事件が多発しているらしい。被害者は中学生にやられたことをものすごく不名誉なことだと思ってどこにも通報しないので、モールでもなんの対応もしていない。事件のことを知っているのは従業員だけなのだ。 中学生達は、とても日本語だとは思えないようなスラングで話していて、時折奇声を発して大声で笑っている。 とてもそこを通り過ぎる気にはならなくて、遠回りすることにした。 売場に近づき、レジに目をやると女房と目があった。思わず顔がゆるんでしまう。結婚3年目で、まだ恋人同士のような気分なのだ。 レジへ近づこうとしたとき、何者かが僕の肘をつかんだ。とても強い力で、不意をつかれたために全く抵抗できなかった。不良学生かもしれない。背筋が寒くなった。 女房は、プイとそっぽを向いてしまった。いったいどうしたんだ。人を呼んで助けてくれないのか。 階段の近くまで引っ張り回された末に、やっと相手と向き合って顔を見た。 「みな子……!」 5年前に別れた恋人だった。すでに結婚してT市に住んでいるはずだ。今まで一度も出くわしたことはない。なんでまたこんな時に。 「久しぶりねぇ」 みな子は瞳をうるませながら僕の顔をじっと見ている。 「今、急いでるんだ」 「あら、私は急いでなんかいないけど?」 「僕は急いでいる」 「あわてなくてもいいじゃない」 そのままみな子の強力な力でグイグイと引っ張られ、外に出てしまった。街中で争うわけにもいかない。他人から見れば男の方が悪く見えるに決まっている。逆らうこともできず寄り添って歩くしかなかった。 みな子に誘導されて着いた場所は、ラブホテルだった。そのまま抗えずに部屋に入ってしまった。 拒否しようとする僕を無理矢理ベッドに横たわらせ、勝手にズボンのファスナーを下げて、みな子はペニスをなめ始めた。 よせ、困る、やめろ。 でも、みな子はものすごくうまい。 ボタンを押すと液体を発射する機械のように、みな子にツボを刺激されると射精してしまいそうになる。僕のボタンを、彼女は知り尽くしている。そして、発射の直前で機械を停止させてしまうことにも慣れている。 我慢ができなくなって、みな子の体を押し倒し、乱暴に下着を取り去った。すでに、あふれていた。白いミニのワンピースがたくし上がって、煙みたいな毛と、黒い花びらと、桜色の真珠が見えた。 我慢できなくなって挿入してしまった。 懐かしい感触だった。狭苦しくて、でも何かの生き物がいっぱいのたくっているみたいで。 僕が体を動かすたびに、みな子の顔はゆがむ。とんでもない罪を犯して悔いるかのように、口を不安げに開けたり噛みしめたり。 お椀みたいな柔らかい乳房が、ほにょほにょと揺れている。 そのまま僕は、みな子の中で3回射精した。 情事を終えて、グッタリとなったみな子をそのままほったらかし、外に出て車まで戻り、村に帰った。もうシューズなんてどうでもいい。早くレースに参加しなければ。 先頭の人はとっくにゴールしているはずなのに、今から全速力で頑張れば追いついて抜けそうな気がするのだ。間に合うかもしれない。きっと間に合う。どんなに出遅れたって、頑張りさえすればきっと一番になれる。そんな気がして仕方がない。 車窓から、最後尾のグループが見えた。すでに折り返し地点を過ぎていて、みんな苦しそうに走ったり歩いたり。それにつれて昨日の子供達が大人達の間を駆け抜けてはしゃいでいる。またそれにつれて、小猫達がはしゃいで走り回る。すっかり元気だ。 小猫達がおもちゃにして戯れているものを見たとき少しだけ驚いた。それは自分達と一緒に火鉢に入れられて、助からなかった蛹達であった。 僕は、女房への言い訳を考えながら、そのまま家路についた。 |
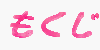
|
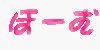
|