自作ノベルス
Copyright (C) by s-maru 2001
|
鏡 愛してるなんて、本当に愛している間は言わない。それを言うのは、言い訳の時だけだ。男なんて、そんなもんさ。 朝っぱらから、寝ぼけたお前を抱くけど、ちっとも濡れなくて、オレは動きが取れない。結局挿入しただけだった。そのうちお前は目を覚まし、一人で目覚めて一人で起きたみたいにベッドから降り、朝風呂を浴びる。 取り残されたオレは、冷蔵庫まで行ってビールを取って来る。ベッドの横にある小さなテーブルで不機嫌にビールを飲んでいると、お前はてんで気にもかけずに、頭にバスタオルを巻き、白い乳房をさらけ出したまま寝室に戻ってくる。赤白ストライプの小さなパンツをつけて、細い腰から親指を突っ込み、ゴムをピシャリとはじいて馴染ませている。 三面鏡の前に座る。後ろ姿。お前のおしりって、こんなに丸っこかったっけ。 タオルを取ると、まるでカーリーヘアみたいにクルクルしている髪も、お前がブラシでなでつけながらドライヤーをあてれば、芸術的と言っていいほど美しい流れに変わる。スッと伸びて、毛先がシャギーに決まる。 お前はまず、眉毛にハサミを入れる。ブラシでそろえながら。それから、打楽器のスティックみたいに先端が玉子型になった筆を這わせる。 ビューランを当てるときにも、お前はまばたき人形みたいに片目だけをキチンとつむることができる。空いた方の目はまん丸だ。鏡の中にも大きな目がいて、三方からお前を見ている。 オレがタバコに火を付けたとき、お前は振り返った。今日初めて、オレを真っ直ぐに見た。大きな瞳は、髪にニオイをつけないでと語っている。お前の鼻の下の産毛がぴくりと動く。呼吸の音が一瞬だけ聞こえる。 少し乱暴に、グラスに2杯目のビールをそそぐ。泡があふれ出す。かまわずにあおる。のび放題の無精ひげがびしょびしょになった。シャツの袖で拭った。 お前は、あきらめたように目を細めて鏡に向き直る。 元々色白で肌のきめの細かいお前は、何もつけなくても十分美しい。 スーパーファインセラミックスのファンデーションが、本当に薄くのせられていく。まるで化粧をするフリだけしているみたいに。 二重まぶたの折り目に、少し濃いめのピンクのラインを引く。それから、太い筆でラメ入りの薄いピンクのシャドウをすべらせる。目と目の間、鼻筋のくぼみにベージュ色の粉をほんの少し、中くらいの筆でなでつける。 お前の筆遣いは、まるで居合いの達人みたいに敏速で正確だ。 頬紅をつけて、最後にリップをひく。劇的に真っ赤な口紅。唇を内側に折り込んでからまた開く。きれいについた。 「なぁ」 呼びかけるが、返事はない。 「なぁって」 「なんやねんな」 何をそんなに怒ってる。学校をズル休みしたことか? 「どこか出かけんのか?」 オレがそう訊くと、お前はブラウスのボタンをとめながら、身体はこっちを向くが顔は鏡の方を向いたまま、 「彼氏が迎えに来んねん」 と言った。 「そうか」 真っ白なウールのスーツ。そいつを着て、二人で八坂神社にお参りしたんじゃないか。 「愛してる……、って言ったら、イヤか?」 鏡で背中を見ていたお前は、ふと動きを止める。ゆっくりオレの方を向く。 「あんた」 急に太い声。 「彼女大事にしたらなあかんで」 「あんなもん、彼女違うわい」 「めったなこと言うもんやないで」 「もう、一年も会うてない」 「でも手紙来てるやん」 「それだけや。たまに電話かかってきても、ずっと黙り込んでるだけや。最初っからそんな調子やったんや。こっちかて、ええかげんイヤになるわい」 「でも続いてるがな。あんたのこと、ホンマに好きなんやで」 「好きなら、抱きたいゆうたら抱かしてくれるもんとちゃうんかい」 「あんたはなんにもわかってない」 バッグを手に取り、お前はドアの方を向きながら、 「ほな、いくで」 と言った。 行ってもええんやな、とめへんのやな、お前の目がそう語っているようにも見えた。そんなのオレの思いこみだ。でも、夜帰る頃には、オレが部屋からいなくなってるかもしれないことを、お前は怖れてるんだ。 お前が去った一人の部屋で、オレは三面鏡の前に座った。3人のオレがオレを見ていた。 オレは、お前になんにも与えてやれやしない。奪うだけの愛だ。そんなの耐えきれない。お前に何かを与える男になりたいんだよ、なぁ、母さん。 |
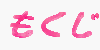
|
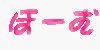
|