自作ノベルス
Copyright (C) by s-maru 2001
|
ヒレトバシカメウオ ――――また降ってきやがった ヒレトバシカメウオはひとりつぶやいた。 梅雨が去った後の海底は、海面に溜まった冷たい雨水が少しずつ降りてきては、潮水と溶け合い切れずに攪乱されてユラユラとにじむ。ちょうど真水の中へ水飴を溶かし込んだときのような、そんな揺らぎが降りてきて海底の視界はとても曖昧になる。海藻類の半透明な茶色や頼りなげな紫、岩肌のモノクロームなど、模糊としてそれぞれの境界を失うのだ。 雨水と潮水との攪乱は、かすかな音を海底に満遍無く響き渡らせる。 ヒレトバシカメウオは、雨が嫌いだった。この音も嫌いだった。雨水は側線を直接刺激して弱く刺すような痛みを彼にもたらす。海上では晴天でも、海底では攪乱がおさまるまでずっと雨降りなのだ。 この時期、ヒレトバシカメウオは決まって棲みかにもぐり込む。彼の棲みかは沈んで逆さまになった大型クルーザーのデッキの下だった。 上向きになった船底にはオレンジ色の海綿がビッシリとはびこり、ところどころポツンと空いた口から細い絹糸のような触手を伸ばしているが、魚が近寄ると蛇の舌のような俊敏さで触手は引き込まれ、そして口はピッタリとふさがれる。 船尾は砂に埋まり、ちょうど船首の半楕円の部分にグルっとめぐらされているステンレスパイプの長いてすりのせいで、一種監獄の様を呈しているが、雨宿りのためには最適な棲みかなのだ。 ちょっと見では鮫のような、どちらかと言えばコチという魚を巨大化させたような、茶褐色の背中に白い斑点のある、ひらべったく長い体を砂の上にうずくまらせて、ヒレトバシカメウオは何日もそこでジッとしていなければならなかった。空腹に耐え切れなくなったときだけ、餌をさがしに雨の中を出かける。 ――――なぁおい、おまえさんはいつからそうやってぶら下がってんだ? 彼はときどき同居人に話しかける。頭上の影を、カレイのように上へ突き出した目でことさら睨み、話しかけてからしばらく待つ。同居人から返事が返ってきたことはない。同居人は物静かでおとなしい。 ヒレトバシカメウオは孤独だった。ヒレトバシカメウオという魚は群をなさないのだが、彼の孤独はそのせいばかりではなかった。他のヒレトバシカメウオ達に比べて、彼の体は十倍近い大きさがあり、とてもつき合うどころではないのだ。 彼がステンレスパイプの檻から外の様子をうかがっていると、雨水のせいで体力を失ってフラフラになったスズメダイが二〜三尾、群からはぐれて近寄ってきた。曖昧な視界の中、スズメダイ特有のピンクに光る尾の一点が、ヒラヒラする泳ぎでチカチカと明滅しているように見える。 ヒレトバシカメウオは緊張した。アコーディオンを広げるように立派な胸ビレを広げて、鰭条のとがった骨をそちらの方へ向けて慎重に狙いを定める。彼の体内でポンプの鼓動のようなものが刻まれ、そしてヒレの付け根に圧縮空気が蓄積された。 ステンレスパイプから一メートルほどのところまで二尾のスズメダイがやってきたとき、ブブ! っという音とともに彼のヒレの先の毒針が三本発射された。鰭条の骨はパイプ状になっていて、先端の針を吹き矢のように飛ばすことができるのだ。およそ五センチほどの長さの針がほぼ直線的に、煙を巻くような軌跡を描いて飛ぶ。 スズメダイは二尾とも、突然何かに打たれたようにピクンと跳ね、次の瞬間には細かいふるえを起こして灰色の砂の上に横たわり痙攣しはじめた。針は貫通して、はるか彼方へ飛んでいってしまっていたが、毒はすぐにまわるのだ。 ヒレトバシカメウオは素早く檻から抜け出して近付くと、二尾の獲物を一呑みにしてしまった。針は二〜三日ですぐに再生される。 ● 「ほんなら、行ってくるでぇ」 「気ぃつけてね、あんた」 「おお、明日の昼過ぎには帰ってくるで」 午後の強い日差しの下、玄関先で亭主が女房に見送られて出かける。亭主の名前は村越一郎、子供の頃から海とともに生き、そして他の仕事のことなど考えたこともないという生まれついての漁師だ。女房の夏江とは幼馴染みで、二人とも村より外の地域で暮らしたことがない。一郎の両親はすでに他界していたので、一人息子と三人の生活だった。 暑いのに長袖のなっぱ服に長靴履いて、小脇に紺色の分厚い合羽ズボンを抱え、弁当をぶら下げて一郎は波止場へ向かった。道すがら近所の婆さん達に声をかけて歩く。昼間、家のまわりでうろうろしているのは決まって婆さん達である。若い娘は隣町へ働きに行っているし、若嫁さん達は家の中で亭主と一緒にいる。中年のオバちゃん達は山へ畑をしに行っている。 婆さん達は、家の男どもが漁から帰りしなに持ち帰った魚で干物を作ってみたり、魚のはらわたを溜めておいて堆肥を作ってみたりと、いろいろとすることはある。畑に行きたいのだが、嫁に譲ってしまったのでもう行けないのである。 婆さん達はいずれも絣にもんぺ姿で、白髪だらけの髪を後ろにひっつめて鼈甲の櫛でとめ、その上から手拭いをかぶってうなじのあたりで結んで日差しをしのいでいる。 「暑うなったのお」 歩きながら出会う婆さん一人一人に、一郎は同じように話しかける。婆さん達も皆同じように 「おいね、ほんにあついわいねー」 と答える。それから 「こんなに早おから出るんかい、一郎さん」 と聞き返してくる。 「ああ、沖で機械が故障したなんてことにでもなったら恥じゃさかいの。人より先に出て機械を見とかにゃぁ」 「えらいのー、一郎さんはぁ」 一郎は、どの婆さんとも年中顔を合わせるたんびに同じやり取りで、少々面倒くさいとは思うのだが、年寄りというのはそういうもんだと思い、もう慣れてしまった。 村は入り組んだ半島の一角にあり、海に面しているところ以外は険しい山林に囲まれている。近年になって、この山林にアスファルト道が通ったおかげで自動車で他の町と行き来できるようになった。それまでは交通機関というと船だけだったのだ。 少しだけ下り坂の踏み固められた赤土の小道を、潮風で漂白されたような家々を縫って一〜二分歩くと波止場の入口にさしかかる。ちょうど粗壁がむき出しになった蔵がある。蔵は、屋根の近くだけが白壁に塗られていて、上の方に小さな明かり取りの窓があいている。窓には古びた鉄の格子がはめ込まれているが、格子は欄間のような細工になっており、蔵の中に映る影は船と荒波の絵になるのを一郎は幼い頃に見たことがある。 その蔵までは日陰を歩いて来れたのだが、波止場にさしかかるともう日差しをさえぎるものはない。細かい砂でざらつくコンクリの道に足を踏み入れた途端、突然視界が開けて海が広がり、強烈な紫外線が脳天を貫くように降り注いだ。 船の係留場に人影はなかった。ジリジリと照りつける日差しで荷揚げ場のコンクリは焼け、海猫達も真っ青な海上に白く点々と浮かんで羽を休めている。入り江を両側から包み込む手のような、巨大な岸壁の岬をコンクリで固めた防波堤は、ところどころ元の岩肌をのぞかせていた。 村の男達は全員が漁師で、十五軒ある家々全てが株主になって運営されている任意組合経営の巻網船に乗っている。そしてそれが村で唯一の職場でもあった。乗組員数は二二人、父子で乗っている者もいる。 大工も左官屋も畳屋も水道屋も電気屋もいない。漁師以外の職業の人達は全て、需要があれば隣町から出張してくる。 一郎は係留場へ向かうと、船に乗り込んだ。一郎が機関士を勤める網船は、長さが約二〇メートル、幅六メートルほどのべったりした形の船だ。デッキの高さも喫水から一メートルほどと低い。 船尾に積んだままの網にしみこんだ潮が乾いてツンと鼻をつくような臭いが夏の熱風とともにまとわりついてくる。 他の乗組員よりも二時間ばかり早く出てきての始業点検だ。船は三バイあるが、他の二ハイの船の機関士はまだ出てきていない。一郎はいつも、自分の受け持つ船が一番調子がよくてピカピカで、沖でも故障などのトラブルを起こさないことを誇りに思っていた。 灼けたデッキの下の機関場はほとんどサウナのようなもので、もぐり込んだ途端に汗がどっと吹き出した。 まずボロキレにオイルを含ませてエンジンの表面を磨く。ついでに機関場の床も乾いたボロで拭いておく。板場にしみこんだオイルやカーボンでボロキレは黒く汚れる。それからオイル点検とラジエーター水の点検。船底にビルジが溜っていればシャフトのスタンチューブを少ししめておく。 エンジンの始業点検が済むと今度は油圧機械の点検だ。機関場から這い出してデッキに上がり、操舵室に入る。暖機のためにエンジンを始動させる。轟音が波止場のコンクリートで反響して辺り一面を支配する。大型のディーゼルの音は、カリカリいわない。どちらかといえば大型のガソリンエンジンの音をもっと低くしたようなうなり方をする。配電盤のスイッチを操作して油圧の電着クラッチをオンにすると、エンジンに負荷がかかって少し回転が落ちる。そこら中の油圧配管がぶーんとうなる。デッキまわりを点検しながら油圧機械の点検だ。 全ての機器が正常に作動することを確かめ、油圧の電着クラッチをオフにする。ある程度エンジンが暖まってくれば、今度はパネルの計器を見て異常な値を示す部分がないか確かめる。 あとは舵取りのラットを回してみて手ごたえをみる。こちらも一種の油圧機械なので、油もれなどのトラブルがないか確かめておく。 エンジンをかけたままにしておいて、一郎はオイルやカーボンで汚れた上に水をぶっかぶったみたいに汗でグショグショになった体のまま、上屋根の下まで歩き、そこで本当に水道の水をかぶった。かぶりながらガブガブ飲んだ。 そうしているうちに本船の機関士がやってきた。 「今日もいきなり行水かい」 「ああ、気持ちええぞ」 「おめーはホントにマジメなやっちゃなぁ」 「おっちゃんも昔は同じことやっとったんやろが」 「あ〜、今はもう機械屋まかせになってしもたがな」 「年はとりとおないの」 「アホぬかせ、給金に見合わんことするのがあほらしゅうなっただけじゃい」 「そうか、ワシは金が安かろうが高かろうが、自分が人に恥ずかしない仕事さえすれば満足じゃがの」 「おーおー、そう思とるんも今のうちじゃ」 苦笑いしながらそう言うと、彼は本船のエンジンを始動しに係留場へ向かった。 一パイだけでもやかましいエンジン音が二つになる。波止場はたちまち慌ただしさを増した。本船は巨大な電灯を装備している。テストのためにスイッチが入れられる。初めオレンジ色の小さな光が遠慮がちに灯るが、それは見る見るうちに青白くなる。青い光の矢が放射状に広がり、一面に突き刺さる。夏の日差しを凌駕してしまうほどの光量が波止場を支配する。一郎は船に背中を向けてズダ袋からタオルを取り出して頭を拭いた。服はそのうち勝手に乾いてしまうだろう。それからタバコも取り出して一服した。 すぐにあと一人も現れて一郎に声をかけてから運搬船に向かう。 三バイの船のエンジン音は村中に響き渡り、乗組員達はそれに急かされてしぶしぶと波止場へ集まってくる。 午後五時頃には出航だ。 ● 夕飯の支度をしながら、夏江は近所の子供達がおもてではしゃぐ声を聞いていた。息子の孝一の声が混じっていない。ほんの少し心配ではあったがいつものことだ。夏の日は長く、七時すぎまで明るい。それに孝一はもう三年生だ、心配するほどのこともないだろう。 一郎達の乗った船が出航するけたたましいエンジン音は家まで聴こえてきてあわただしい。一日おきの一人寝にはもう慣れてしまっているが、それでもこのけたたましいエンジン音は夏江の胸にジリジリした淋しさを湧き起こさせる。 一郎のセックスは精力のかたまりのように強い。体格はそれほどでもないが、力もあるしなんといってもスタミナが並み大抵ではない。家で寝る日は必ず夜を徹して求められるのだ。 そんな一郎の強さに引けを取らず、夏江もまた強かった。子供の頃から日焼けしながら育った肌は健康的な小麦色で、全身はバネのようなしなやかさを持ち、獣のような激しさで一郎のせめに応える。一晩のうちに十数回も達して、クタクタになるまで一郎につき合うのだ。 昨夜の記憶が夏江の胸を苦しくさせた。やさしさもムードもなにもない、気のきいたセリフの一つもなしに、むさ苦しい畳の上の潮くさいセンベイ布団の上で、二頭の獣がまぐわった。 下腹の皮膚を破って一郎のペニスが顔を出すのではないかと思われるほど突きまくられた。今でもそこが熱い。今夜もきっと体が火照ってなかなか寝つけないだろう。 ● 夏江がまだ家で少年の帰りを待ちながら家事にいそしんでいた頃、少年は海岸より少しだけ沖合いにある叩き台の上で、小さい蟹やイソギンチャクなどを観察しながら遊んでいた。 この叩き台は巨大な平べったい岩で、常に表面を波が洗うので、ブロッコリのような形の弾力のある短い海藻が表面をビッシリとおおい、小さなくぼみの中にかわいらしい海の生き物達がたくさんいて子供の遊び場になっている。赤や黄色、紫に緑と極彩色の、ちょうど人口芝のような表面の海藻は、足の裏にとても心地よい。 ときたま岩の割れ目の中に亀の手がついている。亀の手はその名のとおり、まるで岩石の内部に閉じ込められた亀が五千年ぶりに開いた割れ目から抜け出そうとして、やっと出口に手をかけたところで岩戸が閉じてしまい、指先だけが彼の存在を知らしめているというようなそんな風情の生き物だ。 叩き台へ磯から行くときには大人なら背が届くくらいの浅瀬を泳いで行ける。しかし、その沖側は断崖絶壁のように切り立っていて、叩き台の向こうは十数メートルの深い海になっていてとても危険だ。 浮き輪さえあれば低学年の子供でもめったなことはないのだが、少年は観察に夢中になって、足元に置いておいた浮き輪が流されていることに気がつかなかった。 沖を通る船の音に気付いて、少年は立ち上がった。父の乗る船が小さく見える。傾きかけた日の下で薄青く見渡せる半島の先を目指して船は行く。 少年はたくましい父が大好きだった。家にいるときにはいつも一緒に遊んでもらう。強くて優しい父を世界中に自慢してやりたいといつも思っていた。 船影が見えなくなるまで少年は沖をながめていた。それから母の顔を思い浮かべて家が恋しくなりはじめ、そろそろ帰ろうと思い立った。 足元の、岩肌が少しだけ突出した部分にかけておいた浮き輪を拾おうとして、はじめて浮き輪が流されていることに気がついた。 少年は急に不安になり、回りをキョロキョロとさがした。浮き輪を見つけ出すという目的だけが少年の意識を支配してしまい、少年は沖側と磯側を見分ける判断力を失ってしまった。 すぐに浮き輪は見つかったのだが、すでに断崖よりも沖の方へ流されていたのだ。 沖へ流された浮き輪を追う少年は、西日でキラキラ光る海面に目がくらんで叩き台の終端が見えなかった。気がついたときには金槌のように海底へと落ちていくばかりなのだった。 ● 夏江は六時近くになっても姿を見せない孝一のことが段々心配になりはじめていた。孝一の遊び連れの子供達を呼び止めて孝一のことを尋ねるのだが、誰の返事も要領を得ない。浜で遊んでいたことは皆が言っているので間違いなさそうだが、遊び場と言ったら浜か山しかないのだからそんなことはわかりきったことなのだ。 夏江は胸騒ぎをおぼえて海岸へと向かった。 夏の日が長いとはいえ、五時すぎにはたいていの子供達が海から上がってその辺で遊んでいるのが普通だ。 もう三年生だからと、一人で海へ遊びにやらせたのが間違いだったのだろうか。いや、たまたま遊びすぎてまだ泳いでいるに違いない、胸騒ぎは単なる錯覚だ。夏江はいろんなことを考えながら海岸へと向かっていたが、いつのまにか走り出していた。 夏江が海岸にたどり着いたとき、あたりにはもう人影はなく、夕方に吹き込むそよ風が、後ろで束ねた夏江の髪一本一本を丁寧に選別するようにして通りすぎるばかりだった。 夏江は孝一が叩き台の向こう側へ落ちたのだと直観的に悟った。 思わず知らず叩き台まで泳いで行き、沖側の深い海へと身を投じて孝一が沈んでいないか潜ってさがしたのだが、そんなに深くは潜れない。 数メートルの深さのあたりをうろうろするばかりで、海底はモヤモヤしていて全然見えないのだ。 亭主を含め村の男達は皆、さっき沖へ出たばかりだ。明日の昼過ぎまで戻らない。沖が休みの日にはアワビ取りなどもやっている亭主なら、このぐらいの深さは楽に潜って息子をさがしてくれるだろうに。 夢中で潜っているうちに激しく疲れて叩き台の上に半身をあずけたまま、夏江は情けなくなって泣いた。 呼吸が落ち着いてから、近所に誰か潜れる人はいないかと考えたが、村に残っているのは女子供とヨボヨボの年寄りだけだった。 もしかしたらどこかの浜辺に流されて途方にくれているのかもしれない。夏江は辺りの海岸という海岸全てをさがして歩き回った。だがどこにも人影はない。そのうちすっかりあたりは夜闇に包まれてしまった。 夏江はすぐ近所にある実家の母に相談しようと村へ戻った。 夏江の母は孝一が浜でいなくなったことを聞いて青くなり、さっそく近所中の女達全員に頼み込んで海岸を捜索してもらった。もしかしたら夏江のしらないうちに服を着て山へ行ったのかもしれないと、誰かが山の方へもさがしに行ってくれた。 十数名で明け方まで捜索したが、孝一はついに見つからなかった。皆には気の毒なので帰ってもらい、夏江も半ばあきらめて家に戻った。 夏江は泣く泣く亭主の帰りを待った。 ● ヒレトバシカメウオは、空腹に耐えかねていた。日が落ちて暗くなる前にあと一食取っておきたかった。 ――――おまえさんは、はらがすかなくていいよなぁ…… 同居人に話しかける。返事はない。しばらく同居人をながめてからヒレトバシカメウオは狩りに出かけた。 棲みかを出ると、雨水が側線にしみる。 ――――う〜、ブルブル。雨降りってのはこれだからいやんなるぜ ヒレトバシカメウオは獲物をさがして結構遠くにまで出かけた。自分が出かけている間にとんでもないお客が舞い込んでくるなど、彼には知る由もなかった。 ヒレトバシカメウオにはいくつかの狩場があった。そのひとつで、少し沖合いに巨大な岩石の並び立つ墓場のような場所がある。その巨岩の中でも狛犬のような形の岩が、彼の好物であるスズメダイのたまり場なのだ。 昼間でもほの暗い沖合では、夕方近くにはかなり暗くなっている。これくらいの深さになると、もう海藻はほとんど生えていない。砂地の上に突き出ている巨岩は、ちょうど草木が生えない高山のような岩肌をさらしている。部分的に赤く変色しているのは、珊瑚の一種が生息していた跡だ。どころどころに牡蠣貝がはびこっている。 暗い中で、ピンク色の小さな光が無数に明滅しているのが見えた。スズメダイだ。尻尾の光は点滅するわけではないが、泳ぐ向きによって見え隠れするので明滅して見えるのだ。その光を見ていると、普通の魚なら幻惑されるか本能を利用されて危険と勘違いしてしまうかのどちらかだ。 毒針を使うのももったいないので、彼はスズメダイの群の中に突っ込んで手あたり次第に食べた。スズメダイもそう簡単にはつかまらない、必死で散らばって逃げた。逃げる際にはどういうわけか必ず最後尾の一〜二尾が逃げ遅れて群とは別方向へ向かう。群をなす生き物というのは群が危機に瀕したときには必ず一〜二の者が群を助けるために進んで犠牲になるのだ。 だが群をなす魚の習性で、一旦散らばってもまた必ず一つにまとまってその場でグルグルし始める。かたまることによって大きな生き物のように振舞い、敵を威嚇しようとするのだが、通用しない相手だっているのだ。しかしスズメダイは考えてそういう行動を取っているわけではない。全ては遺伝子に記録された通りの動きなのである。 腹一杯食べてからヒレトバシカメウオは棲みかに戻った。あたりはもう暗くなり始めていた。棲みかに訪れた客のことも、そして同居人がそれを招き入れていたことも、ヒレトバシカメウオは全く知らないまま、砂に体を半分うずめて眠りにかかった。 ● 一郎は快調なエンジン音に心をはずませながらラットを握っていた。日は傾き、少しだけ赤く染まっている。今夜も良い凪ぎだ。夏は仕事がやりやすくて助かる。 計器の冷却水温度は正常値を示している、全く調子いい。歌でも歌いたい気分だ。おまけに今年はいつになくハマチが大漁で、景気もいいのだ。 先頭を漁労長の乗り込んだ本船が走り、一郎が舵を握る網船がその後に、さらにその後に運搬船が続く。先頭の本船は網船の数倍の大きさで、重厚な造りの舶用十トンクレーンを装備し、船室の屋根ではレーダーのアンテナがゆっくり回っている。船室内には、魚群探知機や、衛星から送られてくる情報を受信するための機器類がところせましと並べられているのを一郎は見たことがある。一般の乗組員が本船の船室に入ることはまずないので、それらの機器類を見たことがある者は限られているのだ。 三バイの船は、深く入り組んだ半島沿いに外海を目指す。 エンジンの調子が良すぎて一郎の船は先頭の船に追い付いてしまいそうになるので、一郎は少しだけエンジンの回転を落した。 針路を修正するとき以外は、船が直進するように時々ラットをいじるだけなので、運転中はそれほど忙しくない。一郎はちょっとだけ昨夜の回想をして、夏江のしなやかな肢体のことを思い浮かべては思わずニヤけてしまうということを繰り返した。股間の一物がムクムクと膨張してはおさまり、また膨張しておさまる。 そのうち夜の闇が海原に降りてくる。陸の家々では夕食を終えてテレビのバラエティ番組を見はじめる頃だ。考えごとなどしていると、時々海苔の養殖イカダを引っかけそうになったり浮標にぶち当たりそうになる。そのたびに気を取り直すのだが、そのうちまた回想が始まってしまう。 そうこうしている間に三バイの船は外海に達する。ここから先はどこへ進むのかわからない。先頭を行く船はレーダーを見ながら針路を決めている。その後にしたがってついていくだけだ。 三十分ほど走ってから、先頭の船が速度を落した。一郎は途端に緊張する。本船の電灯がともされる。透明でレモンのような形の巨大な電球の中心では、はじめは小さな灯がともり、見る見るうちに巨大な光源となっていく。あたりの海原は真昼のように明るくなってしまった。 エンジンの回転を落して船を止め、指示を待つ。ときどきスローで船の向きを整えながら待っていると合図があった。網船は速度を少しだけ上げて網を落しながら本船を取り巻くように走る。うまく魚群をとらえているだろうか。魚に散られたらまたやり直しだ。だが失敗してやり直したことなど、一郎が船に乗ってからの十四年間ただの一度もなかった。もっともこれだけの強力な光を発していれば、よそにいる魚でも寄ってきてしまうのだが。 一郎は中学を出てすぐに船に乗った。最初の頃はつらかった。元々体は大きくない方なので、まだ未成熟な体には労働が過酷だった。デッキの上でおっちゃん達に叱られながら必死で這いずり回った。当時は大型電球もなく、夜目がきかなくてまっぽうくらやみながら無我夢中で仕事していたのだ。機械化が進んで船も大型化し、以前に比べると仕事もずいぶん楽になった。 魚群を囲むように投じられた網をしぼり込むと、本船は網の外へ抜ける。それから網を巻き上げる。一郎は船体中央にある特大のキャッチホーラーの操作をまかされていた。網の巻き方ひとつにもコツがあって、この機械を操れる者は少ないのだ。 順調に網を巻き上げていると、誰かが船尾の方で大声を出した。 「おい! 良太が落ちたぞ!」 一郎は青くなって船尾の方を振り向いた。 良太というのは今年中学を出て船に乗った男の子だ。慣れない船上の作業で最初はオタオタしていたが、すぐに仕事に慣れてなかなか見どころのあるやつだと思っていた。ところがこいつは要領が悪くてお調子者なので、たまに危険な目に遭うのだ。 今日は船からこぼれて暗闇の海へ落ちてしまったという。 一郎は機械を止めて船尾の方へ駆け寄った。 良太の姿はどこにも見えない。外海は潮流も速いしうねりも強い、下手をするともう遠くへ流されてしまっている可能性もある。あたら若い命を海に散らしてなるものか、一郎は声を限りに良太の名を呼んだ。返事がない。 一郎は船の回りを一周してあたりを見回した。やはり人影は見えなかった。乗組員全員が良太の影をさがした。相方の船も作業を止めて全員が海上を見ている。誰もが「見つけた」という一声を待っていた。 一郎はハタと思うところあって船首へ向かった。船首のブルワークから体を乗りだしてせり上がった舳先の下をのぞき見た。良太はいた。 「お、おーーーい! いたぞ、いたぞー」 全員が船首へ詰め寄った。 良太は水を飲みながら船体の一部を必死でつかんでしがみついていた。とても声を出せるような状態ではなかったのだ。 一郎はロープを持って飛び込み、良太を抱え込んだ。その場の数人がロープを引き上げ、めでたく一郎と良太は引き上げられた。 「こ、この、バカモン!」 一郎は良太を叱った。良太は弱ってしまってその場に寝転がったまま返事しなかった。 良太の父親は沖の事故で命を落してしまって、良太は母親と妹との三人家族だ。良太の父の事故のときには、一郎はまだ中学に通っていたのだが、そのニュースは村中を悲しませた。当時良太は二歳で、妹はまだ腹の中だった。一郎は子供心に幼子が不憫で、良太のことが何かと気になって面倒見たりしていたのだ。 良太を船室に運び込んで寝かせてから作業が再開された。 魚を水揚げする頃には夜はしらじらと明けてくる。空が紅に染まりはじめる頃、船団は荷積みを終えて近所の大きな港へ荷揚げに向かう。そこには漁連の支所があり、そして市場があるのだ。 ● 一郎は昼近くになってからクタクタに疲れて家に着いた。さぁ夜まで寝るぞ、それから先は……一郎は鼻の穴を膨らませてニヤけながら家の中に入った。 「帰ったぞ!」 しかし夏江の返事がない。 「いないのか?」 部屋に入ると、夏江が泣きはらかした目をしてうつ向いたまま黙ってうなだれていた。尋常な様子ではない、何かがあったに違いない。一郎はとっさに悟って夏江に訊いた。 「なにがあったんじゃ、まさかおまえ……」 「孝一が、孝一が……」 「こ、孝一がどうしたんじゃ! 腹痛起こしたんか? 熱出したんか?」 夏江は首を横にふり、それからとぎれとぎれに話しはじめた。 話を聞いた一郎は、慌てて海岸へ走り、叩き台の向こうへ飛び込んだ。ほとんど絶望的観測で、せめて亡骸をきれいなうちにさがし出したいという一心で海底をさがし回った。 しかしどこをさがしても、孝一の姿はなかった。あとさがしていないのは、沈没した大型クルーザーの中だけだ。もしそこに逃げ込んでいるのなら助かっている可能性は高い。一郎は胸を踊らせて沈没船へと向かった。 クルーザーの船尾は少し砂に埋まっていた。船首の方半分は、デッキの縁にステンレスパイプのてすりが付けられてあり、おわんを斜めにかぶせたような形で海底に鎮座している。 デッキへ近付くには、このステンレスパイプの檻の隙間を見つけて入り込まなければならない。グルっと沈没船のまわりを一回りして、一箇所だけパイプのちぎれた場所を見つけ、一郎は一旦息継ぎに上がった後再びそこへ向かった。 パイプの切れ目から入り込もうとして、一郎は一瞬凍り付くように動きを止めた。目の前にヒレトバシカメウオがいたのだ。 ヒレトバシカメウオは普通体長二十センチくらいの魚で、鰭に猛毒を持っており、これを水中銃のように飛ばすことができる。この針にやられると人間でも絶命することがあるのだが、一郎の目の前に陣どっていたのはなんと体長二メートルもあろうかと思われる大型のヒレトバシカメウオだったのだ。 こんなのにやられたらひとたまりもない。一郎は一旦あきらめて海上に上がり、ヒレトバシカメウオに対抗するための水中銃と、アクアラングの装備をして出直すことにした。 ● 少年は、ほの暗く狭い室内で目を覚ました。 室内が全て逆さまになっているために、そこが沈没した大型クルーザーの船室だということを理解するまでに少し時間がかかった。 もう一夜が明けて日は高く上っているのだが、海底の少年には朝なのか昼なのか、それともまだ夕方なのかさえもよくわからない。薄明るいことから夜でないことだけはわかる。 少年は、逆さまになって沈んでいる大型クルーザーのデッキにあるハッチから船室の天井に上半身を乗り上げたまま気を失っていたのだった。船室内には十分な空気が残っている。 正気に戻るに連れて少年はどうやってここに入り込んだのかを少しずつ思い出してきた。 海底で気を失いかけたときに、髪の長い美しい女性が見えた。その女性の声に導かれて少年はここにたどり着いたのだった。それは人魚なのだろうか。少年は不思議な体験を思い返しながら、助かったという喜びを段々実感しはじめたが、あの女性のことが気にかかってしかたなかった。 とりあえず寒さをしのぐために室内に這い上がって身を縮めていたが、寒さがおさまったときに思い切って水面に上半身を突っ込み、ハッチの縁に手をかけて潜り、デッキの表面を見回してみた。 そこには、昨日の女性の姿らしきものが逆さまに見えた。 デッキと、海底の砂との間でフワフワと浮くようにして、髪の長い女性が立っているように見えた。少年には、それがポスターの写真か人形か何かのように思えたが、確かめられるほど接近するには、完全にハッチから出て泳がなければならない。少年はまだうまく泳げないのだ。 逆さまに潜っているために鼻から水が入り、鼻の奥がツンと痛む。それに耐えながら海底を見回している少年の頭の中に、またその女性の声が語りかけてきた。 ――――アブナイ……ヘヤニモドリナサイ…… 少年は体を上げて、再び船室の天井へ這い込んだ。 ちょうど父が沈没船の回りをさがしてヒレトバシカメウオに出会った頃、少年は女性の声にしたがって船室内へ入り込んでいたのだった。 しかしあのまま半身を海中にさらしていれば、父に見つけてもらえたかもしれないが、下手をすると親子そろってヒレトバシカメウオの針の餌食になっていたかもしれない。いや、十中八九二人ともやられていただろう。 少年はまたもやその女性の声に救われたのだ。 しばらくすると、またその声が聞こえてきた。 ――――イマナラ、デラレル……ソコノタナノドウグヲツカイナサイ ● ヒレトバシカメウオは、昼頃まで眠っていたが、目を覚ますとさっそく空腹を感じて狩りに出かけることにした。 出かける間際に、さきほどクルーザーのハッチから何者かが姿を見せていたような気がして、同居人に話しかけた。 ――――よぉ、おまえさん、さっきそこからなんか変なやつがのぞいてなかったかね 返事はない。 ――――けっ、どうしておまえさんはそうも無口なんだろうね。さっきはいったいだれと話してたんだよ やはり返事はない。 ――――やれやれ、おまえさんには嫌われてるみたいだな 同居人にちょっとだけ毒づいてみる。しかし彼は自分の孤独がこの同居人と自分の独り言とのおかげでずいぶん癒されていることを知っているので、それ以上文句は言わない。 今日は昨日の狩場とは別の、近くの狩場へ向かうつもりだった。細かい砂や砂利の狩場で、カレイかナガウオを狙うつもりだ。あそこは砂や砂利が砂漠の風紋のようにうねっているので、隠れて近付くには絶好だし、おまけに獲物の方も隠れやすいと思って油断しているので針を命中させやすいのだ。 相変わらず雨水の刺激にブルルと体をふるわせながら、ヒレトバシカメウオは狩場へと向かった。 ● 夏江は海岸で亭主を待っていた。 間もなく亭主は上がってきた。夏江は思わず立ち上がって亭主の胸にすがりついて言った。 「あの子は、あの子は見つかった?」 「いや、見つからねぇ」 夏江はほんの少し安心したが、絶望的な気持ちには変わりなかった。孝一の死が確定したわけではない。しかし、見つからないということはやはり絶望的な状況に変わりがないことを意味するのだ。 「そこの海底にでっかいクルーザーが沈んどる。逆さまだから中に空気が残っているかもしれん。もしもそこの中へ逃げ込んでたら、案外中で生きとるかもしれんぞ」 夏江は、生きとるかもしれんぞ、というひとことを耳にして、飛び上がりそうになった。生きているかもしれない、可能性があるのだ。藁にもすがる思いでその可能性が現実のものとなることを願った。 「あんた、はよぉその中見てきて! 孝一が、孝一がおるかもしれんのやろ? なんで、なんで見てこんのや、はよぉ、はよ見てきませ」 「あほ! ヒレトバシカメウオのこ〜んなでかいのんがおるんや。うかつに近寄れるか。あんなもんにやられたらこっちもひとたまりもないわい」 ヒレトバシカメウオ…… 夏江は息を呑んだ。手の平ぐらいのものでも、たまに人が刺されて救急車で病院へ運ばれる。それがひとかかえほどもあるなんて。 夏江のわずかな希望は、ヒレトバシカメウオというひとことのためにすっかり縮んでしまった。 亭主は家へ向かった。そこでアクアラングの装備をして波止場から小さな伝馬船でここまで来るつもりなのだろう。しかし水中銃で、化物みたいに大きなヒレトバシカメウオに対抗できるのだろうか。いくら亭主が水中銃の使い手だからといっても、針を飛ばすのはあちらの方が本職だ、やられなければいいが…… ● 少年が女性の声に導かれるまま棚をさぐると、そこにはスキューバ用のタンクとレギュレイターとBC、それにマスクがあった。 これはいったい、何をする器具なんだろう……? 少年は不思議に思った。マスクは顔にはめて使う水中メガネだというのはわかる。しかしその他の器具は何をどう取り扱えば良いものやら皆目見当もつかないのだ。 ――――タンクノ、クチノ、バルブヲ、マワシテミルノデス また女性の声が少年の頭の中へ話しかけてきた。少年はバルブを回してみた。 それはステンレス製ではあるが、少し錆び付いていてなかなか回らなかった。 何度も何度も試しているうちに少しずつ錆が取れてきて、バルブは少しゆるんだ。バルブの頭の四角い部分の横手に丸いくぼみがあり、そしてその中にある小さな穴から空気が勢い良く吹き出した。 少年はあわててバルブを反対に回して閉めた。 ――――ソノ、クボミノマワリニアル、ゴムノワッカニアワセテ、レギュヲトリツケルノデス レギュ? レギュっていったい…… ――――ホースノツイタドウグデス あ、これか。 少年はその器具を真っ直ぐに見たり斜めに見たりということを何回か繰り返して、やっと意味がつかめてきた。丸いくぼみの回りについているゴムの大きさと、ホースの片側の方の器具のはめ込み式の丸い部分の大きさとが同じなのだ。ここへこれを合わせて後ろからネジでしめ込んでやればいいのだ。反対側の部分は口に加えて空気を吸い込むのに違いない。 少年はそれを取り付けてくわえてみた。だが空気は一向に入ってこない。 ――――タンクノバルブヲ、ヒライテ あ、そうか。 少年は言われるままにバルブを開けて、それからマウスピースをもう一度くわえた。息を吸い込むと、「シュコー」という音とともに空気が入ってきた。 タンクには布の袋のようなものがついていて、両横に二つの穴が空いている。 ここに腕を通すんだな……そしてこれをくわえて、それからマスクをかぶって。 ――――ソレデイイノデス、ソレデミズノナカデモイキガデキマス、タダシゼッタイニ、イキヲトメナイデ、ズット、スッタリ、ハイタリシツヅケルノデス うん、わかったよ。 少年はその女性の声にすっかり勇気づけられ、さっそく水の中へ飛び込んだ。 少年は女性の姿を見て確かめることができると思い、さきほど人間がフワフワ浮いて立っているように見えた方を見つめた。だが影になっていてよく見えない。相変わらずそれはフワフワとデッキからぶら下がるようにして立っていた。 ――――ハヤクシナイト、ヒレトバシカメウオガ、モドッテキマス あ、ヒレトバシカメウオがいたのか。 少年は思わずあたりを見回した。上を見ると、自分の吐き出した泡がデッキの表面を這って逃げていくのが見えた。それと同時に人の足の骨らしきものが目に映った。 それで少年は大変なことに気づいた。ヒレトバシカメウオへの恐さも引金になり、少年の中でこれまで忘れ去られていた恐怖感というものが呼び覚まされたのだ。 こ、この女の人は、なんでこんなとこでフワフワ浮いてるんだろう? それからこの骨みたいなのはなんなんだろう? 少年はあわてて泡を撒き散らしながらその場を去った。 そして奇跡的にも叩き台の上にまで泳いで上がることができた。 ● 夏江は海岸でしょんぼりと海をながめながら、亭主が伝馬船でやってくるのを待っていた。 ほとんど放心状態で沖をながめる夏江の目に、何かが見えた。叩き台のあたりで何かが動いたのだ。 しかし夏江は、その動くものに対してなんの興味も抱かなかった。昨日から寝てないのだ。脳の働きもずいぶんと鈍っている。 手が叩き台にすがりつこうと必死でもがいている。 あー、手か。夏江はそう感じた。 顔にマスクをはめた頭が浮かび上がってきた。 あー、頭か。夏江はそう感じた。 手が顔のマスクを外した。孝一だった。 あー、孝一か。夏江は、そうつぶやいた。 ……孝一! 孝一が上がってきた! 夏江は一瞬信じられない気持ちで叩き台のあたりでもがいている頭と腕を見ていたが、やっと自分の息子であることをさとり、大慌てで泳いでいって孝一の体を引っ張り上げて抱えた。驚きとうれしさで声を失いながら抱き締めて泣いた。 もがいている間にタンクやレギュは海中へ没していたので、夏江は孝一がどうやって上がってきたのか、全く想像もできなかった。 夏江は気を取り直して孝一の顔色を見た。少し青ざめているが、大事はなさそうだ。孝一が何か言おうとしているので、夏江は孝一の口のそばへ耳を近付けて聞いた。 「ゆ、ゆうれいが、ゆうれいがたすけてくれた……」 夏江は、孝一が動転しておかしなことを口走っているのだと思い、とにかく冷えた体を暖めてあげることと、診療所へ連れていくことを考えて孝一を抱えたまま海岸まで泳ぎ着き、急いで家へ向かった。 ● 一郎の伝馬船が叩き台の少し沖に着いて停まった。 一郎は浜辺の方を眺めてみたが、夏江の姿がない。いったん家に戻ったのか、それとも波止場で待つつもりなのか。どちらにしろ、そんなことを考えている余裕はなかった。 黒いウェットスーツに身を包み、アクアラング機材を装着して、水中銃を持って早速潜り、目的のポイントにたどり着いた。 ステンレスパイプの切れ目からおそるおそる中を覗くと、ヒレトバシカメウオは先ほどの場所にはいない。どこか物陰にいるかも知れないと思い、一郎は注意深くパイプで囲まれたデッキと砂地との間の空間へもぐり込もうとした。 ところが背後におぞましい気配を感じて思わずその場から離れた。クルーザーの船体に十センチほどの針が音をたてて突き刺さった。 一郎は体をこわばらせた。こんなところでヒレトバシカメウオとの勝負になろうとは思いもよらなかったのだ。一郎の緊張とは裏腹にヒレトバシカメウオはユラリユラリと遊ぶように一郎の回りを泳いでいる。腹を見ると相当なふくらみようだ。きっと餌を腹一杯喰ってきたに違いない。一郎は少しだけリラックスした。 勝負は一瞬で決まるだろう。こちらのヤスが外れた場合、ヒレトバシカメウオは危険を察知して残りの針を一斉にぶち込んでくる可能性もある。そうなったらよけきれない。しかし狩りで針を使っていれば、そう多くの針は残っていないはずだ。 一郎は注意深く水中銃を構えた。ヒレトバシカメウオは、相変わらず満腹の腹を抱えて鈍くウロウロするばかりだ。だが鈍い動きにも隙がない。 しゅぴ! 一郎がヤスを放った。まるで空気中を矢が飛ぶような鋭さで真っ直ぐに飛び、ちょうどヒレトバシカメウオの両目の間をめがけて走る。だが思いがけないような俊敏さでヒレトバシカメウオは体をねじり、ヤスをよけてしまった。砂の中にヤスがめり込む。一郎はあせった。次のヤスを装着しようと腰の筒をまさぐるが、なかなかヤスが取り出せない。 ヒレトバシカメウオは体を丸めて背鰭をいっぱいに広げ、くるりと横になった。背鰭の針は最も強力で、ヒレトバシカメウオの切り札なのだ。だが体を丸めてしまうために命中率は低い。そのため放射状に広がったヒレからありったけの針を飛ばしてくる。 とっさに一郎は身を翻してクルーザーの向こう側へ回り込もうとした。間に合うかどうかはわからない、すでにヒレの付け根に圧縮空気が充填されていれば即座に針が飛んでくるだろう。 一郎が、上向きになった船底の表面の海綿に沿って這うように泳いでいるとき、後方からぶぶっという発射音が聞こえてきた。船底に張り付いて、神にすがる思いで目を閉じた。船体に針が突き刺さる音がした。頭の上の方を飛んでいく針の、水を切る音も聞こえた。同時に足の先の方でごつんと衝撃が走った。背中全体を悪寒が走った。恐怖で体がこわばり、動けなくなりそうだったが、気を取り直して振り返った。 切り札を出してしまったヒレトバシカメウオは、ぐったりして砂の上に横たわっている。上半身を起こして足の先を見てみると、ゴム製の足ヒレに針が一本刺さっていた。攻撃を凌ぐことができたのだ。とたんに一郎は強気になった。海綿の上で立ち膝になり、ヤスを取り出して再び水中銃を構え、発射した。 鋭く飛んでいくヤスが、とても頼もしく見えた。ほとんど速度をゆるめないまま、ヤスはヒレトバシカメウオの両目の間にめり込み、矢尻を数センチ残して止まった。ヒレトバシカメウオの両目は真ん中に寄ってしまい、まるで〈何が起こったのか全くわからない〉という表情を浮かべたかのように見えた。しばらく体をびくつかせていたが、そのまま腹を上に向けて、赤い血を漂わせながらヒレトバシカメウオは果てた。 一郎は緊張が解けて体中をしびれが覆い尽くすような感覚にとらわれた。しばらく息を吸い込むのを忘れていたため急に息苦しくなり、大きく息を吸い込んだ。「シュコー」という吸音がやけに大きく聞こえる。それから大きな泡を吐き出した。 足ヒレに刺さった針を抜こうと注意深く引っ張る。だがなかなか抜けない。針は20センチ近い長さだった。これがもし体のどこかに命中していたら、確実に命を落としていただろう。再び背中に悪寒が走った。 なんとか針を抜き去って、クルーザーのてすりの間を抜けて中へ入った。薄暗い海底で、ヒレトバシカメウオとよく似た形のものがデッキからぶら下がるようにしてフワフワ立っているのが見えた。体中から血の気が引いた。もう一尾いたのか!? 慌てて水中銃にヤスを取り付け放った。続けて数本のヤスを放つ。全てが命中し、物体からは青白い体液のようなものがにじみ出て、あたりを濁した。 獲物が動かないのを確認して、一郎はそれに近付いた。よくよく見てみると、それは葉巻型をした巨大なホヤであった。ホヤというのは原索動物の一種で、空に浮かぶ雲のように白くてもこもこしている。イソギンチャクに似た構造をしており、内部は空洞だが口はない。口の代わりに小さな穴があって、普段は閉じられている。細い一本足のような根っこで岩などにつかまってぶら下がる、袋のような生き物だ。 一郎の目の前の巨大なホヤはデッキに根を張っていた。ホヤが根を張る部分には女性らしき白骨死体が、デッキに固定されるように横たわっていた。長い髪がまばらに残っている。珊瑚の一種が繁殖した名残であるカルシウムの殻がデッキの一面に広がり白骨死体もいっしょに包み込んでいたのだ。 ホヤは体液を吹き出して少し縮み、そのうち息絶えたのか根の部分が切れて底の砂地に静かに落ち、横たわった。 一郎は船室に入るハッチを見つけ、そこから顔を出して中を覗いてみた。だがそこに孝一の姿らしきものはなかった。 一郎は愕然となった。船室へ這い上がり、中の戸棚などをしらみつぶしにさがした。戸棚などがつい最近物色されているような形跡がみてとれた。もしかしたら、自力で抜け出したのかもしれない。ほとんど可能性はないが、そう考えて絶望感からのがれようとした。だが肩がどっと重たくなり、全身の力が抜けていく感じを、どうすることもできなかった。 あきらめて海上に上がり、伝馬船を港へ戻して道具をかついで家に帰った。ウェットスーツがなかなか脱げない。手にも力が入らないのだ。なんとか脱ぎ終えて水をかぶり、それから体を乾かして家にはいると酒を飲み始めた。 一郎はやり切れなかった。孝一が見つからなかったことに加えて、ホヤを撃ち殺したことがなんとも後味悪く、どうにもやり切れなくて一升瓶をラッパ飲みにしてそのままつぶれて寝てしまった。 ● 夏江が診療所から孝一を連れて戻ってきたときには、すっかり日は傾き、家の中はかなり暗くなっていた。一郎は、薄暗い茶の間の卓袱台の横で寝ていたが、いつのまにか流れ出た涙が顔中をベタベタにしていて、夏江はそれがおかしくてクスクス笑った。蛍光灯のひもを引いて明かりをともす。 夏江が何を笑っているのかを理解できない孝一が、怪訝そうな視線を向ける。 それから父親の方へ視線を向けて心配そうに、 「おとうさん、風邪ひかんかな」 と、つぶやく。 夏江は、少し意地悪な気持ちで 「おとうさんが、風邪ひくわけないわ」 と言った。笑いがこみ上げてきてしかたがない。孝一の無事を早く知らせてやりたいのに、当人は悲しみのうちに眠りこけてしまっているので伝えようもない。伝えることができればどんなに喜ぶか、それを想像すると、うれしくてうれしくてどうしようもないのだ。うれしい知らせを一番伝えたい人に伝えることができないもどかしさというのは、まるで腹や脇の下をくすぐられているような変な気分だ。 「あんた、あんた……」 夏江は何度も一郎の体を揺さぶった。だが一郎は全く反応しなかった。相当深く眠り込んでいるようだ。仕方がないので起きるまで放っておくことにした。 そのときはまだ夏江も、孝一の命を救ってくれたホヤを一郎が撃ち殺していたことなど全く知らなかった。 海から上がってきてから、ずっと寒さを訴えていた孝一だが、今では顔色も赤みを帯び、精神状態もかなり落ち着いていたので、お粥を作って食べさせることにした。孝一は、おいしそうにお粥をたいらげた。それからテレビの横の棚からおもちゃを引っぱり出して遊びにかかった。すっかり元気が回復したように見える。 夏江は、ことの成りゆきを聞き出して叱っておかなければならないと思い、おもちゃを片づけさせて孝一を子供部屋に連れて行った。そこで、どうしてこんなことになったのかを説明させた。 浮き輪が流されたことや、西日でよく見えなかったことなどを孝一がぽつりぽつりと話した。黙って聞いていたが、だいたいのところを聞き終えると、夏江は孝一に説教を始めた。落ち着いているとはいえ孝一はかなり体力を消耗しているはずだ。あまり強く叱るわけにはいかない。短く注意だけして、布団に寝かせることにした。 掛け布団をかけてやりながら、孝一の額に手を当てて熱がないか確かめる。母親らしく優しい声で、 「気分悪いことないか?」 と訊ねると、孝一は小さくこくりとうなづいた。それから、眠りに入る前のぼんやりした状態のまま、孝一はまたもやおかしなことを言い始めた。 「おかあさん、ゆうれいがね、ゆうれいがぼくをたすけてくれたんや」 「また、おまえって子は……夢でも見てたんやないの?」 孝一の傍らに添い寝しながら、夏江は言う。 「でも、でもほんとうやもん。髪の毛のながいおんなのひとのゆうれいやったもん。あの船に、骨があった」 夢にしてはあまりに具体的すぎる。もしかすると本当のことなのかもしれない。とたんに夏江の背中に寒気が走った。 「本当に、本当に見たんやね?」 「うん、ほんとうや」 孝一は、力強く言った。 夏江は寒気を感じた。だが、恐ろしさよりも不思議な縁というものを感じて、しみじみとした気持ちになった。弱い驚きが、しばらく続いた。まるで神秘的で美しい芸術作品に出会った時のような、そんな感慨が胸に満ちた。その幽霊に感謝せずにはいられなかった。 その夜、軽い夜食を用意してから、孝一がよく眠っているのを確かめ、夏江はもう一度一郎を起こしてみた。一郎は、もがもがとわけのわからない寝言を言いながら、そのうちゆっくり目を覚ました。 「あんた、孝一がね、クルーザーの中で髪の長い女の幽霊に助けられたんやってゆうてるんやけど」 すでに夏江の頭の中は、孝一が助かったことを伝えなければならないという気持ちよりも、幽霊のことでいっぱいだった。 「あ? こ、孝一がいたんか? 生きてたんか? ど、どこにおったんや!」 一郎はあわてて飛び起きた。拍子に卓袱台に膝をぶつけてしまい、そこを押さえてうずくまってしまった。 「あ、あんたが言うてたあの……、大丈夫か?」 夏江は、一郎があんまり痛そうにするのでそちらの方が心配になってきた。だが、一郎は突然頭を上げて大声で、 「やっぱあれか、クルーザーの中か! 自分で海面まで上がったんやな」 と言った。 夏江は一郎の大声が頭に響いて何を言っていいのかわからなくなってしまった。とにかくウンウンとうなづいていた。 「やっぱり、やっぱりそうだったか、良かった、ほんまに良かった。近所の人らに知らせたか? おめーのかあちゃんにも知らせたか、よろこんどったやろ」 夏江が答えようとしているのに、一郎は見向きもせずにドタバタと走って孝一の寝床を見に行った。夏江もそれに続いて行った。一郎は孝一の頬に自分の頬をすりつけて涙を流し、そのうち嗚咽をもらし始めた。夏江はしばらくその様子をながめていたが、つられて一緒に泣いた。ひとしきりして一郎は口を開き、 「あー、良かった、ホンマに良かった。神様ありがとう」 と言った。 「あんた、それなんやけど……」 一郎は夏江が話しかけるのに全く取り合わずに頬ずりを続けていた。しばらくしてから納得したのか、孝一から頬を離して夏江に訊き返した。 「なんじゃ?」 夏江は、どう説明していいのか迷いながら、困ったように切り出した。 「ほやからね、孝一が言うには、髪の毛の長い女の幽霊に助けられたちゅうことやて」 「髪の毛の長い……あー、おったで、白骨になったどざえもんが、クルーザーのデッキにへばりついてた」 一郎は驚いた風でもなく、平然と答えた。 「ホ、ホンマやの? ほやったら、この子の言うたことは、やっぱ本当のことやったんやねぇ」 夏江は、孝一の言ったことが本当だったという確信を得て、しみじみと言った。 一郎は、少し思案するような顔をしてから相づちを打つ。 「ああ、それがほんとならその幽霊にぎょうさんとお礼せなならんな……あ!」 「なに? もうこれ以上おどかさんといてね」 「あのホヤ」 「ほやからなんやの?」 「ホヤや」 「ほややーて、なんやの?」 夏江がじれていらだちながら聞き返す。 「ほやから、ホヤっちゅう生きもんがおるんじゃ! あほたれ」 一郎の声が大きくなる。夏江は顔を曇らせて 「なんでわてがあほたれやの?」 と言い返す。 「あほたれじゃ、子供一人あんなとこで遊ばしてほったらかしよって」 「そんなん、誰かてあんなとこ勝手に遊んでるやないの」 夏江の目に涙が浮かんだ。一郎はあわてて取り繕うように、 「あー、わかったわかった、それはええ。ほやからな、ホヤ喰うたことあるじゃろーが、おめーも」 と、話を戻した。 「あ、あのホヤか」 「ほやほや」 「変なシャレ言わんとき」 夏江は涙を拭いながら苦笑いして言った。 「シャレと違うわい。そのホヤがな、えげつないおっきなホヤでな、どざえもんから生えとったんじゃ」 「ちょっとあんた、それって……」 「ああ、きっと女の魂がホヤにのりうつっとったにちがいない」 「ほんなら明日潜って行ってホヤにお礼言わなあかんな」 「それなんやけど……」 「なんやの?」 「そのホヤ撃ち殺してしもたんや」 「えー! 命の恩人やでぇ!」 「明日どざえもん引き上げて成仏さしたるわ」 「……うん、ほやね、それがええわ」 ● その後、白骨死体は一郎が引き上げて寺で供養を行い、クルーザーの船籍から身元を割り出して遺族に知らせた。 クルーザーが海難に遭った海域は、村から数百キロも離れた場所だった。 そうして、孝一を助けた女性の魂は一郎のおかげで成仏することができた。 水死体を引き上げて成仏させた漁師は、一年間は大漁に恵まれると言われている。その年、村の巻網は実に例年の十倍の水揚げをしたということだ。 |
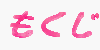
|
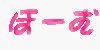
|