自作ノベルス
Copyright (C) by s-maru 2001
|
トンネル 歩道橋から電車をながめるのが好きだ。 長い電車の流れはとめどなく、まるで胃の中にスルスルと入って来るみたいだ。そうやってどれだけの電車を呑み込んだことだろう。 駅の東口商店街の裏路地に、西口商店街の裏路地へ通じる古い歩道橋がある。 表面がゴツゴツになった赤錆の手すりから、雨だれで色が伝い落ちて、コンクリートに流水模様がついている。 この場所が一番気に入っている。めったに人が通らないから。 ポケットから小石を取りだして、走る電車の上に落としてみた。わかってるんだ、それがどんなに危険かということ。走る電車に小石があたったりしたら。 運転席の窓を突き破って運転士に当たっちゃうかもな。運転士は額に穴が空いてそのまま死んじゃう。そして、電車は脱線して踏切から一般道路へ飛び出し、通学途中の小学生達の中へ突っ込んでいく。たくさんの命がぐちゃぐちゃにつぶされて、髪の毛と血と目玉と、それからどろどろした白い脳とか、骨とか、そういう普段は人の目に触れることのないような複雑なモノへと変化してしまう。 数秒の間だと思う。僕がそんなしょうもない妄想を抱いていたのは。妄想は、電車の屋根で小石がはじき飛ばされる「カチン!」という音で終了するはずだったんだ。 なかなか終了しない。いや、いつまで待っても「カチン!」って言わないんだ。騒音にかき消されたのか、それとも電車に当たらなかったのかな。 僕は、手からこぼした小石を確かに目で追っていた。でも、僕の目はいつでも対象物よりも遠くに焦点を置いている。はっきりと見て取るのが苦手で、いつだって突き通して遠くを見ているんだ。ぼやけて二つに別れて見える。そうやって知覚認識するのが、世の中と関わり合うには一番楽チンなつき合い方じゃないかな。少なくとも僕にとってはそれが最も良い方法なんだ。 だから、小石の行方なんてわからない。 後ろの方で、「カチリ」と音がした。 何かのスイッチが入ったみたいな音だった。もしかしたら、僕の生命の終了プログラムが起動した音なのかもしれないと思った。そんなわけない。一人で苦笑いしながら振り向いた。 僕がここに来てから、誰一人後ろを通っていないし、この歩道橋は滅多に使われないはずだ。 僕の真後ろに、小石があった。拾った。この表面の丸みや凹凸、亀裂の入り方、僕の指は全部記憶していた。さっきの小石だった。手の油がしみ込んで、黒い光沢がある。最初に拾ってから38時間もの間、ずっと僕のポケットの中にあった。 風圧で吹き飛ばされて戻ってきたのだろうか。いや、それはあり得ない。 億劫になって、考えるのをやめた。再び手すりに胸をもたれかけて電車をながめた。 鋼のこすれ合う騒音も、そのうち耳に入らなくなった。上とか下とか、そういう区別もよくわからなくなってくる。無音の電車が、レールを駆け上がって天高く舞い上がっていく。 電車がとぎれた。信じられないような静寂が一瞬だけ僕のまわりに落ちてくる。 僕の母さんは、結婚する時妊娠していた。父さんじゃない誰かの子供、つまり僕がお腹にいたんだ。でも、父さんは承知の上で結婚した。父さんは僕のことも母さんのことも許してくれている。 本当に心の底から許してくれているみたいなんだ。もう23年のつき合いだ。それくらいわかるさ。 僕がそれを知ったのは、20才の時だった。 一人っ子の僕は、父さんのことが大好きだよ。本当に良い父さんなんだ。僕のことを一番よく知っているのは、やっぱり父さんだ。 もう一度、小石を落としてみた。またしても後ろの方に落ちてきた。何度も何度も試しているうちに、気づいた。 僕の目の下のこのあたりに、目に見えないトンネルがあるみたいなんだ。つまり、歩道橋のあっちとこっちが、U字型のトンネルでつながってる。次元のひずみか何かでできたトンネル。 それなら、ここから飛び降りても、またこの歩道に戻って来るんだろうか。 小石を落とす範囲をいろいろと調節してみた。今度は、じっと見ながら落とす。空中でフッと消える。それから後ろに飛び上がってきて、歩道へ戻る。 少なくとも、人間一人がすっぽり入れるくらいの穴があることはわかった。 おそろしいのと同時に、ものすごく興味をひかれた。どうせ、何もかもイヤになっているところだ。何かに自分を賭けてみたって、それもいいんじゃないだろうか。 もしかしたら、トンネルを通って出てくれば別人のように器用になって、みんなと同じようにちゃんと人付き合いができるような、そんな人間になっているかもしれないじゃないか。 世の中の誰もが、人間関係の海をスイスイとうまく泳いでいる。どうしてみんな、あんなにも器用なんだろう。場の空気をつかむのがとてもうまい。誰も前もって教えてくれないのに。 僕なんか、ちっとも気が回らないし。人が喜ぶことなんて何一つできやしない。気の利いたことなんて何一つ言えやしない。言葉に詰まって黙り込んでばかり。たまにしゃべると、他人を退屈させるか不愉快にさせるかのどちらかだ。 僕は、父さんのことを許せなかった。僕と母さんのことを、本当に心から許してしまうなんて、そんなこと絶対許せない。 僕と母さんのことを許してくれない父さんに会ってみたいと思った。僕にとってその人は父さんとは別人なのかもしれない。それでもいい。たとえ別人でも、父さんでありさえすれば。 風が強くなってきた。ジャンパーの襟を立ててほっぺたに当てる。デニムの生地じゃ、風はすかすか通ってしまって、背中が痛いほど冷たい。あごがガチガチ鳴り出した。 もうすぐ、陽が射してくるはずなんだ。だって、せっかく朝なんだもの。もし陽が射さなかったら、朝なんかにいったい何の意味があるだろう。僕は背中で陽の暖かさを感じるのが好きなんだ。それだと、太陽を見なくてすむから。 それほど迷わなかった。このまま生きていたって、どうせ死んでいるのと同じだと思っていたからだ。 飛んだ。錆の浮き出た手すりに右手を置いて、両足でピョンとまたぎ、そのまま勢いをつけて小石の消えるあのあたりへと。 真下に電車があった。僕の頭の中には、電車にぶつかってぐちゃぐちゃにくだける自分の姿があった。このまま死んじゃうのも良いかもな。 でも、本当にトンネルはあった。足先から消えた。ボロボロのスニーカーが、次にすり切れたGパンが、毛玉だらけのセーターが、スーッと消えていくのを見ながら、頭まで入り込んだ。 気が付くと、白い光の中に放り出されていた。ここは本当に上も下もない。言うなれば、どこかよその宇宙だ。遠くや近くの区別もない、目の前で明滅する光の玉は、取り返しのつかない過去と同じくらい遠くにあるんだ。 自分の身体が見えていた。スニーカーやGパンや、足のすね毛とか、そういうものが境界を曖昧にしている。自分の足を見下ろしているのに後頭部が見える。スニーカーを見ているとお尻が見える。 こっちじゃ、光が真っ直ぐには進まないってことだろうか。 遥か下の方に小さな裂け目が見える。こっちからはあっちが見えるようになっているらしい。鉛色の空も見える。出口だ。 急に胸がわくわくしてきた。本当に、単なるワープだ。ただ入って出るだけの、遊園地の遊具みたいなもんじゃないか。これは、結構スリルのある遊びだ。 出口が迫ってきた。このまま歩道の上まで放り上げられて、元の場所に戻るってわけか。 足が出口に入った。 突然、激しい痛みが走った。まるで犬にでも噛まれたみたいな。顔をしかめながら足を見てみると、骨になっていた。 そのまま、下半身がどんどん骨になった。 激痛がせり上がってくる。 骨は、風化して白い粉になり、鉛色の空へ舞い上がっていった。 「ギャー!」 痛みのあまり叫んだ。だが、それもつかの間のことだった。頭まで全部骨になった時には、もう僕の意識は消えていた。 ● 歩道に、ほんの些細な風が吹いた。それは生暖かく、「ゲップ……!」という声のように鳴り響いたが、歩道橋に人影はなく、誰も聞いてはいなかった。 |
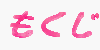
|
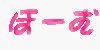
|