自作ノベルス
Copyright (C) by s-maru 2001
|
後悔 大阪駅に着いた。 改札を抜けて構内を歩いている時、和服姿の老婆がしゃがみ込んでいるのが見えた。無視して通り過ぎようと思った。都会だからって、人は冷たいわけじゃない。忙しすぎるだけだ。浩二自身もそうだ。今は時間がない。 しかし、浩二は無意識のうちに老婆の方へ歩み寄っていた。足の方は勝手に老婆のそばで動きを止めてしまった。 黙って突っ立ってるわけにもいかず、身体をかがめて、 「婆ちゃん、どないしたんや」 と、訊いてみた。 老婆は、苦しそうに顔を上げると、 「どうもおへん。あんさん、どこのどなたかは存じませんけども、ご親切にありがとさんです。しばらくこうやっとったら、じき良おなりまっさかい」 と、息も絶え絶えに言った。 「どうもないことないがな。めちゃしんどそうやで。病院連れてったる」 浩二は、しゃがんだまま背中を向けて、おぶさるように促した。 「そないなこと、悪いがな」 「なんも悪いことないて。ワシも今病院行くとこなんや」 「あんさん、どっか悪いのかいな」 「いや、ワシとちゃうねん。そんなことどうでもええがな。はよ乗り」 老婆は、ヨタヨタとよろけながら浩二の背中にもたれかかった。そのままおんぶしてタクシー乗り場に向かった。 タクシー待ちの行列の最後尾に加わった。 目の前の若い女性が振り返って、浩二と老婆を見た。すぐに順番を譲ってくれた。その前にいた若い男の子も、おばさんも、次々と順番を譲ってくれた。前から6番目ぐらいのところで、中年の男の後ろに立った。グレーのコートを着た、少し太り気味で髪が薄くなりかけた男は、一度振り向いたが、苦々しい顔をして前に向き直ってしまい、譲ってはくれなかった。意外にも、涙もろそうなオヤジに限って冷たいのだった。 もしかすると浩二自身も、普段は無意識のうちにこの男と同じようなことをしているかもしれない、そんな気がして胸が痛んだ。 浩二は、あと4年で50才になる。前にいる男は、おそらく50代の前半ぐらいだろう。5〜6年もすれば、自分も胸の痛みさえ感じなくなってしまうのだろうか。 「すんまへん、あんさん、もう下ろしとくなはれな。なんやら体裁悪うてしょうがないがな」 後ろで老婆がつぶやいた。 「気にせんでええ」 「せやかて、ワテもう歩けまっさかいに」 「無理したらあかん。それより、病院に着いたら婆ちゃんの家の人に連絡せんとあかんな。電話番号とか、わかるか」 「電話はあるけど、家には誰もおりません。犬はおるけどな。ひっひっひ」 「おかしな笑い方しよるなぁ。そんならどこへ連絡したらええのや」 「身内は、誰もいてしまへん。天涯孤独っちゅうやっちゃ」 「子供もおらんの?」 「はい、ワテ、独身だ」 老婆の声は、通常会話程度に回復していた。 「格好悪いけど、おとこはんの背中ちゅうのも悪うないなぁ。何十年ぶりやろ」 老婆は、浩二の背中を手のひらでさすり始めた。 「わかった、下ろしたるがな。ほんまにもう」 「いやや、下りひんで」 「なんや、冗談で言うとったんとちゃうんかい」 「冗談やがな、冗談の通じんお人や」 浩二が少ししゃがむと、老婆はひっひっひと笑いながら背中から下りた。 「えらいお世話さんになりました」 小さな老婆は、小さく会釈した。ちょうど、タクシーがやってきた。 「一緒に病院行くねやろ」 「いや、もう家帰りまっさ」 浩二は、後ろに並んだ列の人々の顔を見た。全員に注目されている。これでは順番を譲ってくれた人達に申し訳が立たないと思い、とにかく一緒に乗り込んで発進してもらった。 老婆が行き先を告げた。病院とは反対方向だった。 「ほんなら、婆ちゃんを家まで送り届けて、そこからそのまま病院行くことにするわ。婆ちゃんかて、タクシー代払うの大変やろ。ワシ払ろたるさかいな」 老婆は、滅相もないという顔をして 「そないなことできますかいな。あんさんはどっかその辺で下りなはれ。タクシーならその辺でも拾える」 浩二は、どうも引っかかった。老婆の顔はまだ真っ青なのだ。心配かけまいとして無理しているのではないだろうか。 「ええがな、とにかく婆ちゃんが無事家までたどり着くのを確かめんことには気がすまん。ホンマに、病院行かんでもええねやな」 「家についたら、かかりつけのお医者さんに来てもらいますよって」 「よし、わかった。とにかく家まで送るわ」 「ホンマに、奇特なお方や。ひっひっひ」 ほどなく、タクシーは郊外の住宅地に着いた。 「ほな、気ぃつけてな」 「ホンマに、ありがとさんでした」 老婆は、そう言いながらタクシーを降りた。ヨタヨタと歩いて玄関に向かった。 運転手に行き先を告げると、車はそばの空き地で方向転換して去ろうとした。 車中から老婆の方を見ると、玄関口でうずくまって倒れていた。 「運転手さん、止めて下さい!」 急停車させて、老婆のそばへ駆け寄った。 「やっぱり無理しとったんやな。今から病院連れてくで」 「その必要ない。血糖値が下がっとるだけや。先生に来てもろうて点滴してもうたらすぐに良おなりますよって。どうか、家の中へ連れて入って下さい」 浩二は、タクシーまで戻って料金を払い、老婆を抱え起こして家の中へ連れて入った。 「すんまへんなぁ」 ベッドに横になって、老婆は幾分顔色が良くなってきた。白い小さな犬が、ベッドの横で心配そうにたたずんでいる。 かかりつけの医者にも、すでに電話を入れた。医者が来るまでついていてやることにした。 「婆ちゃん、立派な家に住んどるなぁ」 「ああ、金は仰山あるで。せや、タクシー代立て替えてくれたんやな。返さんと……」 老婆は起きあがろうとした。 「そんなもん、ええやんか」 「そうかぁ、悪いなぁ。それより、あんさん急いどったんちゃんうかいな。もう大丈夫やさかいに、はよ病院行きなはれ」 「あ、そや。ちょっと電話借りるで」 「どうぞどうぞ、いくらでも使ことくなはれ。なんやったらアフリカまで国際電話かけてもええで」 「アフリカに親戚はおらんわい」 浩二は、玄関口の近くにある電話台の方へ向かった。妻が、危篤なのだった。大学に通っている長男と、吹田市へ嫁に行った長女とが、すでについているはずだ。 電話を終えて、浩二は老婆の部屋へ戻った。 「ほな、そろそろ去ぬさかい」 「はいな、ホンマにありがとさんでした。って、あんさん真っ青やで。どないしたんや」 「なんでもない」 「なんでもないことあるかいな。ぶっ倒れそうな顔しとるがな。何があったんや。話してみなはれ」 浩二は、その場に座り込んだ。 「女房が…… 女房が、逝きよってん」 「な、なんやて! そ、そんな大事な時に」 老婆は驚き、それから涙ぐんだ。 浩二は、うつむきながら力無く言った。 「かなうんやったら、半年前に戻りたい。半年早く治療してたら、女房助かってたはずやねん」 「アホやなぁ、時間が戻るわけないがな」 老婆は泣き声になり、続けて言った。 「ワテみたいな婆ぁ一人構うとったばっかりに、女房の死に目にあわれへんなんて。あんさん、アホやで」 老婆は涙をこぼした。 「せやけど、婆ちゃんのこと放ったらかして病院行ってたらな、きっと女房にどやされとるわ。年寄りが困っとんのに、見放してきたんか、言うてな。そういうやっちゃねん」 「あんたら、夫婦そろって大バカモンや」 老婆は、布団で顔を覆って泣いた。 三十五日の法要を終えて、日々の生活も日常を取り戻しつつあった。葬儀のときも、それから後も、浩二は涙を流さなかった。妻がいないという現実をなかなか受け入れることができない。今でも信じられないのだ。 居間で寝っ転がっていると、買い物袋をたくさん持って、あわただしく妻が帰ってくる。「まーたゴロゴロしてからに」とぼやかれる。「ああ」と生返事を返す。それがごく自然で当たり前で。 テレビを見ていると、台所には妻がいるような気がするし、それを疑うことはなく、そのうち夜になり、「ああ、おらんかったんやな」と気付く。 妻が死んでからというもの、浩二の中の時間は止まってしまっていた。 ある日、なんの気なしにテレビを見ていた浩二は、見覚えのある人物を画面の中に見かけた。 大阪中座で講演されている芝居が上映され、あの老婆が主役を演じていたのだ。主役の名前は、浩二も知っている。日本中で知らない人はいないというくらい有名な喜劇女優だ。 浩二は口を開けたまま呆然としてテレビを見ていた。老婆は、画面の中で青年の背中におぶさりながら、 「何十年ぶりやろ、おとこはんの背中は」 と言って背中をさすり、気持ち悪がられている。客席でドッと笑いが起こった。浩二は食い入るように芝居に見入った。 老婆が自宅のベッドの中で、 「あんたら、夫婦そろって大バカモンや」 と言って泣く場面になった。 それまで全く出なかった涙が急に溢れ出してとまらなくなった。子供が泣きじゃくるような嗚咽がもれてしまい、息することもままならない。 やはり、生きている間に一目でも会っておきたかった。浩二は妻の名前を呼びながら、体をよじらせよじらせ、何時間も泣き続けた。 |
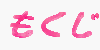
|
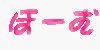
|