自作ノベルス
Copyright (C) by s-maru 2001
|
ボタンの壷 臼羽剣太は、十数年もの間探し回っていたものをやっと見つけ出すことができて、少なからず興奮していた。海岸に打ち上げられた、まるで象牙の加工品のような美しい壷、そしてそれを背負うようにしてつながっている小人の白骨死体。 「やはり、存在するのだ」 剣太は歓喜を押し隠すように低く独り言を言った。この十五年間に調べ上げて来たことが今ここで具体的な証拠と共に確かなものになった喜びに思わず顔が緩み、そして涙腺まで緩んできた。 ● 思えば不思議なことだと、剣太は思った。あの壷に出会いさえしなければ、剣太は今も妻や子と共に平凡だが幸せな毎日を送っていたはずなのだ。 十五年前、繊維会社のエンジニアだった剣太は、中国でナイロン製の靴下を製造するための合弁会社設立にあたって、技術派遣員として中国へ渡った。上海から北回りに迂回している鉄道で目的地の武漢を目指す長旅の途中、徐州という町に一泊したときのことだった。 列車の固い椅子で十時間以上も辛抱していた剣太は、部屋のベッドに体を投げ出すと、そのままウトウト眠り込んでしまった。部屋で目覚めたときには、ベッドサイドの照明に薄暗く照らされている天井や壁だけが見えた。寝ぼけたまま起き上がったとき、剣太は部屋の中に幻のような人影があることに気づき、しばらくしてそれが侵入者だと気づいて仰天した。 節くれだった杖を持つ、仙人のような汚らしい老爺で、ただ黙って部屋の中に立っていた。 外国人しか利用しないようなホテルへどうやって忍び込んだのかちょっと理解に苦しんだが、建物自体粗末なホテルが防犯管理に頓着していないのもしかたがないことだと思い当たった。 とっさに手荷物が物色されていないか確かめようと旅行カバンを手に取り、中を確かめたが物色されたような痕跡はない。泥棒なら、とっくに逃げていることだろう。 本当に人間なのかどうか確かめようとじっと見つめていると、老爺はまるで床の上を滑べるように移動して椅子に腰掛け、テーブルの上に置いてあったカボチャの種をポリポリとつまんで食べ始めた。動き方は仙人みたいなのにやることは人間くさい。 電話でフロントを呼び出すが、全く応答がない。 ドアの近くの壁のところまで歩いていって、部屋の明りをつけた。老爺はカボチャの種を喰う手を止めて、不思議そうに剣太の顔をのぞき込んだ。 剣太は、日本語以外には英語がほんの少しわかるというだけで、北京語も広東語も福建語も全く知らない。黙ってドアを開けて老爺に向かって手招きをし、その手をドアの外へ向けて出て行くようにと訴えかけた。 老爺はまだ不思議そうに剣太をながめていたが、そのうち何かを理解したという風に「あーうー」とうなずき、笑顔を見せた。剣太も理解してもらえたと思って絵顔になり、ウンウンとうなずいて見せた。すると老爺は、肩から下げていたズダ袋の中をまさぐり始めた。剣太はそのとき嫌な予感がした。 予感は当たり、老爺が袋から取り出して見せたのがその壷だった。老爺は美術品を剣太に売りつけることが目的だったのだ。剣太が手を横に振って断ろうとすると、老爺は壷をテーブルの上に置いたまま再びカボチャの種をむさぼり始めた。もう床の上は種の外殻でいっぱいに散らかっていた。 剣太が寝ている間に荷物を盗むこともせずに待っていたくらいだから悪人ではないというのはわかる。剣太は老爺のことを少し信じてはいた。 しかたなく老爺と向い合って座り、困った顔を作った。老爺はうれしそうに笑いながらうなずくだけだ。どうせ大した金額じゃないだろうとたかをくくって壷を手に取って見てみたとき、剣太はその象牙のような質感と細工の緻密さに目を奪われて、再び仰天した。骨董品など扱ったことのない剣太にも、それがとても価値の高いものだということがわかった。 剣太はさっそく財布を取り出して買う意志があることを示した。老爺はニコニコしながら手をこすり合わせていた。剣太がためしに五百元出して見せると、老爺は急に不機嫌な顔になり、壷を袋に戻そうとした。あわててもう五百元出して見せると、老爺はちょっと思いとどまったような振りをして、再び壷を袋におさめようとする。 剣太はそこで、努力して渋面をつくり、財布から出した一千元を再び財布にしまいこんで欠伸をした。そして蝿を追い払うようにして手で老爺を追い払うように振舞って見せた。 当時の一千元といえば、日本円にしてだいたい五万円ほどだ。公務員の給料が六十元程度だったことを考えると、一千元といえば老爺が三年や五年は楽に暮らしていける金額だった。 老爺は案外ねばらずに壷を取り出してテーブルに乗せ、そして手を出した。剣太はその手に六百元握らせた。老爺がそれを数えてなにやらわけのわからないことを口走ったが、剣太はおかまいなしに老爺を部屋から追い出した。ドアの外からまだ罵声が聴こえてきたが、それもしばらくしたらおさまった。 ● それから剣太はその壷にとりつかれたのだ。 帰国してからというもの、会社を休んでは毎日図書館へ出かけ、その壷がいつどこで誰の手によって加工されたのものなのかを調べ始めた。それでも足りず、あちこちの大学へ壷を持ち込んで考古学の研究者から意見を聞いたりした。 必ず何かの画期的な発見があるはずだと確信していた。それはきっと、中国の超古代王朝の遺品に違いないとふんで、いろいろな古文書に関する文献をあたってみた。 そうしているうちに、剣太は契丹古伝{キッタンコデン}という古文書に記されている東大神族というのがそれではないかという自説を持つに至った。また、別の研究者の説によると、現在より約二万年〜五千年前に栄えたというその東大神族は、日本に王朝を置いていたのではないかと言われているのである。これを高天原{タカマ ガハラ}伝説と結び付ける考えもあるのだ。剣太は高天原伝説を追って日本中を旅した。 それで剣太はこの壷の出処が日本国内なのではないかと考えて、さまざまな収集家に壷を見せて回った。何人かの収集家の紹介でやってきたのが茨城県のある旧家だった。その旧家に残る古文書には、常世の国{トコヨノクニ}越中(富山県)に、世界の全ての文明の起源があると記されていることを聞き、それを確かめに訪れることにした。 タクシーを降りると、とたんに夏の蒸せかえる空気に包まれた。それでも都市部に比べれば相当涼しいのだが、クーラーのきいた車内から出た瞬間にはたまらない暑さだ。 あらかじめ電話でアポを取っておいたおかげで、旧家のあるじは剣太を玄関まで迎えに出てくれた。普通、あまりこころよい反応を示してくれないものだが、この旧家の反応はとても柔和だった。 門の格子戸の敷居には黄銅のレールが引かれていて、戸の開け閉めはとてもスムースだ。家を大切にするあるじの細やかな神経がうかがわれた。 座敷に通されてしばらく待っていると、まず奥方が冷茶と冷えた水羊羮を持ってきてくれた。和服が良く似合う、しっとりと落ち着いた感じの女性だ。この奥方に娘がいるとしたら、おそらく高校生ぐらいか、きっと輝くように美しいに違いない。 「じきに主人が参りますので、いましばらくお待ちください」 「は、おそれいります」 剣太は思いの外丁寧に扱われてとまどっていた。ハンカチで何度も額の汗を拭った。奥方はすぐに座敷から立ち去った。 しばらくすると、あるじがいくつかの木箱を持って現れた。 「今お見せできるのはこれだけなんです。原本は神代文字で書かれておりまして、これを第二十五代武烈天皇が当時の宿禰{スクネ} に命じて漢字に書写させたものを、私の先々々代が明治時代にかな漢字混じり文に書き換えました。これがその明治写本です」 剣太は途端に緊張して、居を正して答えた。 「は、どうも貴重なものをありがとうございます。そこでさっそくですが、この文書の中に越中が世界文明の起源だという記述があるとお聞きしてきたのですが」 興味のない部分まで長々と説明させるわけにもいかないので、取り敢えず取材目的の核心部分に触れておこうと、剣太は少しあせって話した。 剣太とは反対に、あるじはゆっくりと座し、おもむろに話し始めた。 「はい、私はこの書を壮大な創作物として楽しんでおりますので、歴史的な真偽のほどはどうかとは思いますが、越中に関する部分をいくつか説明しながらお見せしましょう」 「ありがとうございます」 剣太はメモを取りだし、それから小型カセットレコーダーの録音スイッチを入れてあるじの話に耳を傾けた。 あるじの説明は、まずこの古文書が明治時代に『皇室のタブーに触れた』ということのために隠蔽されてしまったこと、当時の当主が不敬罪で投獄されたことなどから始まった。紀記神話の内容をくつがえすような内容が含まれていたため、天皇を神の子孫として政治の中心においた当時の社会情勢では危険な書として扱われ、昭和の敗戦までずっと禁断の書として扱われてきたのだ。 剣太は、自分が丁寧な待遇を受けている意味が少し呑み込めた。いつのまにか汗は引いており、あるじの説明がとても面白いために剣太はとても熱中して話を聞いた。古文書を開いて読み進みながら、それを剣太に指し示して説明してくれる。あるじは話上手でもあるが、この古文書をかなり読み込んで研究もしているようだ。剣太には古文書の文字はうまく読取れなかったが、あるじの説明でなんとなく呑み込めた。 「それで、臼羽さんは高天原伝説と、この古文書の関連について調べたいとのことでしたね?」 ちょうどカセットレコーダーのボタンが、パチャン! と音を立てて戻り、テープ片面の残量がなくなったことを知らせた。剣太はテープを取り出して裏返しながら答えた。 「はい、富山湾には高天原が沈んでいるという説をお持ちの人がいまして」 「富山湾とは限りませんよ、この古文書によれば、その昔北陸近辺の日本海のかなり広域に渡る部分が陸地であり大異変によって海中に没したとあります。それが高天原であると解釈できる記述があります。ちょうどほら、この部分です。『天下常世の国みな泥の海となること……』とあるでしょう」 剣太はあるじが指でさしている部分とその周辺を読んでみようとしたが、これは一見して読解できるようなものではなかった。 「それからここ、『天雲に磐舟{イワフネ}浮かべ……』という記述がありますが、これは巨石を雲のように浮遊させる特殊な技術とエネルギーのようなものを思い起こさせはしませんか?」 高天原について、あるじは独自の解釈を持っていた。それは、いくつものエネルギー生成所が林立するエネルギーネットワーク都市だったのではないかという、かなりSFがかった考えだった。 超古代になにかのエネルギーが生成されて、それが生活のために使われていたのだが、その生成工場のようなものとしてピラミッドが建造されていたのだと、あるじは言った。 剣太はそのとてつもないアイデアを聞いて、目を丸めてグウとうなった。なんという想像力の豊かな人なのだろう。しかし、古文書にはピラミッドの記述があったのだ。古文書では、それは“アメトツヅヒラミツト”と記されていた。つまり、“天と地ピラミッド”というわけだ。しかも、富山県にはそれと目されるいくつかのピラミッド型の山がある。それらの山々を地図上で結んでみると、いくつかの三角形が出来上がるのだ。頂上の高低差を考えるとそれらの図形は正三角形で、全体的には四角錐をなし、この四角錐の頂上とさらに高台のピラミッド山の頂上を結ぶと、より大きな相似の四角錐となる。まさにピラミッドネットワークなのだ。 あるじは、独自に作成した地図や資料も見せてくれた。論理的整合性の面でもかなり説得力がある資料だった。現地へ調査に行った記録などもあり、ピラミッド型の山々の頂上では、一様に方位磁石が働かなくなったとまで記されている。 「これらのピラミッドネットワークを単純に幾何学的に分析してみると、高天原の中心つまり首都である“天の真名井”は、ずばりここだということになります」 あるじが指さした地図上の位置というのは、丹後半島の先の方と能登半島の付け根のあたりを結んだ線の、だいたい中間の海上だった。そこに立山クラスの高い峰があり、ピラミッド型の山が林立していたはずだと、あるじは言った。 すでに剣太は、話に相槌をうつことさえ忘れていた。ゴクリとツバを飲み込みながら、地図をにらんだ。 「そこで、秀真伝{ホツマツタエ}という古文書によるとですね、臼羽さんの調べられた契丹古伝の東大神族に通じるような部分もあるんですよ。丹後半島にはトヨケカミが眠っていると言われています」 剣太は、この人の突飛な着想には絶対かなわないと思った。そしてあるじを心から尊敬した。真偽のほどはもうどうでも良かった。なんとスケールの大きな空想なのだろうか。それだけでも賞賛に値する。剣太が独自に築いた説など、この説の前ではまったく霞んでしまう。それでも信憑性という面では、自分の説の方が説得力があるぞと、剣太は自分に言い聞かせた。高天原は中国の超古代王朝の都でなければならない、そうでなければこの壷を中国で手に入れたということの説明がつかないではないか。 「突拍子もないことを言うやつだとお思いでしょう」 あるじは苦笑いしながら剣太の顔をのぞき込んだ。 「い、いえ、そんな……」 「はっはっは! いいんですよ、そんな。私だってこんなこと本気で信じてはいませんけど、でも夢があって楽しいじゃないですか」 「はい、すごい壮大な空想で、あ、いや論説で」 「わははは、空想ですよ空想! それでいいんです。そんな何万年も昔のことなんて誰にもわからないんですから、こうやって空想を楽しむのが一番なんです」 「は、はい……」 剣太はどこかに隠れたくなってきた。 しかし、気を取り直して、壷についてあるじの意見を聞いてみようと考えた。 「この壷なんですが」 剣太が象牙質のその壷を取り出すと、とたんにあるじの目がキラキラ輝きはじめた。 「それは、どこで手に入れたものですか?」 「ああ、中国なんです。徐州という町で、得体の知れない老爺から無理やり買わされたんですが、あんまり興味深いものですからこいつの出処を探ってみようと思い、それで取り憑かれたようになってしまいまして。古文書について取材にうかがったのも、もとはといえばこいつのせいでして」 剣太は照れ笑いしながらあるじに壷を手渡した。 あるじはしげしげとそれをながめて言った。 「これは、加工品ではありませんな。もともとこういう模様なんだ。こういう模様の骨を持った生き物の体の一部でしょう」 あるじは一目見ただけで剣太と同じ考えを述べた。 「そ、そうそう、そうなんですよ! 私もそうだと思い、これが古代東大神族の王家の者の遺骨なんじゃないかと」 「そうだとしたら、これはすごい代物ですよ」 そう言ったまま、あるじは黙り込んでしまった。壷をあちらこちらとひっくり回してみては、ためつすがめつながめている。 沈黙のまま一時間近く経った。外は黄昏がかった帳におおわれはじめていた。座敷へ入り込んでくる風も、かなり冷たくなってきた。 「ところで、臼羽さん」 「は?」 「この壷をお譲りいただくわけには参りませんか?」 「え? これをですか?」 「はい、無理を承知でお願いします、このとおり」 あるじは畳に額をこすりつけた。 「そ、そんな、頭を上げてください。あなたには本当に感謝していますが、いくらなんでもこれだけは」 「二億、でいかがでしょう」 「え……」 「だめですか、やはり」 剣太は考え込んだ。仕事をやめてしまってからもう三年近く経つのだ。道楽のために貯蓄をほとんど使い果たし、子供達の学費さえ乏しい。そればかりか家族の生活自体、妻のパートだけでいつまでやっていけるかわからない状態なのだ。 壷の出処さえわかれば、もうこんな道楽はやめてまた働くつもりだった。だが、二億あれば家族の暮らしも保証されるし、なにより自分の研究を続けることができるではないか。 剣太は迷った。 ● 結局、剣太は壷をその旧家のあるじに二億で譲ったのだった。そのかわりにあるじが独自に作成した資料の全てをコピーさせてもらった。 壷の代金の一部を自分の研究費用とし、残りを家族に渡して剣太は旅だったのだった。 壷に出会ってからまる三年研究に費やし、あげくに十二年もの間、家族の元を離れて旅を続けていた剣太は、この北陸の海岸で白骨の壷を見つけた今、もう家族の元へは帰れないことを覚悟していた。 長女はもう、お嫁にいったのだろうか、長男は大学に入れただろうか、いや、もう思うまい。自分はただ恨まれているだけのはずだ。こんなものにとりつかれて家族を捨てた男のことなど、誰が待っているものか。 しかしもういい、何もかもが終わった。妻や子のところに帰りたい。明日、十二年ぶりのわが家に帰ろう。たとえ受け入れてくれなくともいい。父が人生を棒にふって捜し求めたものがここにあるということを伝えに行くだけでいいのだ。剣太はそう自分に言い聞かせた。 剣太はそれを持って旅館に戻った。 風呂に入り浴衣に着替えてビールを飲みながら白骨と壷をながめる。旅館のまかない婦達は気持ち悪がって嫌な顔をしていたが、そんなことはおかまいなしだ。 昨日まで毎晩、ため込んだ資料を何回も繰りなおしては調べものにばかり熱中していたことがうそのようだ。もう古い文献も地理学書もみんないらない。自説を発表する気もなかった。この白骨が自説を裏付ける証拠だとして発表するのは簡単だが、剣太の説とこの白骨との関連を裏付ける証拠などどこにもないのだ。全く関係ない未知の動物の白骨かもしれない。生物学的にはそれでも十分価値はあるが、剣太は考古学にとりつかれているのだ。しかもプロではない、単なる道楽なのだ。 剣太は白骨が見つかっただけで満足だと自分に言い聞かせるために、次々とビールをあおった。 今日発見した白骨は、調べればわかることだがどう見たって死後一〜二年しか経っていない。 超古代王朝を支配していた一族の生き残りが、何かの必要性から背骨に突然変異を起こして、背中に壷を背負うようになったのがこの白骨だとすれば、現在でもその末裔がどこかで生きていることになる。そうすると剣太のこれまでの説もかなり変更を加えなくてはならない、おまけに発見場所は福井県だ。なにをどういじくったって剣太の説は矛盾だらけになってしまうのだ。 旅館で数日を過ごすうち、家に帰ろうという決心はだんだん薄らいできた。そればかりか、自説の論理的整合性などもうどうでも良くなってきて、自分の目でその壷を背負った小人の生態を確かめたいという欲求がふくれあがってきたのだ。 悶々と悩んでビールに溺れる日が続いた。さすがに昼は飲まなかったが、日が沈んでからは、部屋の窓からうっすら光って見える海と、資料や地図とを交互に見ながら、この海のどこかに巨大洞窟があるはずなんだと、空想を働かせて夜中まで飲んでいた。 その晩も、いつものように旅館のオヤジが一升瓶をぶら下げて剣太の部屋へやってきた。 いつのまにか、剣太は旅館のオヤジと打ち解けて話すようになっていた。オヤジは剣太のことを飲み友達ぐらいに思っているのだろう。おそらく話を合わせるためなのだろうが、剣太の研究に興味津々といった顔をしながら毎晩部屋へやってくるのだ。 おそらくオヤジにはちんぷんかんぷんなのだとわかっていながら、感慨深げにうなずかれたりするのが気持ち良くて、剣太は毎晩熱弁をふるっていた。他人から見ればきちがいじみた夢物語で、話として聞く分には面白いのだろう。そのオヤジがその晩おかしなことを言い始めた。 「だんな、前から気になって話そうかどうか迷ってたんだが」 「え? なにか知ってるのか?」 「いや、そんな洞窟とかそういうもんとはきっと関係ないと思うんだが、この沖にピラミッドが沈んでるってもっぱらの噂なんだ」 「ピラミッド?」 「ああ、そりゃ昔っからあったんだろうが、最近この辺の漁師が魚探で見つけてね」 「ちょっと、それを詳しく聞かせてくれ」 剣太は急に酔いが醒めてきた。まるであの旧家の主の説と示し合せたように符合するではないか。もしもそれが人の手で造られた建造物だったとしたら、中が古代人の棲みかになっていたっておかしくない。 「へい、そいつぁそれほどでかくはないんだが、あんまりキレイにピラミッドの形をしてるもんだから不思議でねぇ。潮のかげんかなんか知らないが、自然てやつは不思議なもんをつくっちまうもんだよねぇ」 「ピラミッドまで潜っていった人はいないのかね?」 「う〜ん、八十メーターくらいあるかんねえ。そんな金にならねえことするやつぁいねえ」 「明日、船を一パイ借りられないかな」 「ああ、いいよ、近所の漁師に頼んでおっからさ」 「頼む」 その夜は二人とも早めに切り上げて寝た。 次の日、剣太は地元の漁師と共に海底探査のため沖へ出ていた。 「だんな、これでさぁ」 ポイントを中心に何度も往復しながら魚群探知機に記録させたいくつかの線は、ポイントのところで間違いなく三角や台形の海底面を表している。 「かわった瀬だよねぇ、まるでピラミッドだよ。まぁこんなちっちゃい瀬がピラミッドってことないだろうけど」 「水深はどれくらいですか?」 「へい、八十メートルってとこですかね」 「この場所へもう一度来れるかな」 「そりゃまかせといて下さい、漁師ってのはそれが出来なきゃ喰って行けねぇもんですぜ」 「こんな、なにもない海原でわかるのかい?」 「ちゃんと山をためてまさぁ、山が見えなくとも今まで動いた軌跡を全部憶えてますぜ」 「方角もかい?」 「羅針盤もずっと見てきてるし、潮と風の気色からも判断できるもんでさぁね」 「そんなもんかねぇ……」 自分が不可能だと信じていたことを漁師がこうもあっさり日常でやってのけていたことを知った剣太は、ことがそう難しいものではないことを確信していた。 ● 数日後、剣太は潜水の準備をして再びその海域に向かった。天気もいい、風もない、潮もいい、こんな絶好の潜水日和に漁師はどういう訳かとても心配してばかりいる。 「旦那、無理したらいけませんぜ、危ないと思ったらまたやり直せばいいんですから、あがるときには減圧を忘れずに……」 「わかった、わかったってば、もう何回目だろうね、それ聞くのは」 漁師の言葉を遮って半分笑いながら剣太は答えた。心配症な漁師など聞いたことがない。 「私がもし戻らなかったら、旅館に残してきた白骨をオヤジさんに上げると言ってくれ。背中の壷を取り外して売れば、億の金になるんだ」 「お、おく?」 「ああ、億だよ」 漁師は複雑な表情をしながら剣太の顔をながめた。きちがい博士のたわごとにしか、聞こえていないのかもしれない。 エントリーして、各器具を船上から渡してもらい、フットファーストで潜水を始める。水中モーターを抱えて直立したままゆっくりゆっくり沈んでゆく。だんだん光が届かなくなる。 三十メートルを過ぎた。海の青さなど微塵もなく、白い小さなプランクトンが限りなくもろもろと漂っている。下を見てもまだ何も見えない。暗い死の淵が口を開けて待っているだけである。船から海底へ下ろされたアンカーロープだけが心の拠り所となる。 八ミリのウエットスーツは水圧で二ミリほどになって肌に吸いつく。水の冷たさが直接肌に感じられる。寒い。もうほとんど光は届かなくなっていた。腕にくくりつけた小さいライトで下を照らす。海底らしきものが見えはじめた。もやもやとしてそれは途轍もなく大きな怪物の体の一部のようにも見える。視界が曖昧で、ちゃんと見えるのはほんの一メートルさきほどだけだ。 足先がアンカーにふれる。そしてロープを数回ガンガンと引っ張って到着を海上へ知らせると、キンキンという金属音が返ってきた。 呼吸を整えてから水中モーターの操作にかかる。突端にはハロゲンのサーチライトが装着され、バッテリーは小型だが、長時間の使用が可能だ。タンクは二百気圧十四リッターが二本。一本はサブで、水中モーターに固定してある。 太陽光はほとんど届いていない。白黒の古いテレビのように頼りないが、海底の細かい砂利はかろうじて見える。見上げれば、海面全体が小さな楕円形に収束してぼんやりと見える。 見回すと、一部分だけが異様に暗く、まるでどこかよその宇宙へ通じる入り口みたいな感じがする。それは、ピラミッドが作っている巨大な影だった。言いようのない畏怖感が剣太の後頭部から背中のあたりを支配した。 漁師はちっちゃいと言うが、おそらく三階建てのビルぐらいの大きさはある。しかも、まず間違いなく頂上の一部分に過ぎない。本体はほとんど埋もれているはずだ。その巨大な影へと、剣太は近付いていった。 ハロゲンライトと水中モーターのスイッチを入れて、進み出した。近付くほど自分の体が闇に呑み込まれていく。ライトで照らす部分以外はなんにも見えなくなってしまった。 と、突然目の前に石垣が現れた。日本古来の石垣と似ているが、少し違う。独特な組み方だった。配列の基本が全て三角形なのだ。どう考えてもこれは人工の建造物だ。石垣の表面には海藻もなにもついていない。この深さになると太陽光が不足するので海藻は繁殖しないのだ。 石垣に沿って大きな円を描くように、そして上下しながらピラミッドの回りを一周した。剣太は、圧力と窒素酔いのために活動の鈍くなった脳を必死で回転させて考えた。 〈元々ここは……地上だったのかもしれない……〉 独白は泡となって膨張しながら海上へ向かって上昇し、すぐに見えなくなる。かなりリラックスしてきた。ただ、このピラミッド自体が一つの意志を持った生き物であるかのように感じてしまう畏怖心は萎えない。相変わらず背中がゾクゾクしている。 タンクからレギュを通して流れてくる空気は九気圧だ、まとわりつくように喉を過ぎて行く。口の回りだけ皮膚が剥き出しになっていて、プランクトンのモロモロが気持ち悪い。口の中が渇く。 海底の水温は五〜六度ぐらいか。頭蓋の中まで冷えてきて、氷を食べたときのような軽い頭痛が起こる。時々ウェットスーツの隙間から入り込んでくる水は肌を刺すようだ。石垣に沿って何周も回るうちにだいたいの大きさがわかってきた。この壁のどこかに入口があるはずなのだ。 何周目かに、剣太はやっとそれを見つけた。 大きなお化けがぽっかりと口を開けて待っている。足を踏み入れたとたんに閉じて喰われそうな気がする。それはおそらく下の方に向かって斜めに伸びている穴のはずだ。しばらくの間迷ったが、決心して入ってみる。 穴は想像したとおりで、結構広いがかなり長い。入口付近はキレイに四角く組み上げられているが、奥へ入るにしたがって岩を掘削しただけのトンネルのようになってきた。複雑に曲がりくねる穴の岩壁に水中モーターをぶつけないよう、慎重に進んだ。モーターのうなる音だけが延々続く。かなり深く潜ったはずだ。すでに深度計の針は百メートルのあたりを指している。そのうち穴は上向きに曲がり始めた。 運転に慣れてきた剣太は、水中モーターのパワーをいっぱいにして調子良く滑べるように岩石の壁をくぐって進んだ。何か、光が見えてきた。街灯に群がる虫のように、本能的にそれを求め、全速力で光の方へ向かった。 光にたどり着くと同時に、水面に出てしまった。勢い余って機材ごと海底の陸地にまで飛び上がってしまった。ハロゲンのライトは無惨に砕け、スクリューが空回りして唸りを上げる。あわててスイッチを切る。サブのタンクがショックで爆発しなくて良かった。だが、これで光源は手持ちの小さなライトだけになってしまった。 マスクをはずして、背中のタンクを下ろした。レギュを口から離して息を吸ってみる。ちゃんと空気があった。 あたりを見回す。洞窟内は信じられないことに昼間のように明るかった。地面は平たくならされていた。壁も天井も人の手が加えられているらしく、あたりは入り組んだ迷路の一部のようだ。 あちこちから小人が現れて近付いて来るのが見えた。 〈いた!〉 剣太は小躍りして喜んだ。発見はそれだけではなかった。この異常な明るさの光源が彼等自身なのだ。心臓の鼓動がひどく速くなってきた。頚動脈が節足動物のようにあばれている。アドレナリンが異常に分泌しているようだ。その場でうずくまった。吐き気がしてきた。自分の体が制御を失って全ての生理的営みが暴走している。腕がしびれてきた。足がふるえ出した。失禁していた。ウェットスーツの股間のあたりから足にかけて不快な温かさが伝わっていく。剣太はそのまま気を失った。 どれくらい時間が経ったのだろうか、剣太が目を覚ましたときにはおびただしい数の小人達が回りを取り巻いていた。 「う、うわ、うわーー!」 剣太は突然恐怖感を覚えて走り出した。小人達も驚いてワラワラと蜘蛛の子を散らすように離れていった。剣太はウェットスーツの股間をグジュグジュと鳴らしながら走った。ひどい幻想が剣太を追いかけてきた。壷が、小人が、白骨が、地底人が、古代アジア王朝の王の眷属が。 王の眷属。剣太は突然冷静に戻って立ち止まった。小人達はもしかしたら高い知能を持っているかもしれない。海で溺れて海岸で白骨になるということは、すでに地上への行き来があるということだ。日本語をしゃべれるかもしれないではないか。言葉が通じるかもしれない、それだけの希望が剣太をおそろしく冷静にさせた。 剣太は振り返って小人達の方へ歩み寄ろうとした。小人達は物陰から剣太の様子をうかがっていて、近寄ると素早く逃げてしまう。剣太は気を取り直して深呼吸してみた。 こんなに広くて明るくてしかも空気があるのだ。小人達との接触は後回しにして、中を探検だ。歩き出した剣太を、何人かの小人がつかず離れず追ってきていた。ちょうど明りのかわりで便利なのでそのままにさせておく。 迷路は小さな広場や通路でできていて、相当な規模だ。歩くうちに同じような光景に何度もでくわすが、それは微妙に違っている。ある通路にさしかかったときに、植物の茎らしきものを見つけた。それをたどって行くと、段々茎は枝のようになり、そして葉を付けた部分が現れ、さらに進んで見ると、枝のあちこちにボタンに似た花や、見たこともない果実がついていた。この植物が酸素の供給元であり、食料源なのだろう。小人達の光によって光合成が行われているというわけだ。 剣太に対する好奇心を抑制しきれないのか、何人かの小人が寄ってきた。剣太は手をさし伸べて 「おいで」 と、声をかけてみた。 「チュチュ……、キー!」 小人が鼠のような声を発した。突然剣太は相手が鼠に見えてきて気持ち悪くなった。さし伸べた手を思わず引っ込めてしまった。やっぱり小人の観察は後回しにしよう。剣太はそう考えて洞窟探検を再開した。植物の茎はどこまでも長く、いったいその根がどこにあるのか全く想像もつかない。 花を調べてみると、花粉がない。どうやって交配するのだろうか。もしかすると、小人達は地上に花の花粉を求めてときどき上陸しているのではないだろうか。そのせいで遭難者が出るのだ。先日見つけた白骨がまさにそれなのだ。 小人達の背中の壷は陸上から花をもって帰るための入れ物であると同時に海中でエアータンクの役目も持つようになっているのだ。 植物の枝に沿って奥へと探検を続ける。迷路のように沢山の穴が入り組んでいる。それに合わせて植物の枝もウネウネと曲がりくねっている。食虫植物の食指みたいで気味が悪い。 小人達が存在しないところは、行っても意味がないし暗くて見えないので、光の届く場所を全部見て回るつもりで歩き続けた。一〜二日あれば全体を見て回れそうだ。明日は大きめの手提げライトを持ってきて暗い部分も見て回ろう。臆病な小人達を横目で見ながら彼は横になり、少しだけ休憩した。 しばらくして再び探検を開始した。黒い岩肌はコークスを思わせる。触るとどこかジトっとした感じがする。 異様に明るい横穴を見つけて入ると、そこには小さな地底湖があった。地底湖の水は、光っていた。 おそるおそる顔を近付けて見ると、光る水は素晴らしい透明度を保っており、かなり深いところまでぼんやりと見える。手ですくって飲んでみた。手を突っ込んでできた波紋は光の輪となって静かに広がっていく。毒性の強い鉱物が溶け込んでいたとしたら即死だ。しかし、剣太にはこの水が小人達の生活水であるように思えてしかたなかった。いや、それは確信だった。 光る水には塩辛さはなく、ほんの少し甘さを感じる。ミネラルをたくさん含んだ美味しい水は少し甘いのだ。 横穴を出て、奥へ奥へと進む剣太の後を、こそこそと小人達がついてくる。奥は一層強い光に包まれていた。真昼の太陽と変わらないほどの明るさだ。その最も強い光の源を目指して歩いて行くと、かなり広い広場に出た。 広場はドーム状で、真中に根を据えた大木が天井に枝をへばりつかせて蔦のように広がっている。その蔦のような枝の先々にボタンと似た葉がつき、花が咲いているのだ。入口の近くで見た花も全てここから延びた枝につながっている。 大木の周りには七人のコロコロに太った小人が輪を描いて外向きに座っている。じっとして動かない。七人の方から、しわがれた声が聴こえてくる。 『愚かな人間め、とうとうここを見付けてやって来たか』 剣太は少しだけ驚いた。そして、小人が単なる鼠程度の知能しかないような生き物ではないとわかって、無性にうれしくなってきた。 『驚くことはない。我らは言葉を使って話しかけているわけではない。我らが発した信号をお前が自分で言葉に変換しているだけだ』 ますます驚いた、考えていることまで見透かされている。 『人間よ、人間がこれを発見してはいけない、人間には使いこなせる代物ではないのだ……』 〈これ? これってなんなんだ。人間には使いこなせないとは……〉 剣太の疑問に対しての答なのか、突然おびただしいイメージが頭の中へ流れ込んできた。 ここに満ちている光は生体プラズマだ。地上の人間でこの光を関知できる者は少ない。このピラミッドの中に蓄えられている重力子に反応して、体の中の成分が常温プラズマとなって放出される。そのせいで小人達は光るのだ。 地底湖の水に含まれている光る成分が、生体プラズマの元になっているようだ。 ピラミッドは重力子を集めて蓄えておくための施設なのだ。重力子は人間が使っている電気のような使い方をすることができる。この植物は重力子を超伝導状態で取り込んでしまう媒質で、加工して使えば巨大な岩石なども一時的に地球の重力波と相殺する逆位相の重力波を帯びるようになる。その他の特殊な媒質と反応させればさまざまな使い方ができる。 剣太にはよくわからなかったが、イメージだけはしっかりとつかむことができた。それは画期的なエネルギーではないか、平和利用できたならどれほど人類が助かるか、想像もつかないくらいだ。だが悪用されればそれはおそろしい結果を招くだろう、それだって想像もつかない。だがしっかりした管理者がこれを管理すれば悪用されたりはしないに違いない。 このとき剣太はよこしまな考えを持った。胃の後ろのあたりからドクドクと名誉欲が沸き上がってきた。胸をときめかせた。頭をのぼせさせた。 こいつらを地上へ連れて帰って話を聞けば、もっともっとたくさんの謎が解け、そして剣太の学説も完全なものになる。そしてそれは日本にとって国家的な大発見であり、古代史を覆すことにもなるのだ。そのうえ物理学の分野でも画期的な大発見となるだろう。悪用を防ぐ手だてなどないに等しいという考えを、剣太は完全に除外してしまった。 『我らを連れて上がることはできぬ』 また声が聴こえる。しかし、剣太はそれを単なるこけ脅しだと思った。 だが実に、この七人の絶大な重力制御が天井の岩盤を支えていた。七人の中の誰か一人でも欠ければ、ピラミッドは崩壊し、地下洞窟も全て埋もれてしまう。 だが、そんなことはすでに眼中にない、剣太は小人達に近寄って行く。 あと数メートルのところまで近寄った時、剣太の体は見えない力に跳ね飛ばされて広場の壁に激突した。 「ぐぎゃん……」 激突の瞬間、剣太は子犬のような悲鳴を上げた。しばらく動けなかった。気を取り直して再び近寄ろうとすると、小人のうちの一人が、手のひらをかざすようなそぶりを見せる。またもや剣太は跳ね飛ばされた。 剣太が何度か跳ね飛ばされるうちに、小人達は急激に疲労したらしく、その衝撃は段々と弱まった。七人ともほんのしばらくのうちに見違えるほど痩せこけてしまっていた。 フラフラになりながらもスキをついて近付いた剣太は、七人のうちの一人をつかまえた。そのまま小脇に抱えて走り出した。肺に貯めた圧縮空気を少しずつ放出しながら泳いで行けば海上に出られる。九気圧の空気を肺に貯めるのだから海上まで泳いで行くだけの酸素は十分摂取できるはずだ。抱えた小人も、背中の壺があるから死ぬ心配はない。 しかし剣太の考えは甘かった。 『愚かな、何と愚かな……』 抱きかかえた小人のつぶやきが聞こえたかのように思えた。 「なんだって?」 ゴゴゴゴゴゴゴ。 全身が耳になってしまったみたいに、体中で地鳴りを聞いた。 天井はまっぷたつに割れ、大きな地震が起こり、巨大な岩石が落ちてくる。小人達は次々に押しつぶされて死んでいく。滝のように海水がなだれ込んでくる。剣太は思いも寄らぬ出来事に真っ青になった。 抱えていた小人を放り出し、揺れの中で這うようにして逃げた。次々と降ってくる岩石を避けながらとにかく元来た穴へ向かい、何とか岩につぶされずに海中へ飛び込むことが出来た。 必死で泳いだ。しかしすぐに彼は、それが徒労であることを知った。 穴の途中の細い通路がつぶれてふさがっていたのだ。行き止まりの壁でしたたかに頭を打ち、一瞬目から火花が出た。 地底湖で飲んだ水のせいで、剣太の体は弱い光を発していた。そのため、目の前の穴が完全にふさがっていることが見て取れた。 とって戻そうと振り返った瞬間、入口の方から差し込んでいた僅かな光が完全に遮られるのが見えた。穴の入口に大岩が乗ったのだろう。絶望的な暗闇の中で剣太は全てを悟った。自らの愚行がこの事態を招いたのだと知ったが、もういくら悔やんでも悔やみ切れないのだ。 古代史以前の貴重な種族の生き残りを絶滅させてしまった上に、数々の発見を全て無に帰してしまった。薄れ行く意識の中で、彼の脳裏には妻や子供達の顔が浮かんで、そして消えた。 海上で剣太の帰りを待っていた漁師は、深いみどり色の海底から巨大な青白いものが凄い速さで浮上して来るのを見て取り、あわててアンカーロープを投げ出してその場を離れた。 エンジンを全開にして逃げる漁師の後方で巨大な水柱が上がった。海面は山のように盛り上り、真っ白な柱が何百頭もの龍のように空へ向かって伸びていった。そして風が、まるで地球の裏側から大地を突き破って飛び出したような風が、海中から上空へ向かってすごい早さで吹抜け、螺旋状の飛沫を残した。 振り返ってそれを見ていた漁師は、一生忘れることができないような光景を眼に焼き付けていた。恐ろしさのあまり全身がブルブルとふるえて止まらなかった。 しばらく漁師の頭上は真っ暗になり、スコールのような水しぶきが降り注いだ。目の中に潮水が入っても、漁師は目を丸く見開いたまま動けなかった。 水柱のおさまったあとから、今度は大波が船を追っかけてきた。後ろから大波を受けたら船は船首を水中に突っ込んで沈んでしまう。漁師は突然我に返り、百八十度旋回して船首を波が来る方へ向け、エンジンの回転を半分ほどに落し、波に対して少し斜めになるように舳先を当てた。 まるで山登りでもするかのように、船は大波の上へ駆け上がり、そしてまた駆け下りる。何度か上がり下りを繰り返すうちに大波は去った。 その後、漁師はアンカーロープをさがして再び船を着け、剣太が浮上して来るのを待った。 あくる朝までずっとそこで待ち続けて、まわりの海域をずっと見渡していたが、ついに人影らしいものを発見することはできなかった。 漁師は、海底から浮いてきて海一面に広がったボタンの花を、なんとも言えない気持ちでながめていた。 ニュースでは、海底火山の噴火だと伝えられはしたが、洞窟内の空気が一度に海中に放出されたための現象だと知るのは、その漁師だけだった。漁師は旅館のオヤジにだけそのことを話した。 旅館のオヤジは、漁師から剣太の死を知らされ、海底ピラミッドのことを剣太に話さなければ良かったと深く悔いた。 誰もが噴火だと信じていたので、再噴火の危険があるとしてそこへ捜索に入る者はなく、剣太の亡骸が上がることもなかった。 旅館のオヤジは、剣太が大事そうに持っていた小人の白骨を寺におさめ、墓を立てて丁寧に供養を行った。それが、剣太への供養にもなると思ったのだ。剣太の家族の所在については聞かされていなかったので、連絡のしようもなかった。それで、墓標には剣太の名前を刻んだ。 |
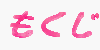
|
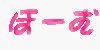
|