−荒天日記 7−
Copyright (C) s-maru 1996
1993年2月2日 今年はよく荒れる。2月に入って雪も良く降る。 よく荒れて雪がたくさん降る年、全然荒れず雪もまばらな年、どでかい時化 があったりドカ雪が降ったりする年、荒れないけど雪だけ降る年。天候という のはだいたい過去と似たようなパターンを繰り返す。 パターンの繰り返しはなんだか周期性を持っていて、漁師はたいてい秋のう ちに冬の荒れ具合を予測して仕事の段取りをたてる。4月から11月中頃まで が漁労期間である大敷網などは、9〜10月の間に冬の天候と冬の回遊魚が豊 漁か不漁かを予測して、何月まで操業するかを判断する。だから、10月いっ ぱいで網を切り上げてしまう年もあれば、暮れまで操業する年もある。 同じように冬の間に春の予測をたてて、4月に入ってから用意にかかるのか 3月半ばから用意にかかるのかを決める。天候や豊漁・不漁の周期性というの は、漁師の生活とは切っても切れない関係にある。 ここで面白いのは、天候の周期と豊漁・不漁の周期とがよく似ているとい うことだ。 漁師が秋のうちに冬の天候のパターンを予測するのによく使われるジンクス で代表的なものが一つある。それは、 「樽イカが10月初旬からたくさんとれる年は冬よく荒れる」 というものだ。 逆に天候から魚のとれ具合を予測する代表的なジンクスは、春から夏にかけ てだが、 「藤の花がたくさん咲くと、あおりイカがたくさんとれる」 というものがある。 つまり、藤の花がたくさん咲くような条件の天候だと、あおりイカがたくさ んとれるということだ。 もちろん、天候→魚、魚→天候の予測だけに限らず、天候→天候、魚→魚と いう予測のしかたもする。村の年寄りの予測というのは不思議にもたいていよ く当り、ジンクスというのがどう考えても「そんなもん何が関係あるんじゃ」 と疑わずにおれないようなデタラメなものなのだ。 「秋に烏が田圃で水浴びした年は暖冬になる」 「冬の曇り空で、西の方だけが黄色くなって良く冴えている日のあくる日から 時化る→(それに付随して)冬に限らず、八幡崎{はちまんざき:村にある、 海岸線に飛び出した巨大な岩山で、八幡様を祭ってある}の上の丘にあるお地 蔵さんのほこらに西日が当ると次の日大荒れになる」 「かまきりが敦賀半島へ向かって飛んで行くと大潮が来る(??)」 「さいしょうフグ(地元ではサバフグと呼んでいる)が春にたくさん入る年は、 夏にハマチが大漁になる」 「かわはぎの多い年は『鰤・鯖』などの青物が少ない」 「冬興しの雷がなると鰤が回遊してくる」 「初物の形が良ければまとまった漁獲が期待できる=ハマチなどが良く肥えて いて肌がツヤツヤしているとか、鯛の色が奇麗だとか、平目が分厚いなど」 「くらげが多いと子鯖が多い」 などなど、数え上げたらきりがないほどたくさんのジンクスがまことしやか にささやかれては、漁師達は来るべき大漁・不漁、大時化・暖冬などに備える わけだ。作り酒屋への出稼ぎに出る時期もこれで決めて、蔵元の方へ事前に連 絡しておく。 周期性の把握と予測、これが毎日の漁師の日課でもある。 朝の漁から戻って魚を選別しているときにも、その日その日の魚の形を値踏 みする。浜で仕事しているときは沖を眺めては明日の風を予測する。それらの 毎日のデータから中期的長期的予測をたてるのだ。 |
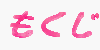
|
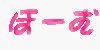
|