【晴れ ところにより二羽カモメ】
Copyright (C) by s-maru 1998
|
13.岩壁の母
越前の海岸線は、鋸の歯みたいに岩山の岬が突き出しているが、その入り江の方は谷川がそそぐ扇状地である。集落は扇状地ごとにぽつりぽつりと発生した。 25年ほど前に、海岸沿いに国道305号線が通った。それ以前は、海岸線の道といったら、各集落ごとの孤立した小道だけだったのだ。オラが今住んでいる一つの地区も、当時は6つぐらいの集落に分かれていて、海岸には連結道がなかった。今なら2分間ほどで行き来できる隣の集落まで、当時は何時間かかけて、背後の山を越えなければならなかった。 村には、江戸時代から受け継がれる家柄の、国家資格を持つ医師がいて、村人の診療にあたっていた。薬剤調合の免許もあり、作れる薬は薬草で手作りして補っていたようだ。 オラの家からは、先生の家がある隣の集落まで、山を一つ越えなければならなかった。当時2才のオラが熱を出すと、母は海岸線を走った。海岸線からだと数分で行けるからだ。 だが、途中にはけわしい岩山が海に突き出していたのだ。巨大な岩の壁にへばりついて進む母の背中から逆巻く日本海を見下ろし、うわごとを言っていた記憶がある。 絶壁というわけではない。ある程度の足場はある。それでも、もし足をすべらせたら、岩場の海へ真っ逆さまなのだ。 オラが小学校に上がる頃、国道305号線が整備され、海岸はアスファルト道とコンクリートの堤防になった。岩山は一部削られ、残りは港の防波堤になった。国道8号線も開通し、武生市の病院へ車で通えるようになった。 村人は、ごくたまにしか先生のところへ診察に行かなくなった。 先生は、あんまり出歩かなかったので、村人にとって段々なじみの薄い存在となっていった。 それでも、庭の薬草畑は常に手入れされていた。 学校へ通う道すがら、堤防の上を歩いたり、先生の家のまわりの石垣の上を歩いた。子供の頃って、それだけのことがとてもスリリングで、なんだかワクワクしたのだ。 石垣の上から先生の家の中が見えた。先生はいつも、机の上で分厚い本を広げていた。本棚にはそういう分厚い本がびっしり並んでいた。 薬草畑も見えた。チューリップに似た大きな花があった。芥子の花だ。本当に、不思議な花だった。他では見たことがないからかもしれないが、花というよりも、生き物という雰囲気が強いように感じた。今にも動き出しそうな感じなのだ。食虫植物みたいにも見えた。 数年後に先生が亡くなった。それで、先祖代々受け継がれた薬草畑は撤去された。芥子の花は、もう見れなくなった。 |
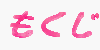
|
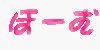
|