【晴れ ところにより二羽カモメ】
Copyright (C) by s-maru 1998
|
12.死体は起きあがるもの
オラの村は、各集落に火葬場がある。死者が安らかに眠る場所のことを三昧場と言うが、これが村では火葬場の意味で使われている。略され訛って「さんめぇ」と呼ばれている。昭和50年ぐらいまで、さんめぇは実際に使用されていた。オラが小学校6年生の時、父方の祖母が近所のさんめぇで荼毘に付された。白装束で棺桶を担いで丘への道を登る父とおじ達の姿が今も印象に残っている。 村には穏亡焼き{おんぼやき}と呼ばれる、火葬の番をする人がいた。焼き方がまずいと、骨まで燃えて消えてしまったり、炭のようになって骨が拾えなかったりするから、経験を受け継ぐ専門職がいたのだ。大昔には、賤民扱いされていたそうだが、少なくとも昭和の時代には専門職となっている。 火葬場というのは、簡単な屋根がしつらえてあるだけの小屋である。入ってすぐに控えの土間があり、奥に少し掘り下げた焼き場がある。 火葬の際、遺体は棺桶から出して、炭と薪を敷き詰めた上に仰向けに寝かせてくべ、ゆっくり焼く。 焼くと、筋肉の中の水分が失われるため、遺体はそりくり返ったりのたうち回ったりする。これを押さえつけておく道具があり、べら棒という。先端がへらになっていて、ちょうど大きなしゃもじを四角くしたような、はたまた船の櫂のような形をしている。 ところで、父は男4人兄弟なのだが、最年長の伯父は種違いの兄だ。祖母が19の年、結婚を反対されたために私生児として産んだのだった。3才ぐらいまでは祖母が育てたようだが、父方に引き取られた。だが正妻が嫁入りすると同時に追い出され、母の元に帰してもらえもせず、里子に出されて非常に苦労したらしい。 伯父は片腕がない。トンネル掘りをやっていたときにダイナマイトで吹っ飛ばされたそうだ。 子供の頃からさんざん過酷な労働をさせられて、成人してから村に戻ってきた。 伯父の父親が亡くなったとき、長男としての義務感から、伯父は穏亡焼きに代わって火の番を勤めた。 伯父が一人で火の番をしていると、遺体はむっくりと起きあがってきた。伯父は、 「死んでからまでも俺を苦しめるのか!」 と言って、遺体の頭をべら棒でどつき回したそうだ。 時代はさかのぼり、まだオラの父が生まれる前のこと。 オラが住んでいる集落は、元々神田別当領であり、ヤハタ八幡宮の神域とされていたため数件しか家がなかった。中でも、宮を管理する者として宮野、宮内、治部という名字を授かっている家が古く、平安時代にはすでにその姓を名乗っていたようだ。オラの父の実家は治部である。 明治末期に土地が開放されてから、近所の集落から移り住んで来るものや、よそから流れてきたものなどで人口が増え、集落が形成されていった。 常に村には素性のわからない流れ者が何人かいて、そのまま住み着く者もいればさらに流れていく者もいた。流れ者の集まりだから、流れ者には寛容で、どこの家でも適当に流れ者の面倒をみたりしていた。 ある旅人が、居候していた家でふぐを食べてあたってしまった。泊めていた家の者だけで葬式をし、火葬されることになった。 さて、炭と薪を敷いて遺体を寝かし、火をつけた。 「あちちちち!」 遺体は飛び上がって一目散に丘を駆け下りていった。 ちょうど丘の登り口にある「名左右衛門」という家に駆け込んだところ、その家の主は、 「お前は死んだ人間だから、この村にいてはいけない。人目に付かないように急いで村を離れなさい」 と言って服を着せてやり、送り出したそうだ。 さんめぇは、使われなくなってからは誰も近寄らない。そのうち朽ちて、崖崩れと一緒に海岸へと崩れていった。さんめぇが崩れて海に土が流れ込んだ年、いくつもの海難事故があった。また、その年は不漁で、ひどく海が荒れた。 別の集落では、使われなくなったさんめぇを取り壊すことになり、誰もやる者がいないので、高い給金目当てによその村からオッサンが2人やってきて実行した、数ヶ月の間に、2人とも原因不明の病気で死んだ。 また別の集落では、酒に酔った若い衆達が、連れの一人が酔いつぶれたのを良いことにさんめぇの中へ連れ込み、 「おい、家についたぞ、もう寝ろ」 と言って焼き場に寝かせたまま放置した。ちゃんと手を組ませて、仰向けに寝かせたのである。村の若い衆は、そういう冗談を平気でやってしまうのだ。 明くる朝目覚めて飛んで帰った若者は、それ以来体調を崩し、寝たり起きたりの生活をしていたが、そのうち心臓発作を起こして危うく死にかけた。一命は取り留めたものの、心臓病が持病となってしまった。 |
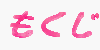
|
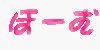
|