【晴れ ところにより二羽カモメ】
Copyright (C) by s-maru 1998
|
11.ふぐちり
ふぐが高級魚だと知ったのは、大人になってからだ。市場へ運び、売れた値段を見てぶったまげた。猫の赤ちゃんみたいなふぐが5万円もするのだ。越前産天然フグ、日本で最高のふぐなんだそうだ。でっかいやつは30万円もする。 それもこれも、道路が整備され、敦賀の市場までトラックで30分もあれば行けるようになったからだ。 国道8号線が開通する前は、交通手段といえば船だけだった。だが当時は手こぎである。そうそう敦賀まで通えるものではなかった。発動機付きの船に載せることのできる物資は限られている。だから無駄なものは一切運ばなかった。 ふぐなんて、毒があって食えないと思っていたので、ほとんど捨てていた。身だけ食べていれば大丈夫だということはわかっていたので、村人は時々晩飯のおかずにして食べていた。 子供の頃には、よくオヤジがふぐを食わしてくれた。 母が、 「今日は、おかずがなんにもねえんや、父ちゃん」 「そうか、ほんなら晩網{ばんこ}のふぐでも持って帰って食うか」 ふぐの水炊きである。鍋の真ん中にでっかい湯飲みみたいなやつを置いて、その中に醤油とネギをツルツルいっぱい入れておく。煮えたフグと白菜をそこにちょぼちょぼとつけてハフハフと食べるのだ。 最後にこの醤油を鍋の中にあけて、おじやにする。 オラは、フグばっかり食ってて飽きてたので、 「なんじゃ、またふぐか。お肉か玉子焼きが食べたいじょ、母ちゃん」 などと文句を言い、 「ばかもん、贅沢言うんじゃありません」 と叱られたものだ。 民宿では、料理を一通り出した後、母やまかないのおばちゃん達が厨房の隅の茶の間で晩飯を食べる。そこへ客の一人が宴会から抜け出して話をしに来たことがあった。どこの団体にもたいてい一人、厨房をのぞきたがる客というのがいるもんである。 ひとしきり世間話をした後、何かを思い出したらしく、おもむろに切り出してきた。 「そういえば、おカミさん、この辺じゃふぐはとれないんですかね。わたしゃ、ふぐが大好きでね、一年に一回だけ、社長が課の連中をフグ割烹屋さんへ連れてってくれるのが唯一の楽しみなんですよ。安月給じゃとても自分で食べに行ったりできませんからね。それが今年は私だけ出張が入って、ふぐが食えなかった。そりゃもう残念で残念で、ううう……」 泣き上戸なのか、そう言って泣き出すのだ。都会の人もふぐを食べるらしい。泣くほど食いたいものなのか? ふぐを? 幼かったオラは、けったいなオッサンやなぁ、と思った。 ひとしきり泣いた後、気を取り直して顔を上げ、茶の間の食卓をのぞき込みながら、 「ほう、鍋ですか、何の鍋?」 などと愛想を言う。 まかないのおばちゃんが、 「なんにもおかずがないもんだから、しょうがないんですよ。たくさんとれるけど、売れもしないし、ふぐなんて子供達が蹴っ転がして遊んでるんですよ」 などと、恥ずかしそうに答える。村では、ふぐなんか食ってるのは貧乏人ってことなのだ。皆が捨てるものを拾って来て食べているわけだから。また、ふぐは風船みたいにふくれるのでサッカーボールの代用にして遊んだ。もちろん、サッカーボールなどという高価な玩具は、村にはなかった。 客は、茶の間で一緒にふぐをつつきはじめた。最初は遠慮そうに箸をのばしていたが、 「いくらでもありますから、好きなだけ食ってください」 と、母がふぐの白身をドバドバと鍋にあけるのを見て、複雑な表情を浮かべ、半ばやけくそ気味に、憑かれたようにガツガツと食べていた。 |
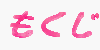
|
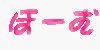
|