【晴れ ところにより二羽カモメ】
Copyright (C) by s-maru 1998
|
10.冷水塊の話
保安庁から毎年、若狭沖の水温の状況が記録された海図が送られてくる。これを見ると魚の通る道のようなものが一目でわかる。単にだだっ広いだけの海のように見えても、そこには生活道のような獣道のような、魚にしかわからない街道が、ある。これを魚道という。 日本海のいたるところには、冷水塊というものが点在している。回遊魚は、当然冷水塊を避けながら渡っている。冷水塊は、消えたり現れたりするものではない。ずっと居座っていて、わずかに移動している。特定の範囲内で行ったり来たりしているのだ。冷水塊とは、海流のよどみである。 回遊魚の「渡り」の方法なのだが、不思議なことに人間が船で「渡り」を行う航海術と、とてもよく似ている。陸地に沿って渡るか、岬から岬を渡りつないでいくか、この2種類が、基本的な航海の方法で、羅針盤や星座観測などを用いた大航海とはまた別の話である。 そして、魚は魚で、独自の「渡り」の方法がある。 鰤・鮪などの大型魚はたいてい岬を渡りつないでくる。一本釣りの漁師達が、これを直に目で見ている。大型魚は、回遊の途中で鰯の群の存在を音でキャッチして捕食しながら進むのだが、その時には必ず海面近くまで小魚を追い込むので、海面が騒がしくなる。これをわきこみという。わきこみには鳥が集まる。 コース内に小魚がいないということはまず考えられないが、捕食のために、さらに湾の中まで入り込んでくることも多い。でも、基本的なコースは岬の先端と先端をつなぐ直線に近い。 ところが、冷水塊が陸地に近づいているときは話は違う。かなり磯の方まで入り込んだコースを取る。そうなると、定置網は大漁になるのだ。 ここで読者は当然「おや?」と疑問に思われるはずだ。海中から陸地や岬が見えるはずがないのである。でも、どういうわけか回遊魚の航法は、岬の渡りつなぎか、海岸線に沿って歩くかのどちらかなのだ。 それを調べるために、水産試験場では、魚に標識をつけてみたり、場合によっては発信器を埋め込んだりして、もう100年以上も観測してデータをため込んでいる。回遊魚の生態を完全に把握することはできないから、正確なところまではわからないのだが。 回遊魚は、実際には岬や陸地を関知しているわけではなく、水温の変化にとても敏感なのだ。水温は、もちろん潮流に影響されるが、海深もすごく関係ある。等温線と等深線が相似形になる場合が多いわけだ。 寒流がよどみを作る冷水塊だって、海底の地形の影響を受けているはずだ。この冷水塊ってやつは、魚にとってはとてつもなく大きな化け物のように思えるのではないかと想像できる。 回遊魚は、温度変化に対してとる行動にもパターンがあるが、障害物に遭遇した場合の行動にもパターンがある。これを利用した漁法が定置網というわけだ。定置網は、静かに魚を待つ漁法だが、なぜか魚は袋状の魚取りまで入り込んでしまう。そういう風に網を作ってるわけなのだが。 よく、迷宮を抜けるための方法として、ずっと壁に手を触れて歩けばいつかは出口がくると言われるが、同じように、長く続く壁のような障害物に出くわすと、魚はそれに沿って進む。これはミクロな意味でのパターン。 マクロな意味では、地形に沿って回遊する魚は、水温が一定のところを進むことによって、結果的に同じことをしているわけだ。これで列島の北の端から南の端まで往復する。もしくは九州あたりからは大陸沿いにスイッチして。 前述のように、岬を渡りつなぐ回遊魚も、ある程度は湾の中へ入り込む。これには特徴があって、日本海側においては、北上する魚は素直に渡るが、南下する魚は湾にさしかかると、「の」の字の筆順を逆にしたような道を描いて渡る。太平洋側を渡る魚のことはわからないが、きっと北上するときに「の」の字を描くんじゃないかと思う。 海も宇宙規模で観察するならば、無重力の宇宙船内に浮かぶ水球と同じ。宙にぽっかり浮いた水の球の中を魚が泳いでいて、しかもそこには、棲んでいるものにしかわからないネットワークが存在するのかと思うと、なんだか不思議な気持ちになる。 自分の船で、敦賀に用事があって湾内を走るときには、よくイルカの群に遭遇する。まぁぁ、スッポンスッポンと息継ぎに飛び上がるイルカが100頭近く見えるわけで、その瞬間に海中にも100頭ぐらいいるわけで、なんだか自分の船がひどくちっぽけなものに思えてしまって、やっぱり海にはかなわねーよなーと思う。 自分の船の1万倍以上もあるフェリーとすれ違っても自分の船の方が立派だと思ってるような自信過剰の漁師なのだが。 |
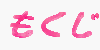
|
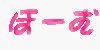
|