【晴れ ところにより二羽カモメ】
Copyright (C) by s-maru 1998
|
9.定置網四方山話
オラんとこでは新規で網を架設することを「網を建てる」と言う。 大工さんが家を建てる初日のことを「建前」って言うけど、定置網の場合は「建て込み」と言う。 昔は神主さん呼んでお祓いしたりしてたけど、今では御神酒をまくだけで、簡略化されている。 ちなみに、合繊ロープが出回る前は、大敷き網は毎年春に大量の藁を仕入れてきて、藁縄と藁網と砂俵を編む作業から始めて、同じ漁場でも毎年新規の建て込みをやっていた。 網の設計は海深に合わせてあるから、例年通りの場所に建て込まなければならない。漁労長はしっかりと山を記憶していて、山をためながら位置を決めていく。「山をためる」の「ためる」については、大工さんがカンナの刃の出具合を見るときに、目の下にカンナをくっつけて底面を見渡す、あれを「ためる」って言うよね。鋸の刃を研ぐときなんかも、持ち手を頬につけて刃渡りを見渡すけど、これも「刃をためる」って言う。そういう意味で「山をためる」って言うわけだ。 ちなみに、山が見えないような沖合へ出る場合は、帰ってくるときに最初に見える山の頂上を「女星(目星)」って言うが、オラの村ではただ単に「山が見えた」と言う。 これが転じて、どんな作業をやってるときでも、だいたい終了のめどがつくことを「山が見えた」と言う。 箱網と運動場は綿糸の網で、道網は藁網。数人がかりで藁をしめて作る縄も、藁網も、コールタールに浸けて干しておく。だから春には番屋付近がコールタールのニオイでいっぱいになった。 網のつづくろいに使われる糸は綿糸で、これもコールタールに浸けて干す。だもんで、「こーるたんひも」なんて呼んだ。現在ではスパンナイロンを使っている。 フロートは孟宗竹のたばねたやつだった。 砂俵は、近所の海岸で砂利や砂を詰めて、積み上げる。だから春には必ず海岸が俵だらけになって、たくさん積み上げられていて、まるで戦場みたいになっていた。そこで忍者部隊月光ごっこをやる。でも、俵が崩れてきて下敷きになったりしたら大変なので、こっぴどく叱らる。俵の山から山へと飛び移るのが、忍者みたいでかっこよくて、すごくうれしかった。 その時期、村では決まって大豆を挽く。どの家の軒先も、簾を広げて大豆を干してあったものだ。大豆を煎る芳ばしい香りが村中に漂うと、黄粉餅が食えるって思ってうれしかった。何か暦の節にあたるのだろう。 村で主婦連中を束ねる肝っ玉母ちゃんが、近所の若嫁達を寄せて、ぼた餅と黄粉餅を大量に作る。それを、浜で砂俵を結っている大網(大敷き網のこと)の水主(かこ:乗組員)に配る。俵で遊んでいる子供達もおこぼれに預かる。大網の水主達は、俵に尻を下ろして休憩を取る。 若嫁達は、赤い腰巻きの上に裾の短いカスリ(おしりがかくれる程度)を着て、かっぽう着をかぶり、頭には手ぬぐいをかけている。家事ではモンペをはかない。 年輩の母ちゃん達に急かされるもんだから、その格好のままわらじを突っかけて、餅を配りに来るんである。 意地の悪いとっつぁんが、 「おい、腰巻きの間にシリムカデが入ったぞ」 などと言うと、 「え? なに? どこ?」 と、パニックになって腰巻きの合わせ目をめくったりする。昔は腰巻きが肌着で、パンツなんてなかったわけで。 「そりゃ、その裏の方へ行ったぞ」 「え? え?」 さらに下の方もめくり上げてしまう。 自分の内股を覗き込んだ後、ハッとなって一同を見れば、視線が集中している。 「きゃー!」 |
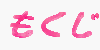
|
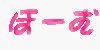
|