【晴れ ところにより二羽カモメ】
Copyright (C) by s-maru 1998
|
8.太神楽が来た
オラが子供の頃には、村に太神楽が来ると村人総出でついて歩いた。太神楽というのは獅子舞のことであるが、春と秋、特定の時期に必ず回ってくるのだ。里の方では田植えが済んだ頃と刈り入れが終わった頃。河野村では、春は大敷き網の建て込みが済んだ頃。秋は切り上げの少し前になる。 ろくな道路がなかった時代のことだから、旅の一座は隣村を明け方に出発して、馬に荷物を乗せ、歩いてやってくる。曲がりくねった山道を、野を越え山越え、狼に襲われないように刀を振りながらやってくる。宮崎村の各在所〜武生市白山町(旧白山村)の各在所〜河野村の各集落、という順で、何日もかけて回る。宮崎村や白山は米どころだ。 山本源太夫と石川宗太夫という伝統芸能一座があり、世襲制で曲芸を伝承している。春には石川、秋には山本の一座がやってきた。 獅子舞は、各家一軒ごとに祓いの舞いを披露する。当時の相場では、礼金は500円ぐらいで、約10分間舞う。礼金をたくさん出した家の前では、延々30分くらい舞い、傘回しの芸も披露する。 村人は太神楽のことを「でえかんぐら」と呼んだ。 「ピーヨーロ……」 という笛の音を聞きつけた村人が一軒目の家の前に集まる。村が騒がしいので、他の村人も出歩き始める。 「なんじゃ、なんじゃ」 「でえかんぐらや、でえかんぐらが来たぞ!」 「おー、でえかんぐらか!」 狭い砂利道は、村人でわき返る。所帯の良い家の前に来ると、みんながワクワクして目をきらきら輝かす。礼金がたんまり出れば芸が見られるからだ。子供達には飴が配られる。小さな板っきれに、柔らかくした水飴をからめてくれるのだ。飴の箱を持った若い衆のまわりは蟻みたいに子供がウジャウジャたかり、一本口にくわえたまま追加をねだる。でもくれない。意外と、消極的でおねだりしない子供の方がいくつも追加をもらったりする。 「あ〜!?」 「でへへぇ」 実は計算されたしおらしさなんである。なかなかあざとい。 でも、獅子の面に頭を噛んでもらう段になると、子供達は一斉に物陰に隠れてしまう。これを見つけだして獅子面がガブリとやるのだ。 「ぎゃー!」 「いやー!」 ――かたかたかた、がぶ―― 噛まれると、子供は「だー」というような泣き声をもらしながら、何故か歩き出す。家に帰るのかというとそうではなく、とにかく方向を見失いながら、なんでもいいからすたすたと歩き出すのだ。走って逃げるわけでもない。顔をくしゃくしゃにしながら、どういうわけか足取りだけはしっかりと、冷静な歩き方をする。歩いていく方角は全くとんちんかんなのだが。 決まって、親が笑いながら追っかけてって抱き上げる。 「おそろしかったんかぁ?」 「うん」 しゃくり上げる子は、飴を持たされると途端に人が変わって再びはしゃぎ始める。 4〜5才だったオラが、なんでそんな細かい観察をして、しっかりおぼえてるんだろう。今思えばそっちの方が不思議だ。そのくせ、自分が噛んでもらったときのことなど一つもおぼえていない。 家々を回り終えると、最後に岸壁で長い舞いが始まる。舞いと一緒に、5人の曲芸師が代わる代わる芸を披露する。刀をくわえて、切っ先にぼんぼりを乗せたり、そういうのをいくつも継ぎ足して一番上の灯籠をくるくる回して見せたり、とんぼ返りしたり、短刀を5〜6本ぐらいお手玉してみたり、とにかくすごかった。 一つの集落を丸一日かけて回り、その集落にある旅籠に泊まる。 オラが7〜8才の頃には、得体の知れないヤクザものが太神楽のフリをし、似非舞いを舞って礼金だけむしり取り、芸をやらずにスタコラピュー、というのが増えた。 おかげで、山本源太夫も石川宗太夫も、ヤクザものと間違われて相手にされなくなり、段々すたれてしまった。 |
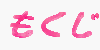
|
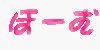
|