【晴れ ところにより二羽カモメ】
Copyright (C) by s-maru 1998
|
5.第三セイコウ丸
とんでもない時化だった。 オラが小学校3年生の冬だ。 あれは海なんてもんじゃなかった。激しく動く山脈だった。風で飛ばされるしぶきがあまりにも多すぎて、海上はどこから空気でどこから水なのか見当もつかなかい。上も下もなかった。 港の中の船は、獅子舞みたいに踊っていた。木造船が一艘、打ち付ける水の力で破壊され、たった一晩で流木の群に変わってしまったのだ。 防波堤に据えられた灯台は、粉々になって港の中に沈んだ。残されたのは、土台から生えだしたように伸びる鉄筋だけだった。径の太い鉄筋が何十本も、引きちぎられたようにねじ切れていた。 そんな時化の中、新潟発舞鶴行の客船が航行していた。避難場所を求めて、やっとのことで若狭湾に入ったというのに、その途端、転覆・沈没してしまったのだ。真夜中の悲惨なニュースだった。 数万トンの鉄船が、ボッキリ折れてしまったと、後に聞いた。 時化が静まった後は、たいてい空は晴れ渡り、穏やかな小春日和になる。 あちこちいたんでしまった定置網は、一旦陸に上げて修理し、もう一度かけ直すしかない。村中の網が全部いたんでしまったのだ。村中の漁師がお互い手伝って、順番に網上げしていく。 うちの網の順番の時だった。 道網を上げていると、毛布だのなんだのと、村人が捨てたのか、難破船の備品だったのか、そういう布きれがたくさん引っかかってくる。臆病な漁師がいて、そばにいる者が 「それ! どざえもんじゃ」 と指さすと、 「どわー!」 と叫んで物陰に隠れてしまう。そして全員の失笑を買う。 何度か繰り返すうち、真に受けなくなった。 赤い布きれが浮かび上がってきた時、臆病な男はどうせ毛布か何かだろうとたかをくくって、自分の目の前まで来ても特にこだわらず網をたぐっていた。 その布きれをつかんで引っ張ったら、人間だったのだ。ものも言わずに座り込んだという。腰が抜けて、もう仕事にならなかった。(後年、アザラシが上がったとき、『アザラシの肉は食えるのか』と、しきりに言っていた男である) 他の漁師達が丁寧にホトケを船に上げて寝かし、港まで運んだ。 村中の者が朝から港で忙しく働いていたので、オラは、学校帰りに港に寄って、その辺でウロウロしていた。漁師達が数人でホトケを抱えて船から上がってきた。ちょうどオラの目の前に寝かせて再び沖へ出ていったのである。 まるで、パントマイムをやるタレントが、マネキン人形の真似をして立っているときのような姿で、ホトケは横たわっていた。白地に青いチェックのネルシャツに、赤いベストを着ていた。紺のズボンをはいていた。なぜか、ズボンのポケットに栓抜きが入っていて、それがこぼれ落ちそうになっていた。 とても死んでいるようには見えなかった。顔が真っ赤だった。きっと、息が苦しくて、ぐっと踏んばったんだなって思った。衣服は全く乱れておらず、腰のあたりから白い肌着が少しのぞいていただけだった。きれいなホトケだった。 ホトケが上がった漁場は、大漁になると昔から言われている。ホトケが感謝して漁をもたらしてくれるというのだ。 年が明けて、修理した網をかけてからというもの、その漁場は一年間ずっと大漁だった。 |
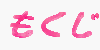
|
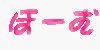
|