【晴れ ところにより二羽カモメ】
Copyright (C) by s-maru 1998
|
4.アリガラという海藻
定置網というのは、海の中に架設しておくものである。つまり待つ漁法だ。海に入れっぱなしだと海藻や貝類が繁殖してしまうので、定期的に入れ替えたり掃除したりする。 夏は特に海藻が繁りやすい。網につくもので最も多いのが「アリガラ」と呼ばれるやつだ。 体調1〜1.5センチ。木人形のピノキオにそっくりな形をしている。肌の質感は、ホンダワラやワカメの芯にも似ている。そいつが、細長いゴム風船を所々ひねって人型にしたみたいな姿をしているのだ。 海藻だから、熱されると緑色になる。 ある時期一気に繁殖して、絨毯みたいにびっしりと網につく。 もうおわかりかと思うが、このアリガラは、ヨタヨタと這って歩く海藻なんである。 両手両足の先っちょが、カブトムシやクワガタなどの昆虫のつま先と似ていて、釣り針みたいなカギになっている。体を伸ばして手のカギで取り付くと、足のカギをはずして体を曲げる。 網を入れ替えるときには、そのアリガラのかたまりの中に手を突っ込んで、船の上に引っ張り上げなければならない。蟻の巣の中に手を突っ込んだみたいなもので、もうウジャウジャなのだ。 軍手に取り付いて手の表面を歩き回る。それほど気持ち悪いわけでもないのだが、結構むかつく。忌々しいのだ。海藻のくせに、虫みたいに這いまわりやがって。 春に多いのは、「馬の背中」と呼ばれる海藻で、まさに馬のたてがみのように、茶黒い毛のようなやつが群生する。こいつは最も始末が悪い。重たいし、振っても落ちないし、網の中が暗くなるから魚が箱網へ入り込まなくなる。 でも、この「馬の背中」は、冬の間に海底から巻き上げられた泥を栄養にして育つ。泥というのは、いろいろな魚類が死んで海底に沈みバクテリアに分解されたやつとか、河から流れてきた泥水の沈殿物などである。 海底は水温が低いので繁殖しない。定置網にこびりついた泥に、「馬の背中」は生える。海全体で言えば、一種の浄化の役割を果たす海藻だ。 そして、この「馬の背中」を、アリガラのやつが好んで食べるのだ。アリガラときたら、海藻のくせに他の海藻を食べるという、植物の食物連鎖がここにある。信じがたいことだが。 陸の植物にたとえて想像してみるとよくわかると思う。根っこと枝を使って器用に歩き回る木があり、そいつが他の木や草をもしゃもしゃと食べているのと同じなのだ。 アリガラの体の中は、ワカメやホンダワラと大して違わない。つまり、単なる海藻で、別に消化器や神経があるわけではない。どこをどう眺め回してみても、海藻以外の何者でもない。 四肢のカギが根の機能を持っていて、そいつを突き刺して栄養分を吸い取るだけなのだ。そして、思考するわけでもないのに、しっかりと他の海藻がいる場所を探し回り、突き止めるとそこに取り付いてしまう。 そのうち、食べ尽くすとミクロ範囲での絶滅と相成る。 こういった変な海藻達は、有害物質を濃縮して体内に貯える。おかげで海が浄化されるわけだが、さらにこれらの有害物質を貯えた海藻や植物性プランクトンなどを、クラゲが吸収し、解毒してしまうのである。解毒というか、クラゲの毒に変えちゃうわけだ。科学的根拠はないけど、きっとそうだ。 敦賀湾の、鯛・ハマチ養殖場で、生エサが海底に沈殿して腐敗し、有毒なプランクトン(赤潮)が大量発生した年、クラゲも大発生した。海の上を立って歩けるほどクラゲがいたのだ。 定置の漁師は、このクラゲにどれだけ泣かされたことかわからない。網の中にどっぷりたまってしまって、網を取り詰めることができない。毎日数百トンものクラゲを、人力ですくい上げて網の外に出し、残った魚をやっとの思いで取っていた。魚も、酸欠で敦賀湾近辺では生きられず、全然回遊してこなくなっていた。水揚げが激減した。 でも、クラゲは赤潮を浄化してくれたのである。そして、サバの子がクラゲを食べる。 海って、うまいことなってるよなぁ。 |
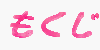
|
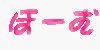
|