【開かれた階段と、くたびれたサンダル】
Copyright (C) by s-maru 1999
|
Vol.03 カワシモのおばちゃん
カワシモのおばあちゃんの頬っぺたに、いつごろからキノコが生え出したの か、村人は誰も知らなかった。それは唐突に、しかしきわめて必然に、発見さ れた。 風のない静かな午後に、気まぐれに吹いた突風がそれである。 カワシモのおばあちゃんがいつもいつも手ぬぐいをかぶるようになったのは、 日差しに耐えられないほど弱ってきたせいなんだろうと誰もが思っていた。 口数も少なくなり、ほとんど村人と口もきかなくなってしまった。人とすれ 違っても顔を背けるように斜め下を見ながら歩く。 それもこれも、手ぬぐいで顔を隠すためだったのだ。 頬茸はひょろひょろと細長く、真横に伸びていた。大人の中指よりも少し長 めで、子供の小指よりも少し細めぐらいだ。枯れた草のツルのような芯の先に は、裏返った小さな傘がついていた。 オラがそれを発見したのは、村人達が突風に遭遇するよりも1週間ほど前の ことだ。 たくさん獲れた魚を近所におすそ分けする「分け魚{いよ}」という、村の 風習からなのだが、子供の頃に可愛がってもらったカワシモのおばちゃんのと ころを訪ねるのは実に25年ぶりでもあったので、ちょっと照れくさい気もし ていた。 おばちゃんはかなり若い頃から後家だったのだが、子供達も孫達も都会に住 んでいて盆と正月にしか帰ってこない。おばあちゃんになってからはずっと一 人暮らしで、寂しがってるんだろうなぁ、と常々思っていた。 玄関を開けて呼ぶと、そこにいるくせに出てこなかった。何度もしつこく呼 んだら、おばあちゃんは後ろ向きに立ち上った。その時に感じた何か絶望的な、 アキラメのような、何とも言えない雰囲気は、物凄い違和感を伴って暗い家い っぱいに広がり、オラは少し怖かった。 漁をしてきた男達からの分け魚を拒絶することは、村人にとって大変罪深い ことである。漁師が、自分の獲ってきた魚を誰かに贈るというのは、単なるプ レゼントとはわけが違う。海で体を張っている男にとって、命を削って得た成 果を親しい人達と共有する、ひとつの象徴が分け魚なのである。 これを受け取らないというのは、つまり「お前の働きなど何の価値もない」 と言っているのと同じで、漁師としての存在そのものを否定する行為なのであ る。 だからおばあちゃんは意を決して立ち上ったのだ。 玄関先までやってきたおばあちゃんは、顔に手ぬぐいをかけておらず、頬茸 を隠していなかった。昔通りのあのやさしい笑顔を作ろうとしているようだっ たが、顔が半分しか動いていないように見えた。 頬茸は、おばあちゃんの左頬の一番高いところ、つまり目の下あたりから生 えていた。結構弾力があるようで、ピーンと真横に突っ張っている。ゆらゆら 揺れてもすぐにその角度を回復する。 オラはかなりひるんだが、とにかく平静を装って気づかないフリをした。 「大漁で……」 そう、ひとこと言ってツバスが2本入ったトロ箱を差し出した。 おばあちゃんは小さくお辞儀をして受け取った。口をハクハクしていたが、 声が出てこなかった。 「え?」 と聞き返した。またハクハクした。 何度か聞き返しているうちに、おばあちゃんは顔を曇らせてしまい、奥へ引 っ込んでいった。後から考えたら、礼を言っていただけなのだと気づく。 それにしてもオラはショックだった。まるで別人だったのだ。いや、そうで はない、おばあちゃんの人格の他に何か別の人格がそこにあって、それが圧倒 的にオラを気押していたような気がしたのだ。 頬茸のことが村の主婦達の間で噂になり、カワシモのおばあちゃんは外を出 歩かなくなった。毎日通っていた山にもいかなくなり、畑もほったらかしにな ってしまった。 近所の人が皆心配して毎日のようにカワシモ家を訪ね、米やおかずを置いて いくのだが、手をつけていないようだった。 隣家の主婦が、都会に住んでいる息子達に連絡して、様子を見に来るように すすめた。息子達は自分の家に引き取ろうとおばあちゃんを説得したが聞き入 れてもらえず、あまりの強情さに負けて引き上げてしまった。 その後、シルバーケア・センターの職員がおばあちゃんを連れに来た。頬茸 を取り除く手術が行われたのかどうかは不明である。 |
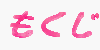
|
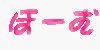
|