【開かれた階段と、くたびれたサンダル】
Copyright (C) by s-maru 1999
|
Vol.02 サンドイッチ
「うっぷ……」 水道の蛇口をあけっぱなしのまま、流しの前で少しだけ息をとられた。 胃薬を流し込んだコップの水をあけてもう一度汲みなおし、一息に飲み干す が、不快感は変わらない。げっぷが鼻について顔の前にふわふわと抜けでて行 くだけである。 「夕べの肉がまだそのまま胃にあるみたいだ……」 時計を見るとまだ0時前ではないか。2時間ほどしか眠ってなかったのだ。 寝室に戻ろうとすると、玄関の呼び鈴がけたたましく鳴り始める。 「誰だよ、今ごろ…… はい、はーい、今あけます、あけますってば」 灯をつけて玄関に向かう。 ドアをあけると、一昨日きっぱりと別れたはずの芳子が、これ以上出来ないっ てくらい明るい笑顔をつくって立っている。でも、まぶたの腫れが引いてなか った。 両手でぶら下げたバスケットには、それまで彼女には縁のなかった可愛いマ スコットがいくつかぶら下がっている。似合わない。 (可愛い女が好きなんだ) 昨日の夜、確かにそう言って彼女の手を振り切った。 暗い街角に泣き叫ぶ声が響きわたった、まだ耳にこびりついている。 「まぁ、上がれよ」 まだ胃がムカムカする。 「うまく作れなくて、夜中までかかっちゃった」 「え? なにが?」 彼女はバスケットをおもむろにあけると、サンドイッチを取り出してテーブ ルに並べた。 「紅茶煎れるね」 「お、おい、ちょっとまてよ、こんな夜中にピクニックじゃあるまいし、食え ねぇよ、こんなもん」 聴こえぬふりをしながら、彼女はせっせとお茶の用意をする。 ため息をついて椅子に座ってると、香ばしい香りとともにレモンティーが運 ばれてくる。 「さ、めしあがれ」 「めしあがれって…… おまえ今何時だと思ってんの?」 そう言いながら、ひとつつまんでみる。 「か、からいじゃねーか、なんだよこれ! 辛子の塊みたいだよ」 「あら、だって悦子が、辛子を入れなきゃサンドじゃないって……」 「ばか、入れるにもほどってもんがあるだろうが!」 「だって、こないだね、悦子んちで作り方習ったんだ、あんた好きだって言っ てたでしょ? サンドイッチ」 「いくら好きでもな、こんな時間にいきなり現れてサンドイッチも何もないだ ろうが、ばっかだなぁおまえって、つくづく」 それまでのつくり笑顔がしゅんとしずみ込んで、うつむいたまま芳子は言い 始めた。 「なによ、いつも人の事馬鹿馬鹿って。そうだよ、あんたはえらいからね」 「おめーなぁ、もう来るなよな」 芳子の目にみるみるうちに涙が溢れ出し、とたんにあたりの物を投げるやら 蹴飛ばすやらわめくやらして暴れだした。ガラスは割れ、本は引きちぎられ、 電話は宙を飛び、とにかくそんな状態が10分間くらい続いた。ダイニングの 片隅で、俺は頭を抱えてうずくまった。 別にショックでも何でもなかった。暴れられようと親切にされようと同じだ った。とにかくこいつとの関わり全てが鬱陶しくて嫌なだけなのだ。 「ばかやろー! てめーんちなんか二度と来るもんか! 誰が夜中にこんなも ん作って持ってきてくれるってんだよ、ちょうしんのるんじゃねえぞ! 頼ま れたってもう来るもんか!」 あっけにとられる俺を残して芳子は去った。 しばらくは口を開けたままぼーっとしていたが、やっとのことで厄介払いが 出来たと胸をなで下ろして、部屋を片付けることにする。割れた花瓶、CD、 月刊の読み物誌、新聞、そのほか壊れていないものは棚にしまい、壊れたもの はごみ箱へ。 だいたい掃除が済んで、最後にテーブルのサンドイッチが残った。 あと、そうだ、それをごみ箱に入れるだけでいいのだ。それだけで、朝にな ればすがすがしい明日を迎える事が出来る。 俺はなぜか捨てられないまま椅子に座ってしばらくそれを見つめていた。 あの可愛げのない女が、別れてみると無性に愛らしくてしかたなく思えてき たのだ。 不格好なそれを一口、口に運ぶ、辛い、涙が出た。 言葉にならない言葉でつぶやく。 「ばかやろー、こんなまずいもんつくるのに、一日中かかりやがって……」 いつのまにか俺はそれを、全部食べていた。 |
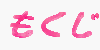
|
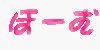
|