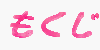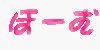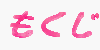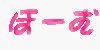|
たぶん、高校の時に紛失したのと同じタイプだと思う。
出品者は古物商らしい。常套句の「譲り受けた商品なので詳しい詳細は分かりません云々……」とのこと。詳しい詳細ねぇ……
でも、FGなんだから別にいいや。
落札価格:5,450円+送料1,600円
表板:松の合板。
裏側板:パリサンドルに良く似た材。アガチスとかいう?
指板:パリサンドルかローズ
駒 :たぶんローズだろう。
ネックが心持ち順反り。ロッドで調整できる範囲。
元オーナーがブリッジのサドル溝あたりを少しペーパーがけしている。サドルはまだ十分余裕があるのだが。何のためだったのだろう……?
|
 |
先細り音叉マーク。このモデルの他にも、フォークタイプで同じヘッドのモデルがあるみたいだ。でも、なくしたギターは買ったのが1973年だし、おそらく製造は1972年あたりのはずなので、この年のモデルでこのタイプはFG-130だけだと思う。
音は、「なんでこんなに良く鳴るの!?」って感じ。さすがはFGである。特有のドンシャリサウンド。さすがに音色は単板モデルのように美しくはないが、FG独特の渋みのある、またツヤっぽさもある、良い音色である。
とにかく板の振動が凄い。低音弦をミュートして弾いても、「どっどっどっど」って響いている。
打ち傷が多くて、そのほとんどが板面に達しているので、今度ペーパーがけして何か塗ってやろうかと思う。
|






|
サドルが、薄っぺらくて斜めに倒れていたので、直すことにする。プラスチックだとばかり思っていたのだが、どうも牛骨のようだ。それなら交換するより肉盛りした方が成形の手間が省けて楽だ。
田園百号のナットを作ったとき、溝を切りすぎた場合の対処法がテキストに載っていた。溝に象牙の粉を詰め込んで、瞬間接着剤を一適垂らして固まるのを待ち、また削り直す。これで完璧に補修できたのであった。
これを応用すれば薄いサドルの肉盛りだって簡単じゃないか。
まず、メモ用紙に象牙の粉を細長く盛る。そこに瞬間接着剤を垂らして、サドルを押し付けてやれば良いのだ。
固まるのに15分ぐらいかかった。
はさみで余分な紙を切り取る。切り出しナイフでバリを取る。
まだ紙の厚みが残っているが、約3.2ミリ。ブリッジの方の溝は3ミリなので、ちょうど良い。
でかい普通のヤスリであらかた削り、サンドペーパー100番〜400番を順次使って仕上げる。もう、境目なんて全然わからない。一本物から削り出したみたいに美しく仕上がった。
|
 |
ブリッジの方のサドル溝が一定でなく、これに合わせて厚みを調整するのに無茶苦茶手間がかかった。弦を張って弾いて見たら、6弦だけがどうしてもチューニングしきれない。さらに弦長調整を行う。もうギリギリだ。
その後ネックの反りを調整したらかなり改善されたが、それでも微妙に6弦だけがチューニングしきれない。3フレットを押さえただけでも少し高い。そればかりか、開放弦でも強く弾くと微妙にシャープする。
弦が悪いのだろうか?
S.Yairiのライトゲージが、リサイクルショップで1セット200円で売られていたのを3セット買い置きし、1セットだけ使ってみたら良くなかったので、あとの2セットが余っちゃってしょうがなかったのを、この際だから使ったのだ。
6弦だけ、振動の軌跡が滅茶苦茶である。良い弦は軌跡が少しずつ楕円になっていき、楕円の角度が微妙に回って行くような振動の仕方をするが、この弦はアミーバのようなモニョモニョの軌跡を描く。
たぶん、振動の乱れがテンションに影響して音程が合わないのだ。
|

|
ところで、ネックの調整である。何故かスパナだけは以前から持っている。なんたってYAMAHA純正ツールだもんね。
-----余談-----
余談だが、良く考えたら12弦ギターの方もこいつで少しは調整できるんじゃないだろうか。
と思ってやってみたら、すげー余裕があった。っていうか、最初からロッドゆるゆるだったみたいだ。全然力入れなくてもスイスイ回ってしまう。これはものすごく意外で、びっくりました。
僕が購入する前は、ロッドゆるゆるのまま弦を張って(つまり鉄芯に頼らずに木材の踏ん張りだけで弦の張力に耐え)ショーウィンドウに10年も飾られていたわけだ。これじゃ、悲惨な元起きになってもしょうがないって。もったいないなぁ。
弦がビリつかない程度しか締めなかったが、それでもかなりチューニングが合うようになった。ロッドはまだかなり余裕がありそうだ。
これなら弓なりになるまで締めてから指板を削って平面を出してやれば、よみがえるかもしれない。ARIAのW-420で用いられた修理方法だ。これならネックをリセットすることなく修理できる。
ただ、当然のことながらフレット打ち直しが必要だ。そのための道具も必要になる。今はまだ予算がない。
-----余談終わり-----
|
 |
ロッドを締める時は、そのまま締めてはいけない。ネックに逆向きの力を加えて、ロッドに余裕を作った状態で締めるようにする。でないと、ただ単にロッドだけを締めこんでいくと、ネックを反らせる力よりもネックの長さを縮めようとする力の方が強く働いて、指板が波打ってしまうのだ。
ひどい場合はネック全体がねじれてしまうこともある。経験者が言うんだから間違いない。えっへん。
(※実は、25歳の時にGIBSONでこれをやったのだった。ロッドを戻したら元に戻ったから良かったものの……。そのすぐ後にYAMAHAへリペアに出したというわけなのだった。ちなみに、当時はYAMAHAの代理店がGIBSONの輸入代理店もやっていたため、YAMAHAでGIBSONのリペアを請負っていたらしい。現在は山野楽器が輸入代理店をやっているので、GIBSONのリペアは全て山野楽器である)
裏返しにして椅子にもたれかけさせ、ヒールのあたりにお尻を乗っけて体重をかける。ヒールの角が睾丸の間の裏すじを刺激するのだが、これには耐えなければならない。なかなか精神力の要る作業である。
こうやって、手塩にかけたギターへの愛は深まっていくのである。
|